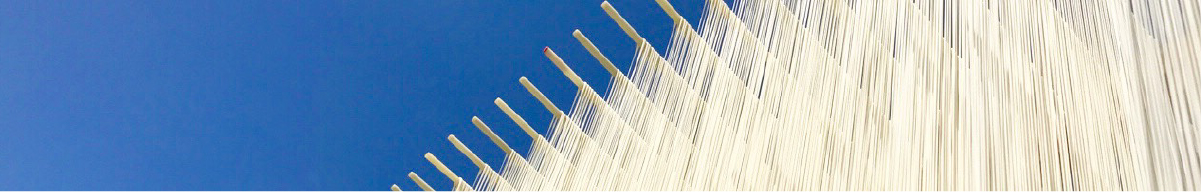【お!いしい けんぶんろく】 Vol.57
メンコレ⑦/唐辛子を練り込んだ麺の“刺激”
私三代目が小豆島に戻り、家業を継いで初めて企画したのが「しょうどしま長命草」を使った「手延べしょうどしま長命草素麺」でした。
それから瀬戸内の特産品として有名な「レモン」を使った「手延べレモン素麺」、ご縁が繋がり池田漁協さんとの出会いから生まれた「手延べひじき麺」、地域での繋がりもある宝食品さんとのご縁で生まれた「手延べきくらげ麺」など、さまざまな手延べ素麺・手延べ麺をつくってきました。
他にも小豆島ならではの「オリーブオイル素麺」や「手延べ黒ごま麺」、他にもOEMとして多くの商品化を手掛けております。
その中で、自社オリジナルの手延べ麺の原料として注目しているのは、やはり香川県や小豆島の特産品です。
香川県は47都道府県の中でも面積が一番小さい県ながら、実は農業が盛んな地域でもあります。
特産品にはオリーブが有名ですが、果物ではみかんなどの柑橘類、いちごやキウイ、ビワ、スモモ、ブドウ、イチジクなど多数あります。
野菜ではブランド品も多く、有名なのは“さぬきのめざめ”と呼ばれる「アスパラガス」をはじめ、キャベツやキュウリ、ナス、トマト、玉ネギなども多く穫れます。
他にもお米のオリジナルブランド“おいでまい”や、小麦のオリジナルブランド“さぬきの夢”などもあります。
こうしてみると、小さな県なのにその農産物パワーを強く感じずにはいられません!
そして今回のテーマの唐辛子も、実は香川県では「香川本鷹」と呼ばれる、辛い辛い唐辛子があるのです。
以下、「香川本鷹」の紹介を「かがわの県産品」サイトから引用してご紹介させていただきます。
輸入品に押されて、姿を消していたスパイス。平成18年、産地であった塩飽諸島の活性化を目的に、香川県や丸亀市などが協力し、幻のトウガラシ「香川本鷹」の復活に向けた取組みがスタートしました。一般的な「鷹の爪」と比べて約2~3倍もの大きさ(7~8cm)で、旨みのある強い辛味が特徴。現在は、「香川本鷹」を用いた様々な加工品が販売されています。
とのことです。<参考サイト>https://www.kensanpin.org/product/processing/1031/
他にも特産品はありますが、こういったさまざまな魅力ある農産物を使い、奇をてらった商品づくりとしてでなく、日々の健康づくりに手延べ麺を上手く活用していただけるような、そんな目標を描きながら人に「よりそうめん」をこれからも目指していきたいと思います。
今回のブログでは、唐辛子(に近い物を含めて)について調べました。
辛いけれどためになる内容だと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。

※写真はPhotoAC「トウガラシ」より
【目次】
① 唐辛子は中南米原産。七味は日本オリジナル!
② 辛み成分カプサイシンを適度に摂って健康増進!
③ 虫除けや魔除けにも使われる!唐辛子の活用法いろいろ
④ 調味料、麺料理、汁ものなど多彩!日本の唐辛子料理
⑤ 激辛から辛くないものまで!世界の唐辛子料理
⑥ 唐辛子を練り込んだ素麺や、素麺以外の麺あれこれ
⑦ 《美味しい手延べ素麺》手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)
① 唐辛子は中南米原産。七味は日本オリジナル!
唐辛子は、中南米原産のナス科トウガラシ属の果実です。紀元前7000~8000年頃にはペルーやメキシコで栽培されていたそうです。
1世紀頃のペルーの遺跡から、唐辛子模様の織物が発見されているとのことです。
世界各国へ広がるのは15世紀以降です。
胡椒やナツメグ、シナモン、クローブなどの香辛料が高値で売買されていた大航海時代、インドの胡椒を求めて航海していたコロンブスが西インド諸島にたどり着いて唐辛子と出会い、1493年にスペインへ最初の唐辛子を持ち帰りました。
当初は観賞用として栽培されていましたが、次第に香辛料の需要が高まっていたヨーロッパへ広まりました。
唐辛子はどの地域でも比較的栽培しやすく、各地で固有の品種が育ちました。
他のスパイスと合わせやすかったことから、各国で独自のミックススパイスや調味料が発達したと考えられています。
ちなみに唐辛子の英語名「Red pepper」は、コロンブスが唐辛子を胡椒の仲間と勘違いしたことに由来しているそうです。
16世紀前半にはヨーロッパ人がインドへ唐辛子を持ち込み、17世紀以降、香辛料として様々な料理に用いられるようになりました。

※写真はPhotoAC「海外の八百屋さん」より
日本への伝来については、諸説あります。
1543年の鉄砲伝来とともに持ち込まれたという説。
1552年頃、キリスト教の宣教師が豊後国(現大分県)の大名である大友義鎮に唐辛子の種を献上したという説。
16世紀末、豊臣秀吉が朝鮮出兵した折、加藤清正が持ち帰ったという説など。
唐辛子が日本に入った当初は、その辛みから毒として扱われたり、足袋に入れてしもやけ予防に使われたりしたとのことです。
1625年、江戸両国橋近くの薬研堀で、七味唐辛子がつくられました。
これが日本初のミックススパイスだそうです。
1760年過ぎには平賀源内が唐辛子図鑑「番椒譜」を記しました。
イラスト付きで50種以上紹介したそうです。
1923年、エスビー食品の創業者である山崎峯次郎氏が、純国産の本格的なカレー粉の製造に成功しました。
家庭の食卓にカレーやウスターソースが上るようになり、それらの原料として使われるようになった昭和初期から、日本で唐辛子の栽培が本格化したそうです。
1971年、神田のせんべい店「神田淡平」が、一味唐辛子をたっぷりまぶした激辛せんべいを発売。
1984年には湖池屋がチリをまぶしたスティックタイプのポテトチップス「カラムーチョ」を発売し、激辛ブームの火付け役となりました。
現在では、唐辛子に含まれるカプサイシンの脂肪燃焼効果などの健康機能にも注目が集まっています。

※写真はPhotoAC「カレーライス」より
唐辛子には数多くの品種があり、辛味種と甘味種に分けられます。
辛味種としては、日本で主流の「鷹の爪」、沖縄の伝統野菜として知られる「島とうがらし」、完熟すると鮮やかな赤色になる「韓国とうがらし」、メキシコ原産でサルサソースに使われる「ハラペーニョ」など。
甘味種には、肉厚で軟らかい京野菜の「万願寺とうがらし」、細長い「伏見とうがらし」などがあり、ピーマンやパプリカ、シシトウも甘味種に含まれます。
日本で消費される唐辛子の大半は輸入に頼っていますが、日本各地で在来品種の栽培が受け継がれています。
青森県の「清水森ナンバ」、新潟県の「山古志かぐらなんばん」、奈良県の「ひもとうがらし」、岐阜県の「あじめコショウ」、石川県の「剣崎なんば」などがあります。
九州をはじめ一部の地域では唐辛子を「こしょう」と呼ぶことがありますが、「柚子胡椒」の「胡椒」は唐辛子のことです。
普通の黒い胡椒のことは「洋こしょう」と呼んで区別するとのことです。
また、北海道や東北では「なんばん」、長野では品種によって「なんばん」と「こしょう」の両方の呼び方が使われているそうです。

※写真はPhotoAC「万願寺とうがらし」より
<参考サイト>
・唐辛子
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E8%BE%9B%E5%AD%90
・唐辛子の歴史と日本に伝わった経緯
https://www.togarashi.co.jp/blog/2017/08/13/history/
・唐辛子はどこから来た?世界一辛いものは?スパイスの基礎講座〜後編〜
https://brutus.jp/spice_knowledge02/
・とうがらしの歴史
https://hotcity-ohtawara.jp/history/
・[とうがらし]選び方と料理のポイント
https://www.kagome.co.jp/vegeday/yasai/red-pepper/
・[とうがらしの種類]辛味や甘味が生きる、料理や調理法とは?
https://www.kagome.co.jp/vegeday/store/201908/9877/
・唐辛子を何と呼ぶ? なんばん? こしょう?
https://tenki.jp/suppl/romisan/2021/08/08/30517.html
・みんなの農業広場 在来品種の紹介【トウガラシ編】
https://www.jeinou.com/benri/vegetable/fru-vege/2016/11/110940.html
② 辛み成分カプサイシンを適度に摂って健康増進!
生の唐辛子はβカロテンを多く含み、緑黄色野菜に分類されます。
ビタミンCが豊富で、夏バテ防止に役立ち、うま味成分のグルタミン酸も含まれています。
辛み成分のカプサイシンは、種を支えるワタの部分(胎座)に多く含まれ、果実が小さい品種ほど多く含まれます。
熱に強く、加熱したり熱いものに加えたりしても辛さが残り、また丸ごとよりも細かくしたほうが辛みが強くなるそうです。
辛みの正体は痛みであり、舌の痛覚神経を刺激することで辛みとして作用します。
過剰に摂取すると胃腸に問題を起こしたり、皮膚の弱い部分に付着すると激しい痛みを引き起こす場合があります。
唐辛子の辛さは、カプサイシンの量を測定して数値化した「スコヴィル値」で示されます。
世界一辛いとギネスに認定されている「キャロライナ・リーパー(=キャロライナの死神)」という品種は300万スコヴィル、鷹の爪は4万~5万、ピーマンは0だそうです。
カプサイシンが体内に入ると、血液によって全身に運ばれ、脳や脊髄などの中枢神経を刺激します。
その刺激が副腎皮質に伝わり、アドレナリンというホルモンが分泌されます。
体脂肪の分解を促進するアドレナリンがエネルギーの代謝を盛んにすることで、効率良く脂肪を燃焼させるため、肥満予防の働きが期待されています。
また、カプサイシンがエネルギーの代謝を活発にさせることにより、体温が上昇して発汗が促進されます。
血流を改善する働きも期待できます。
カプサイシンを含む唐辛子を料理の味付けに使うことで、塩分の摂りすぎを防ぎ、高血圧予防になると考えられています。
他にも、コレステロール値の上昇を抑える、冷え性を改善する、食欲を増進する、疲労を回復する、便秘を解消する、などの作用があるとされています。

<参考サイト>
・スコヴィル値
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AB%E5%80%A4
・食べるだけじゃない、とうがらしの辛さの秘密
・唐辛子:歴史、健康効果、味わい、そして辛さの科学
https://omoshirozatsugaku.jp/entry/2024/05/18/211003
・カプサイシン
https://himitsu.wakasa.jp/contents/capsaicin/
③ 虫除けや魔除けにも使われる!唐辛子の活用法いろいろ
料理に辛みを付け、味のアクセントとなる唐辛子は、実を生のまま食べる場合と、乾燥させて使う場合があります。
乾燥させた唐辛子の実をすりつぶして粉末にした調味料が「一味唐辛子」です。
これに他の薬味や香辛料を混ぜたものが「七味唐辛子」で、調味料ではなく薬味として使用されます。
メーカーにより原料が異なりますが、山椒・麻の実・黒ゴマ・青海苔・ケシの実・チンピなどが使われます。
辛さに加えて香りづけができるので、素麺やうどんなどの麺類、牛丼などの丼もの、豚汁などの汁ものといった和食にほどよい刺激と風味を与えてくれます。
唐辛子を使った調味料や香辛料、醤油・酢・食用油・泡盛などに漬け込んだものも、国内外で多様に使われています。
唐辛子味噌、柚子胡椒、コーレーグース、コチュジャン、豆板醤、ラー油、タバスコ、チリソース、デスソースなどがよく知られています。
食用以外にも、鑑賞用や、様々な実用的な用途に役立てられています。
古くは民間療法として、靴の中に入れてしもやけ予防、腹巻に入れて防寒などに用いられていました。
現代でも繊維に唐辛子を練り込んだ機能性肌着や靴下が販売されています。
カプサイシンの防虫効果を活かして米びつ内の虫よけとして入れる、殺菌・抗菌作用を活かしてぬか床に入れる、などの生活の知恵もあります。
園芸では虫害を減らす目的で、他の作物とともに植える、唐辛子とニンニクを焼酎に漬け込んだ液を薄めて自然派農薬として植物に散布する、なども行われているそうです。

※写真はPhotoAC「米びつに入れた米」より
唐辛子を魔除けやお守りに使う国もあります。
中国や韓国、日本などでは、赤が縁起の良い色とされています。
中国では唐辛子を「火・炎の食材」としており、火は汚れを浄化する力があると信じられ魔除けとされてきました。
また赤はエネルギーを高める力を持ち、活動的になる、自信を持つ、情熱的になるにより幸運をもたらすことが期待されています。
アメリカのニューメキシコ州では唐辛子が幸運を呼ぶとされており、「Chile Ristra(チリリストラ)」と呼ばれる吊るし飾りが古くからお守りとして伝えられています。
インド(ヒンドゥ教)では、家の入り口から悪いものが入ってこないように、唐辛子・レモン・唐辛子の順に糸で通した「魔除けの飾り」を吊るす風習があるそうです。
イタリアでは、赤唐辛子が「Evil Eye(邪眼)」とよく似ていることからお守りとして使用され、災いや邪悪な視線を払い除け、悪運を断ち切る効果があると考えられています。

※写真はPhotoAC「イタリア観光-ナポリの路地」より
<参考サイト>
・一味唐辛子と七味唐辛子の違いとは?使い分けてもっとおいしいピリ辛レシピ5選
https://www.kurashiru.com/articles/5aa5d12b-abbb-4dc7-a03c-14838797c2f8
・唐辛子が縁起物としてお守りなどに使われる理由は?
https://ja.chili2mag.com/chilipepper-as-an-amulet/
・インドの魔除け
・《唐辛子の吊るし飾りの意味・由来》厄除け魔除けになるのはなぜ?
https://miloru.com/ristra-and-cornicello-and-chili/#google_vignette
④ 調味料、麺料理、汁ものなど多彩!日本の唐辛子料理
日本の郷土料理と言えば和食、和食と言えばやさしい味、というイメージがありますが、調べてみると、唐辛子の辛みをきかせた調味料や料理、辛くない唐辛子の揚げものや炒めものなど、バラエティ豊かな料理が各地で食されているようです。
いくつかご紹介します。
【三升漬け】(北海道・青森県)
青なんばん(青唐辛子)・麹・醤油をそれぞれ、一升ずつの分量で漬け込み熟成させた郷土料理。
東北地方では、一升漬け(いっしょうづけ)・麹南蛮(こうじなんばん)とも呼ばれている。
ご飯に乗せたり、野菜にかけたり、調味料としても使われる。

※写真はPhotoAC「三升漬け」より
【切腹南蛮】(福島県)
青なんばんに切れ目を入れて種を取り除き、味噌を入れてシソの葉で巻いて油で揚げる。
夏の暑さを乗り切る農家の料理。
【ベンケイ】(福島県)
南相馬市原町区の萱浜地区(特に北萱浜)に伝わる郷土料理。
ダイコンと芋がら(里芋の茎を干したもの)に赤唐辛子を入れ、醤油・砂糖で炒り煮する。
お正月用の保存食として、またハレの日の食べ物として重宝された。
【かんずり】(新潟県)
妙高市(旧新井市)に伝わる伝統的な発酵調味料。
地場産の唐辛子を雪の中にさらしたのちにすり潰して米麹と柚子、塩を混ぜ、3年間熟成・発酵させる。
厳しい寒さで冷え切った体を温めるために食べたと言われている。
【べっこう】(東京都)
伊豆諸島の郷土料理。
旬の魚を島とうがらし醤油に漬け込む。
切り身がつややかなべっこう色になることからそう呼ばれる。

※写真はPhotoAC「べっこう寿司」より
【やたら】(長野県)
主に北信地域で食べられている郷土料理。
ミョウガやナスなどの夏野菜、ぼたんこしょう、ダイコンの味噌漬けを刻んで混ぜ合わせ、あたたかいご飯にかけて食べる。
「ぼたんこしょう」は、古くからこの地域で栽培されてきた青唐辛子。
【すりだね】(山梨県)
赤唐辛子をベースにゴマや山椒を加えた、富士吉田発祥の万能調味料。
ほうとうや吉田のうどんには、一味や七味ではなくすりだねが使われる。
【つぎ汁】(岐阜県)
郡上市明宝寒水(かのみず)地区の郷土料理。
唐辛子をから煎りして出汁で煮出し、小さく角切りにした硬めの地豆腐を加え、醤油や砂糖で味をととのえるお吸いもの。別名「辛汁(からじる)」。
毎年10月に寺院で行われる報恩講の際、参拝者に振る舞われる。
【から大根】(福井県)
永平寺町京善地区に伝わる郷土料理。
冠婚葬祭や仏事に食されてきた。
ダイコンを軟らかく煮て唐辛子を加え、擦った黒ゴマ・砂糖・醤油・みりん・酒を混ぜ合わせたものを入れて煮詰める。
から大根の「から」は唐辛子の「から」で、ピリッとからいのが特徴。
【きごしょう】(京都府)
京都市伏見区付近で栽培されていた伝統野菜「伏見とうがらし」の若い葉を茹でて炒め煮にする。
辛みのない伏見とうがらしの若い葉は「きごしょう」と呼ばれ、軟らかく、ほのかな唐辛子の風味と独特の苦みが特徴。
真夏のおばんざいとして親しまれている。

※写真はPhotoAC「葉とうがらし」より
【万願寺とうがらしとじゃこの炊いたん】(京都府)
辛みのない「万願寺とうがらし」を、ジャコと一緒に出汁・醤油・みりん・酒を入れてに含める。
「炊いたん」は、出汁をじっくり染み込ませるように炊いてつくるおかずのこと。
夏の家庭料理として親しまれている。
【とうがらし味噌】(奈良県)
大塔村や天川村で昔から家庭でつくられてきた調味料。
ニシンの干物に、刻んだ生唐辛子と味噌、砂糖を加え煮詰めてつくっていた。
家庭ごとに材料が微妙に異なり、現代では刻んだピーマンやパプリカ、ツナ缶等も使われるとのこと。

※写真はPhotoAC「唐辛子味噌のおにぎり」より
【なすそうめん】(香川県)
旬のナスを油で炒め、油揚げと唐辛子を加え、出汁・醤油・砂糖で煮て、硬めに茹でた小豆島特産の素麺を入れる。
汁を冷やしても美味しく食べられる。
食欲のない暑い夏にも食べやすく、夏バテ防止にも役立つとされる家庭料理。
【辛子明太子】(福岡県)
博多名物として有名。
「明太子」の語源はスケトウダラを意味する朝鮮語「明太(ミョンテ」。もとは韓国から輸入されていた、スケトウダラの卵巣を発酵させ唐辛子・ニンニク・ゴマなどを合わせた伝統的な食べもので、朝鮮半島との交流が盛んな福岡・北九州・下関などの地域で売られていた。
第二次世界大戦後に朝鮮から帰還した日本人が、唐辛子を用いた調味液に漬け込む独自の方法で製品化し、博多で販売を開始したのが始まりとされる。
【辛麺】(宮崎県)
宮崎県発祥のラーメン。
大粒の大量のニンニクと、唐辛子によって生み出されるうま味と辛みが混在するスープが特徴。具材にはニラ、溶き卵、ひき肉が入る。

※写真はPhotoAC「辛麺」より
<参考サイト>
・北海道の郷土料理 三升漬け
・【切腹南蛮/福島県】名前に驚き!爽やかなコクに二度驚き!!これぞ農家を支える夏の味です。
https://furusato-gohan.jp/fukushima-seppukunanban/
・郷土料理「ベンケイ」
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/43/ouchidekyoudoryouri_benkei.pdf
・かんずり 新潟県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kanzuri_niigata.html
・べっこう
https://oshima-navi.com/gourmet/bekko01.html
・やたら 長野県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/yatara_nagano.html
・人気の無添加すりだね通販】ほうとうや吉田のうどんにかかせない辛味すりだねの特徴・使い方・レシピ
https://yoshidanoudon-suridane.net/about-suridane/
・つぎ汁 岐阜県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/38_24_gifu.html
・福井県 から大根
https://www.zengakuei.or.jp/kyodosyoku/pref/fukui_02.html
・きごしょう 京都府
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kigosho_kyoto.html
・万願寺とうがらしとじゃこの炊いたん 京都府
・とうがらし味噌
http://nara-shokubunka.jp/yamato/17-09.html
・なすそうめん 香川県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/nasu_soumen_kagawa.html
・辛子めんたいこの話
・明太子の語源は韓国!名産地が福岡県となった背景・歴史を解説
https://chikaefoods.co.jp/?p=1034
・宮崎県 辛麺
https://kyoudo-ryouri.com/food/2151.html
⑤ 激辛から辛くないものまで!世界の唐辛子料理
カレーや麻婆豆腐はもちろん、世界中の料理に唐辛子が使われています。
暑い国で好まれるというよりは、古くから胡椒などのスパイスが使われておりスパイシーな味になじみがあった国で、唐辛子が受け入れられたようです。
世界各国の唐辛子を使った料理にはどんなものがあるか、いくつか調べてみました。
【キムチ】(韓国)
キムチは韓国の漬物の総称で、朝鮮半島に唐辛子が伝わる以前は、食材の色や味を活かしたキムチが多かったとのこと。
18世紀頃から、糸唐辛子が飾りとしてキムチに使われるようになり、18世紀後半には小さい甲殻類である「アミ」の塩辛入りのキムチが出現。
20世紀には粉唐辛子入りの赤いキムチが朝鮮半島南部で好まれるようになり、朝鮮半島によって全土に拡大した。
【ダクバル・チム】(韓国)
鶏足のスパイシーな煮込み。
韓国唐辛子やコチュジャンチリソースなどのスパイスを加えた、舌が引き裂かれるような辛さが特徴。
スパイシーで濃厚、カリカリとした風味が人気の屋台の食べ物。

※写真はPhotoAC「チゲスープ」より
【泡辣椒(パオラージャオ)】(中国)
辛い料理で知られる四川省の家庭でつくられている、生の唐辛子を塩水に漬けて乳酸発酵させた食品。
辛みと酸味が絶妙で、刻んで調味料として使ったり、漬け物として食したりする。
【四川火鍋】(中国)
四川唐辛子をはじめ様々な種類の唐辛子を使った、舌がしびれるようなスパイシーな味のスープが特徴。
胡椒、シナモン、アニスなどの多くの辛いスパイスも使用されている。
2つに分かれた独特のデザインの鍋に、辛いスープと、辛くないスープを入れる場合も。

※写真はPhotoAC「火鍋 四川」より
【担々麺】(中国)
汁はなく、醤油・唐辛子・辣油・粉山椒・酢・ゴマ油・ネギのみじん切り・ペースト状にすったゴマ・すりつぶしたニンニクなどでつくった独特のタレを、麺と和えて食べる。
辛さには、舌を麻痺させるような山椒(花椒)の「麻」、ピリッとくる唐辛子の「辣」の2種類がある。
この2種類の辛さを微妙なバランスで配合するのがポイント。

※写真はPhotoAC「旨辛担々麺」より
【ビャンビャン麺】(中国)
中国の陝西省(せんせいしょう)の郷土料理。
汁なしでたれを絡めて食する。
酢・塩・醤油・ニンニク・唐辛子・花椒などで味付けし、ピリッと辛いのが特徴。
具材には、ネギや豚肉、さっとゆがいたモヤシや小松菜などが使われる。

※写真はPhotoAC「ビャンビャン麺」より
【オレック・サンバル】(インドネシア)
ハバネロ、カイエン、ジャネット、チリ、スパニッシュ、ジョロキア・ナガ・ペッパーなど、世界で最も辛い唐辛子からつくられた、辛さが特徴のチリソース。
生唐辛子を裏ごしし、本来の辛みをそのまま残している。
【ゲーン・タイ・プラー】(タイ)
タイ南部の伝統的な料理。
様々な種類の唐辛子と、「タイ・プラー」という魚の内臓を発酵させたソースを使ったカレーで、ご飯とともに食べる。
【オタク・オタク】(東南アジア)
インドネシア、マレーシア、シンガポールなどの東南アジア諸国で人気のある、スパイシーなかまぼこ。
魚のピューレと各地域の代表的なスパイスを組み合わせてつくる。
唐辛子の辛みと、ショウガ・ラッキョウの強い香り、魚の脂の甘みが調和した魅力的な味わい。
【エマ・ダツィ】(ブータン)
ブータンでは唐辛子(エマ)は野菜として扱われており、唐辛子をふんだんに使った料理が多く「世界一辛い料理」とも称される。
「エマ・ダツィ」は、国民食とも言える唐辛子のチーズ煮込み。
ダツィはチーズの意味。
主に青唐辛子が使われる。

※写真はPhotoAC「エマダツィ」より
【パクシャ・パー】(ブータン)
豚肉(パクシャ)と唐辛子の煮込み料理。
通常はこれにジャガイモやダイコンなどの野菜を1品加えたものが多く見られる。
【ペペロンチーノ】(イタリア)
ニンニクと唐辛子のオイルベースのパスタ料理。
イタリア語で「ペペロンチーノ」は唐辛子の意味で、正式な料理名は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」。

※写真はPhotoAC「ペペロンチーノ」より
【ンドゥーヤ】(イタリア)
唐辛子を使った激辛の料理で知られている南部のカラブリア州の、非常に軟らかいサラミ。
豚肉の内臓が主原料で、肉1kgに対して唐辛子250gが使用されるとのこと。
薄くスライスしてパンに乗せたり、スープやピザ、パスタの調味料として使ったりする。
【グヤーシュ】(ハンガリー)
ハンガリーの伝統的な煮込み料理。
牛肉を、ジャガイモ、ニンジン、タマネギ、ピーマンなどの野菜、パプリカパウダー、その他のスパイスと一緒に煮込む。
辛みの少ない唐辛子のパプリカパウダーが使われる。

※写真はPhotoAC「ハンガリー ブダペスト料理グヤーシュ」より
【ケイ・ワット】(エチオピア)
エチオピアは、アラビア半島やインドとの香辛料貿易が盛んに行われた影響を受け、スパイスを使った料理が多くある。
乾燥させた唐辛子・ニンニク・コリアンダー・カルダモン・クローブなど15種類前後のスパイスを混ぜてつくるミックススパイス「ベルベレ」を使った伝統的なシチューが「ケイ・ワット」。
【クレオールシュリンプ】(アメリカ)
アメリカ南部の料理。
チリペッパーとカイエンペッパーの2種類の辛みの強い唐辛子を使う。
エビの甘み、トマトのマイルドな酸味、タマネギ、ニンニク、胡椒などのスパイスの強い香りが調和した味わい。
【チリコンカン】(アメリカ)
テキサス州で生まれた料理で、アメリカでは国民食のひとつ。
豆、ひき肉、トマトを唐辛子で煮込んで、スパイシーに仕上げた料理。

※写真はPhotoAC「チリコンカンとタコス」より
<参考サイト>
・キムチの歴史とキムジャン文化
https://www.atcenter.or.jp/kimchihistory
・世界一のトウガラシ好きはどの国? 世界で愛されるトウガラシと、日本の“ご当地”トウガラシとは?
https://tenki.jp/suppl/okuyuki/2015/05/29/4081.html
・世界で最もスパイシーな料理 10 品を通して料理を探求
・トウガラシを乳酸発酵させた調味料は、うまくて辛くて自分でも作れる
https://dailyportalz.jp/kiji/180820203730
・(常温)泡辣椒(パオラージャオ) 500g
https://www.kojuken.jp/shopdetail/000000000111/
・担々麺
https://world-noodle-dictionary.com/asia/china/%82%B3%82%B5%82%B7%82%B9%82%BB.html
・ビャンビャン麺とはどんな料理?特徴・味わい・話題の漢字もご紹介!
https://delishkitchen.tv/articles/2284
・ゲーン・タイ・プラー
・ブータンの食文化について
https://dragontours.jp/about_food.html
・ペペロンチーノの正式名称は?意味やおすすめのレシピをご紹介!
https://delishkitchen.tv/articles/1568
・ンドゥーヤは庶民の味方?カラブリアの激辛郷土料理を支える食材とは
https://www.kameyaweb.co.jp/aec/user/catalog_shohin_list?ct=3146
・ハンガリーの国民食。ハンガリー産のパプリカが味の決め手!
https://www.bras-de-chef.com/selection/%E3%82%B0%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5-gulyasleves/
・エチオピアの食文化の特徴は? 「ベルベレ」などスパイスをふんだんに使った料理が多数
https://www.mylifenews.net/column01/37771/
・食べれば発汗!思わず快感! 世界の唐辛子料理
https://www.sunwood.co.jp/sunwoodclub/webmagazine/magazine_201712_2.html
⑥ 唐辛子を練り込んだ素麺や、素麺以外の麺あれこれ
唐辛子を麺に練り込んだものを調べてみたら、素麺やうどん、インスタントラーメンなど、様々な麺がつくられていましたので、いくつかご紹介します。
【とんがらし麺】(日清食品)
大手食品メーカーがつくる、唐辛子を麺に練り込んだカップラーメン。
現在は「うま辛海鮮チゲ」「うま辛トマトクリーム&チーズ味」がラインアップ。
過去には焼きそば、うどんも販売されていた。
【播州唐辛子うどん】(森口製麺製粉)
北海道産小麦のみを使用し、唐辛子粉末を練り込んだスパイシーな辛さのある乾麺のうどん。
サラダ風や、炒めて焼きうどんにするのがおすすめとのこと。
【匠ぴり麺】(くまの農業振興公社)
三重県熊野市産の唐辛子「プリッキーヌ」を練り込んだラーメン用の生麺と、スープのセット。
市内産のハバネロとプリッキーヌ、ハラペーニョに、香酸かんきつ「新姫」と梅の粉末を混ぜた、専用の薬味「熊野三昧」も開発したとのこと。
【とうがらし麺】(金城製麺所)
沖縄県石垣島の製麺所がつくる、存在感のある唐辛子とガーリックパウダーを練りこんだ生麵。
焼きそば、パスタ風にしても、スープでも楽しめるとのこと。
【とうがらし麺】(内藤とうがらし)
江戸時代の宿場町、内藤新宿界隈で生産されていたものが現代に復活し、伝統の江戸東京野菜に認定された「内藤とうがらし」。
辛み・風味が特徴の内藤とうがらしを使用した、包丁切平打ち麺。
パスタ・和の麺・中華風など様々なレシピの麺料理で楽しめるとのこと。
【島とうがらし味噌ラーメン】
東京の隠れたご当地激辛ラーメン。
八丈島の島唐辛子を麺の中にふんだんに練り込んだ、激辛麺と風味豊かな合わせ味噌がマッチしたインスタント袋ラーメン。
【手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)】(島食品)
沖縄県多良間島産の島唐辛子の粉末を練り込んだ手延べ素麺。
鮮やかなオレンジ色が特徴。

※写真はPhotoAC「多良間島 空撮」より
<参考サイト>
・日清食品、業界初の唐辛子練り込み「とんがらし麺」開発
https://news.nissyoku.co.jp/foodsnews/nss-8638-0002
・日清のとんがらし麺
https://www.nissin.com/jp/product/brands/tongarashi/
・「日清のとんがらし太麺」2品 (5月24日発売)
https://www.nissin.com/jp/company/news/1894/
・播州唐辛子うどん
https://moriguchi-seifunseimen.com/?pid=180090719
・熊野産の唐辛子を使ったラーメンいかが 農業振興公社が販売
https://www.chunichi.co.jp/article/402676
・金城製麺所 とうがらし麺
https://www.kinjoseimen.com/products/detail/84
・内藤とうがらし とうがらし麺
・内藤とうがらしとは
https://naito-togarashi.tokyo/about/
・島とうがらし味噌ラーメン 八丈島 唐辛子練りこみ麺 激辛 東京都ご当地ラーメン
https://ec.line.me/foods/noodles_pasta/product/7876066989/
・手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)1袋
https://shimafoods.theshop.jp/items/85519335
⑦ 《美味しい手延べ素麺》手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)
前述しましたが、沖縄県多良間島産の島唐辛子の粉末が練り込まれた手延べ素麺です。
とある、YouTubeの動画でも紹介されていましたが、まずは素麺のうま味があり、後からじわじわと辛さがくるそうです。
「ビールにあう〜」と絶賛されているのを見ると、ビールと一緒に食べてみたい気になります。
麺は茹でるとより一層、キレイなオレンジ色をしていて、見た目は辛そうですが、うま味と辛さが丁度良い?感じだと思います。
夏にぜひ食べてみたい素麺ですね。
上でも書きましたが、唐辛子に含まれるカプサイシンは発汗作用だけでなく、体調を整えてくれる作用に働いたり、脳にも良いそうですから、健康麺を考えてもこれからの暑くなる日には毎日(?!)食べていきたい素麺です。
先日のブログでご紹介させていただいた、「泡盛の酒粕を練り込んだ手延べ素麺」「月桃を練り込んだ手延べ素麺」そして今回の唐辛子を練り込んだ素麺は、沖縄の那覇市牧志にある「酔処 玉川(たまりば)」さんでも食べられるので、沖縄に行ってぜひ食べ比べをしたいものです!

※写真は、出汁専門店 島食品様公式ネットショップより引用させていただいています。
《出汁専門店 島食品公式ネットショップ》 https://shimafoods.theshop.jp/
《手延べそうめん(多良間島唐辛子入り)》 https://shimafoods.theshop.jp/items/85519335
《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。