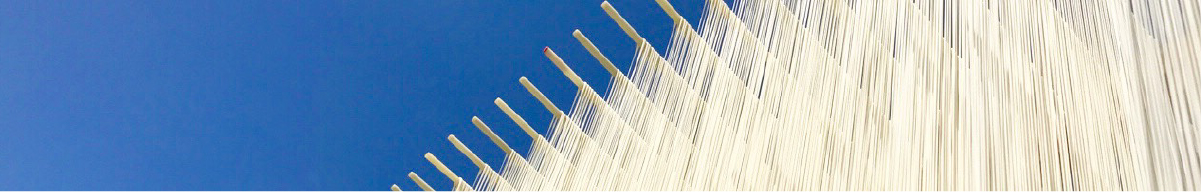石井製麺所通信
2025年8月16日 【Vol.64】メンコレ⑩/ショウガを練り込んだ麺の“温もり”
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.64
メンコレ⑩/ショウガを練り込んだ麺の“温もり”
例年、皆さまからのご注文や発送も落ち着きを見せるお盆シーズン。
今年は異常な暑さのせいか、ありがたいことにご注文が途切れません。
当然、製造もフル回転で稼働しております。
また、この時期のご注文は個人のお客様がほとんどですが、今年はOEM商品や業務用のご注文なども多く、いかに今年の夏、素麺が必要とされているかを強く感じております。
まさに嬉しい悲鳴です。
(本当に嬉しいです)
とはいえ、9月以降の製造・販売計画や北海道への視察旅行、年末に向けてギフト商品など考えないといけないことも盛りだくさんで、「こんな無茶は来年できないな…」と思いながら歳を重ねる身体に不安を感じます。
もちろん、父、母の身体のことが最優先で考えてはいきたいのですが、この8月だけは、まずは製造、発送作業に集中して乗り切りたいと思います。
あと、ご注文の多さにふと頭をよぎるのは、「米不足」による主食の変化…もあるのかなと感じております。
皆さまのお食事の「主食」、変化はどうでしょうか?
暑い時期にお米を炊いて食べるのはなかなか億劫になってしまいますかね。
素麺も茹でるためにはお湯を沸かしますが、その後はヒンヤリとした冷たい素麺を冷たいツユでいただくと、暑い夏は格別です。
日本人にとってお米の美味しさは欠かせないし、米不足といっても、素麺にお鉢が回ってくることはなかなかないと思っていましたが、この夏は素麺が求められていることを実感します。
あと何日、このような酷暑が続くのか分かりませんが、皆さまもお身体にはくれぐれもご注意いただき、健やかにお過ごしください。
さて今回のブログでは、暑い夏ですが、新生姜の季節に合わせて「ショウガ」について調べてみました。
そういえば、素麺の薬味で「ショウガ派」と「ワサビ派」がいらっしゃるそうですが、皆さんはどちらですか?
お時間許せば、ぜひご一読ください。
写真は、8月15日におこなわれた「小豆島まつり」での花火の様子です。
ちなみに石井製麺所の真横です。
徒歩1分で花火観覧のVIP席です(笑)。

【目次】
① 薬用に!香辛料に!ショウガの歴史と現在
② ショウガ特有の栄養成分で身体を温めて健康UP!
③ 無病息災を願う!?ショウガの活用法いろいろ
④ 定番からお菓子や飲み物まで!日本のショウガ料理
⑤ カレーからスイーツまで!世界のショウガ料理
⑥ ショウガを練り込んだ素麺や、素麺以外の麺あれこれ
⑦ 《番外編》小豆島まつり
① 薬用に!香辛料に!ショウガの歴史と現在
ショウガはショウガ科の多年草で、原産地はインドからマレー半島にかけての熱帯アジアが最も有力と考えられています。
インドでは紀元前300~500年前から保存食や医薬品として使用されており、中国でも紀元前から栽培され、孔子の「論語」の記述によると紀元前650年には食用として利用されていたようです。
漢方の生薬の1つ「生薑(ショウキョウ)」としても重用されてきました。
ヨーロッパには紀元1世紀頃に伝来しましたが、栽培に適した気候ではなかったことから、輸入され主に生薬として利用されました。
その後、13~14世紀には香辛料として一般的に利用されるようになりました。
15世紀末に新大陸が発見されると、16世紀の初めにスペイン人がジャマイカに移植し、16世紀半ばには西インド諸島はショウガの産地となり、ヨーロッパやアメリカに大量に輸出されるまでになったとのことです。
日本へは2~3世紀頃に中国から伝わり、奈良時代には栽培が始まっていたと考えられます。
ショウガの古名は「呉(くれ)のハジカミ」と言います。
「ハジカミ(波士加美、波自加彌)」は、歯で噛んで顔をしかめる、つまり刺激的という意味で、古来、山椒を「ハジカミ」と言っていたそうです。
ショウガが伝わると、山椒を「和のハジカミ」、ショウガを「呉のハジカミ」と呼び分けるようになったとのことです。
平安時代の「延喜式」には、その栽培方法や保存法が記されています。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
「ハジカミ」から「ショウガ」に変わったのは室町時代と言われ、「生姜」という漢字をあてるようになったのは江戸時代からとも言われています。
江戸時代には関東以西で広く栽培されるようになり、生産量が増えたことで庶民が気軽に親しめる貴重な食材となりました。
江戸初期の本草書「本朝食鑑」には、ショウガを梅干に漬けて日々愛用し、干したショウガを旅に持っていく、という記述があるそうです。
明治時代になると、「風邪の引き始めにはショウガ湯を飲む」という民間療法も広く知られるほど、ショウガはますます食材としての地位を確かなものにしました。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
昭和に入ると、戦争や経済不況により、ショウガはあまり重要視されなくなりましたが、戦後には再び需要が伸び始め、作付面積も収穫量も増えたそうです。
ショウガは栽培・収穫方法により、根ショウガ・葉ショウガ・矢ショウガに分けられます。
塊根部を食用とする根ショウガは、さらに、新ショウガ・ひねショウガ・親ショウガなどに分類されます。
それぞれの特徴などについて調べてみました。
【根ショウガ】
<新ショウガ>
ショウガの根の部分が育ったばかりの頃に収穫・出荷されたもので、6月~8月末頃にしか入手できない。
繊維質が柔らかく水分を豊富に含み、辛味や風味がマイルドなのが特徴。
生で食べるとみずみずしくシャキシャキとした食感と風味を楽しめる。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<ひねショウガ>
収穫後、一定期間貯蔵したあとに出荷された、茶色くて固い一般的なショウガ。
貯蔵性が高いため年間を通して流通し、料理の薬味や香辛料として幅広く活用されている。
繊維質が多く、風味や辛味も強いのが特徴。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<親ショウガ>
ショウガを栽培する際の種(種ショウガ)として使用したもの。
種ショウガを植えて収穫されると「親ショウガ」と呼ばれるようになります。
収穫時には、「新ショウガ(子ショウガ)」と「親ショウガ」が一緒に穫れますが、「親ショウガ」は植えたとき種ショウガの原型を保ったまま収穫されます。
「親ショウガ」は痩せ細ることはありませんが、子株に栄養を吸い取られているため、かなり固く辛味が強いのが特徴。
生食には向かず、煮物や煮付けなどの煮込み料理に使用すると繊維質が柔らかくなり、おいしく食べられる。
【葉ショウガ】
春から初夏の若いうちに、根茎が小指程度の大きさにまで成長した段階で、葉が付いたまま収穫されたショウガ。
味噌をつけて生食したり、魚の付け合わせ、甘酢漬けなどにしたりする。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【矢ショウガ】
はじかみショウガ、棒ショウガ、筆ショウガなどとも呼ばれる。
軟化栽培し15cm程度に成長したところで太陽に当て、茎元が紅色になった頃に収穫する。
甘酢漬けにして、はじかみとして焼き魚の彩りなどに使われる。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
現在、ショウガの主要産地は高知県で、全国生産量の約4割を担っています。
ほか、熊本県、千葉県、宮崎県、和歌山県、鹿児島県などで多く生産されています。
ちなみに香川県のショウガ生産量は、全国で40位程度(47都道府県中、2022年調べ)だそうです。
各地で生産されている品種について、いくつか調べてみました。
【谷中ショウガ】
葉ショウガとして初夏のみ市場に出荷される、東京の伝統野菜。
葉の根元が赤く色づく。
かつて東京都荒川区東日暮里・西日暮里の旧地名である谷中本村の特産品であった。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【金時ショウガ】
小ぶりで香りと辛味が強い、日本独自の品種。
辛味成分ジンゲロールの含有量が多いとされる。
愛知県、静岡県で主に生産されている。
【朝国ショウガ】
滋賀県湖南市の朝国地域で一大産地となっていた伝統野菜。
小ぶりで爽やかな辛味が特徴。
約220年の伝統を途絶えさせないように復刻プロジェクトが立ち上げられている。
【出西ショウガ】
島根県出雲市斐川町出西地区の限られたショウガ畑で栽培される品種。
繊維が少なく、風味や香りがよく、ピリっとした辛味が特徴。
【黄金ショウガ】
高知県の坂田信夫商店が発見した品種。
繊維質が少なく、長時間保持される濃い黄色と、強い辛味と清涼感のある爽やかな香りが特徴。

※写真はPhotoACより
<参考サイト>
・Wikipedia ショウガ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%82%AC
・ショウガ
https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1553
・生姜のルーツ
https://syouga.ken-shin.net/denrai.html
・ 生姜の歴史と生姜にまつわる行事 – 遠藤食品
https://www.endo-foods.co.jp/mamechisiki/shouga_rekishi-gyozi.htm
・生姜のはなし
https://syougatou-honpo.jp/story/
・しょうがの基礎知識|主な種類・栄養成分・長持ちする保存方法も解説
・生姜 総合ランキング
https://japancrops.com/crops/ginger/prefectures/
・ブランド生姜「黄金しょうが」を高知から全国へ!「坂田信夫商店」で働きませんか?
https://www.kochi-iju.jp/other/details.html?cid=456&type=
・金時生姜とは?
https://shougaya.com/ginger.html
・出西しょうが
https://www.kankou-shimane.com/destination/21214
・朝国しょうが復刻プロジェクト
② ショウガ特有の栄養成分で身体を温めて健康UP!
風邪のひき始めに用いられる「葛根湯」や「桂枝湯」など、多くの漢方薬に含まれる生薬でもあるショウガには、多くの栄養素が含まれています。
主要成分「ジンゲロール」は、生のショウガ特有の辛味成分で、末梢血管を拡張させ血流を良くする働きがあります。
ジンゲロールは、ショウガを加熱して水分を飛ばすと「ショウガオール」に変化し、身体を温める働きが高まります。
胃腸など身体の芯が温まることにより、免疫力向上にもつながります。
また、香り成分の「シネオール」には、リラックス作用があります。
その他、食物繊維やビタミンC、ビタミンB1、B2等を含んでいます。
ショウガを摂ることで冷え性の改善が期待できることはよく知られています。
血流が良くなることにより、血行不良による冷え性や肩こりなどを和らげます。
発汗、排尿、排便が促進され、不要なものが排出されやすくなります。
胃腸の内壁の血流を良くして、胃腸の働きを活発にし、食べ物の消化吸収を助けてくれるうえ、内臓の働きを活発にして食欲を増進する作用もあります。
また身体を温めることで、関節の痛みを和らげます。
ショウガには殺菌効果もあり、魚の臭みを消すだけでなく食中毒予防にも役立ちます。
また、二日酔いや吐き気を抑える働きもあります。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
炎症や痛みを抑える働きがあるため、抗炎症作用や鎮痛作用、せきやのどの痛みの緩和も期待できます。
さらに、コレステロール値や血圧の低下、抗酸化作用なども知られています。
ショウガはたくさん摂っても問題のない食材ですが、辛味が刺激になるため胃が弱い人は摂りすぎに注意が必要です。
1日20グラム、粉末なら2グラム程度がおすすめとのことで、効果の持続時間は3~4時間のため、こまめに摂取すると良いそうです。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<参考サイト>
・【医師監修】生姜の驚くべき健康効果とは?
https://www.aux-ltd.co.jp/magazine/health/ginger_power.html
・体を温めるには、生姜は「生」と「加熱」どっちがいいの?管理栄養士に聞いてみた!
https://www.orangepage.net/news-daily/23965
・しょうがに含まれる栄養と働き|しょうがを使ったレシピを紹介
https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/30623
③ 無病息災を願う!?ショウガの活用法いろいろ
ショウガは、薬用や料理に使われるほか、生姜湯、ジンジャーティー、チャイ等の飲み物に入れたり、乾燥粉末を生姜糖や生姜せんべいなどのお菓子に加えたり、生姜味噌や生姜醤油など、調味料に加えたりと、幅広く活用されています。
さらに、入浴剤としてお風呂や足湯に入れたり、枕元に置いてアロマ効果を楽しんだり、デスクにおいて集中力や記憶力を高めたりといった活用法もあります。
ショウガは風水において熱=赤=生命を意味しており、インドでお払いに使われたり、中国では魔除けに使われたりしてきたそうです。
毎年6月15日は「生姜の日」だそうです。
日本で唯一、香辛料の神様をまつる、石川県金沢市の「波自加彌神社」では、この日に「はじかみ大祭」、通称「しょうが祭り」を行います。
奈良時代に大干ばつが起こり雨乞いをしたところ6月15日に霊水がわき出し、これを祝う際の神饌とすべき食物が、乾燥に強いはじかみ(ショウガ)しか残されていなかったという言い伝えがその由来だそうです。
東京都あきるの市の二宮神社では、毎年9月8日、9日に行われる秋季例大祭が通称「生姜祭り」と呼ばれ、祭礼に神饌としてショウガを奉納します。
9日に立ち並ぶ露店で販売されるショウガを食べると、「風邪をひかない」「1年間無病息災、厄除けになる」と言われているそうです。
福島県岩城郡四倉町(現いわき市)の船渡八幡神社、東京都港区の芝大神宮、福岡県太宰府市の太宰府天満宮、鹿児島県清水町の多賀神社などでは、ショウガの収穫祝いとして「生姜市」が立つ祭礼があり、市でショウガを買ってきて魔除けにするところもあるそうです。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<参考サイト>
・生姜の食べる以外の活用方法は?
https://biminara.com/1043.html
・簡単に運気アップ?知られざるショウガの魔よけ効果
・二宮神社秋季例大祭(生姜祭り)
④ 定番からお菓子や飲み物まで!日本のショウガ料理
爽やかな香りと辛味を持つショウガは、薬味として、また隠し味や臭み消しとして、あらゆる料理に使われます。
一年を通して手頃な価格で手に入りますが、1970年代からチューブ入りのおろしショウガが販売されており、より手軽に使えるため、冷蔵庫に常備しているご家庭も多いかもしれませんね。
日本を代表するショウガ料理と言えば、定食の定番メニューでもある豚肉のショウガ焼きではないでしょうか。
厚めにスライスした豚肉を、醤油ベースにすりおろしショウガをたっぷり入れたタレに漬け込んで焼く、シンプルな料理です。
ご飯のおともにピッタリなのが、ショウガのつくだ煮です。
また、初夏に出回る新ショウガの甘酢漬けは、お酒のつまみや常備菜として活躍します。
お寿司屋さんでは「ガリ」と呼ばれ、口の中をさっぱりとさせ、魚の臭みを消したり殺菌したりする働きがあるとされます。
焼き魚に添えられることが多い細長いタイプのはじかみは、赤色の濃い部分は茎で硬く、白い部分のみを食べるのが一般的です。
全国で広く食されているショウガですが、地域の特色を反映した様々な郷土料理があります。いくつか調べてみました。
【しょうが味噌おでん】(青森県)
青森市周辺では、すりおろしたショウガ入りの味噌ダレでおでんを食べるのが一般的で、コンビニのおでんにもカラシではなくショウガ味噌をつけてくれるとのこと。
戦後の闇市の屋台で、真冬に北海道・函館へわたる青函連絡船に乗るお客さんの身体を少しでも温めようと、屋台のおかみさんが提供したのが由来と言われている。
【長岡生姜醤油ラーメン】(新潟県)
「新潟5大ラーメン」のひとつとされるご当地ラーメン。
豚骨や鶏ガラで出汁をとった醤油ベースのスープにショウガをたっぷり入れて仕上げる。
1960年代に長岡に出店した「青島食堂」が、寒い時期にも身体が温まるようにとショウガの量を増やして提供したのが始まりと言われている。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【生姜せんべい】(石川県)
安土桃山時代が発祥と言われる金沢の生姜せんべいは、ほどよく反った小舟の形状で、通称「柴舟」と呼ばれている。
砂糖の上品な甘さと、口当たりの良さ、あとを引くショウガの風味が特徴。
【しょうが飯】(和歌山県)
和歌山市の紀の川沿いに広がる柔らかい砂地地帯では、温暖な気候を生かし、大正初期からショウガの栽培が行われてきた、全国有数の新ショウガの産地。
新ショウガの旬である5月~10月に収穫・出荷されたものを使い、米と一緒に炊き上げ、ゴマや薬味のネギを添えて食べる。
【生姜糖】(島根県)
出雲市平田町の特産の出西ショウガの搾り汁に砂糖を混ぜ、炭火で煮詰めて固めた菓子で、ショウガならではのツンとする辛さと砂糖の甘さを楽しむことができる。
1715年、茶席にむく高尚な菓子を求めた來間屋文左衛門が完成させたと伝わる。
現在は1軒だけが手がけており、すべて手作業でつくっているとのこと。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【生姜漬け】(高知県)
国内生産量トップの高知県では、ショウガに塩を振って寝かせた後、天日干しにし、赤梅酢に漬けた紅ショウガのほか、甘酢漬けやはちみつ漬、梅酢漬、味噌漬けなど、様々な「生姜漬け」がある。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【冷やしあめ】(高知県)
米飴、上白糖、ショウガの搾り汁を釜焚きしてシロップ状にした蜜を、水で割った飲み物。
夏には爽やかな清涼感が暑さで疲れた身体を癒やし、冬にはこの蜜を湯で割った「あめ湯」が身体の芯を温めてくれるとのこと。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<参考サイト>
・生姜(ショウガ): 爽やかな香りと辛味 あらゆる料理にちょい役で出演
https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c15304/
・“映え” なくても確かな存在感 : ショウガのお料理コレクション
https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c153040/
・しょうが味噌おでん 青森県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/shouga_misooden_aomori.html
・「新潟5大ラーメン」を食す!【①長岡生姜醤油ラーメン 編】/長岡市
https://niigata-kankou.or.jp/blog/485
・新潟名物「長岡ラーメン」とは?特徴や歴史を紹介
https://tenposstar.com/ja/articles/r/1014
・生姜せんべい 石川県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/menu/syoga_senbei.html
・しょうが飯 和歌山県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/shouga_meshi_wakayama.html
・生姜糖 島根県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/menu/syoga_to.html
・生姜漬け 高知県
https://kyoudo-ryouri.com/food/2531.html
・生姜の味噌漬け 熊本県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/menu/shougano-misozuke.html
・冷やしあめ 高知県
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/traditional-foods/menu/hiyasiame.html
⑤ カレーからスイーツまで!世界のショウガ料理
ショウガを生で食べるのは日本独特の習慣だそうです。
韓国では加熱せずおろして多種類の香味野菜や香辛料とともに複合的な味をつくり出すために用い、中国では臭み消しや香りづけに用いて加熱する傾向があり、ヨーロッパでは乾燥品をスパイスとして使うのが一般的とのことです。
世界各国でショウガがどのように食されているか、いくつか調べてみました。
【姜葱牛肉】(中国)
生姜を効かせた牛肉炒め。
薄くスライスしたショウガを炒めて香りを出し、片栗粉をまぶして多めの油で揚げ焼きした牛肉、タマネギを合わせてオイスターソースと醤油で味付ける。
【青椒肉絲】(中国)
日本でもおなじみの定番料理。
細切りにした牛肉、タケノコ、ピーマンを炒め、細切り生姜とネギ、オイスターソースで香りづけし、醤油や酒などの合わせ調味料で仕上げる。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【フォー】(ベトナム)
グルメサイトが発表した 「世界の生姜を使用した100の美味しい料理」で、ベトナム料理が4品選出され、中でもフォーは2種類がそれぞれランクインしているとのこと。
牛骨を煮込んだスープに、米の麺とタマネギ、ネギ、肉団子、ライムなどが具材として入る。
ショウガを加えることで香ばしさと辛味をプラスし、全体の味わいを引き立てる。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【チェー・チョイ・ヌォック】(ベトナム)
ベトナムの伝統行事や祭礼に欠かせないデザート。
もち米の団子に緑豆の餡を詰め、ココナッツミルクや黒糖シロップをかけ、仕上げにショウガを加えることで、甘さと辛味が絶妙に調和する。
【ゆで鶏】(ベトナム)
鶏肉を、塩、ショウガ、ネギ、ターメリックなどと茹でる料理。
ショウガが鶏肉の自然な風味を引き立て、バランスの取れた味わいに仕上げる。
【黒鶏の鍋】(ベトナム)
ベトナム北部サパ地方の伝統料理。
肉質がしっかりして独特の風味のある黒鶏と、シイタケ、カボチャ、サツマイモなどを入れた、滋味深いスープが特徴。
【カレー】(インド)
インドはショウガの生産量・消費量ともに世界1位。ショウガとニンニクは、ペーストにして「ジンジャー・ガーリック・ペースト」として炒めることで、カレーに豊かなうま味と香りを加えるのに欠かせない。
食感が残るよう、カレーの仕上げにショウガを加えることもある。
【アチャール】(インド)
アチャールはインドの漬物のことで、カレーの付け合わせによくつくられる。
スライスしたショウガに、レモン汁、油、塩、カレー粉を混ぜ合わせて漬け込む。
【ジンジャーチャイ】(インド)
マサラ(数種類のスパイスを混ぜ合わせたもの)と一緒にショウガを入れたチャイ。
スパイスなしでショウガだけの場合もある。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
【ジンジャービール】(イギリス)
イギリスではショウガは主にお菓子や甘い飲み物に使われる。
ジンジャービールは、イギリスで古くから親しまれてきた微炭酸の飲み物。
ショウガ、砂糖、イースト菌、水を主な材料とし、発酵させてつくる。
アルコールをほとんど含まず、ジンジャーエールと比べるとショウガの風味が強い。
【ジンジャーエール】(イギリス)
19世紀、発酵ではなく炭酸ガスを用いて炭酸をつくり出す技術が進歩し、ジンジャービ―ルから派生したノンアルコールの「ジンジャーエール」が誕生した。
そのシンプルさとスパイシーさから、カクテルのベースとして、また健康志向の飲み物として世界中で愛されている。
【クリスマスプディング】(イギリス)
クリスマスに食べるイギリスの伝統的なデザート。
ドライフルーツとパン粉、ショウガなどの数種類のスパイスを混ぜ合わせて型に入れ、蒸し焼きにしてつくる。
【ジンジャーブレッド】(イギリス)
欧米でよく食べられているショウガを使ったお菓子の代表格。
しっとりとしたパンやケーキ、クッキーやビスケットなど、いろいろなものがある。
クリスマスの飾りとしても使われる、人の形をしたクッキー「ジンジャーブレッドマン」もそのひとつ。
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
<参考サイト>
・料理書にみる中国,朝鮮,日本料理中のショウガ利用比較
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1995/36/3/36_255/_article/-char/ja/
・姜葱牛肉 牛肉のジンジャー炒め
https://www.japanjournals.com/company/232-eat/hitorimeshi/19643-beef-with-ginger.html
・きょうの料理レシピ チンジャオロースー
・世界の美味しい生姜料理100選、ベトナム料理4品が選出
https://poste-vn.com/news/2024-09-20-18210
・北インド料理のニンニクと生姜について
https://note.com/llittle_press/n/ncdeb30280247
・世界のショウガ生産量ランキング2023(最新)
https://world-guide.jp/ranking/products/596
・ 香辛料を使った生姜のアチャール
https://www.onakanohanashi.com/patient/1385.html
・インド・ネパール料理におけるニンニク・しょうが・玉ねぎ
・生姜と甘味のコンチェルト! 大英帝国の歴史に刻まれたベストハーモニー
https://www.kanro.co.jp/sweeten/detail/id=2021
⑥ ショウガを練り込んだ素麺や、素麺以外の麺あれこれ
ショウガを麺に練り込んだものを調べてみたら、素麺や生麺、インスタントラーメンなど、様々な麺がつくられていましたので、いくつかご紹介します。
【しょうが麺】(はしづめ製麺)
職人が手間ひまかけてカットした国産の黄金ショウガを使用。
生のものと低温乾燥・粉砕したものをブレンドして生地に練り込んでいる。
寒い季節の温かい料理に使われている。
・しょうが麺20-130[秋冬限定]
https://hashizumen.co.jp/noodles/ginger/
【手延べ生姜めん】(三輪山本)
生姜を練り込んだ手延べ素麺。
ゆで汁にショウガの味がつき、丸ごと食べられる。
・手延べ 生姜めん
https://store.mahorobashop.jp/products/mhr00235
【しょうがめん】(肥後そう川)
熊本県産の小麦粉に、粉末にした熊本県産のショウガを練り込み、健康的な麺に仕上げている。
寒い冬も身体の芯からポカポカ温まる。
つゆ付きも販売されている。
・しょうがめん(つゆ付き/2食入)
https://www.sougawa.com/item/kjt/
【新生姜生そうめん】(岩下食品)
栃木県栃木市にある「岩下の新生姜ミュージアム」にて販売されている。
栃木市の製麺所「中沢製麺」と共同開発したオリジナルの“生そうめん”。
「岩下の新生姜パウダー」を練り込み、ピンク色でほんのりショウガ風味。
なめらかな舌触りとのどごしの良さ、モチモチとした食べ応えが特徴。
・岩下の新生姜生そうめん 2食入
https://shinshoga-museum.com/news/190716_shinshoga-somen
【濃くてうまい MISO】(日清食品)
ショウガを麺に練り込んだ“旨み練り込み麺”を採用し、麺一本一本にまでしっかりとした味わいを感じられるインスタントラーメン。
スープにも、赤味噌と白味噌をブレンドした濃厚な味噌スープにジンジャーチップを加えている。
2020年、全国のセブン&アイグループ各社で限定販売された。
・“旨み練り込み麺”が味の決め手!『日清 濃くてうまい』2アイテム
https://www.7andi.com/company/news/release/20200618.html
 ※写真はPhotoACより
※写真はPhotoACより
⑦ 《番外編》小豆島まつり
我が故郷の夏のお祭り「小豆島まつり」が8月15日(金)に開催されました。
開催場所は、石井製麺所から道を挟んだ向かい側のグラウンド。
たくさんの屋台が出て、お祭り好きな方々が島中から集まって来られます。
打ち上げ花火もあってとっても賑やかなお祭りです。



小豆島の中には2つの行政区があって、もうひとつの町、土庄町でも「小豆島まつり」が開催され、こちらも打ち上げ花火が上がります。
8月に入ると打ち上げ花火を伴う2つのお祭りがあり、島の方はあちらこちらへとお出かけするそうで、小豆島ならではの贅沢な感じではないでしょうか。
「小豆島まつり」の打ち上げ花火は、少し沖合の台船から打ち上げられますが、至近距離からの打ち上げなので、遠くに上がる花火を眺めるのでなく、真上に上がる感覚で、ほとんど下から見上げるような打ち上げ花火は“大迫力”の一言!
まるで火の粉が空から降り注ぐような迫力を味わえるのがこのお祭りの醍醐味だと思います。
なかなか都会では味わえない打ち上げ花火です。



ぜひ来年の夏は、小豆島で大迫力の打ち上げ花火をご覧に来られませんか。
石井製麺所の真横ですので、その際には製麺所へもぜひぜひお立ち寄りください。
《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。