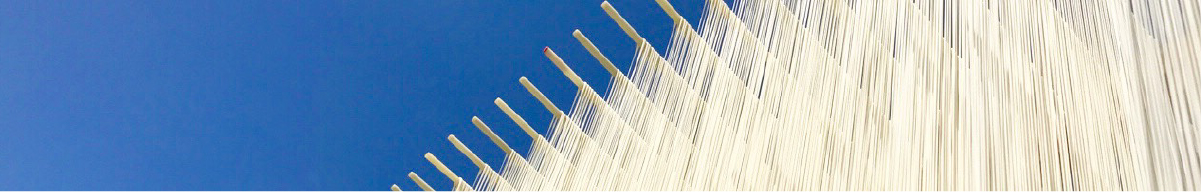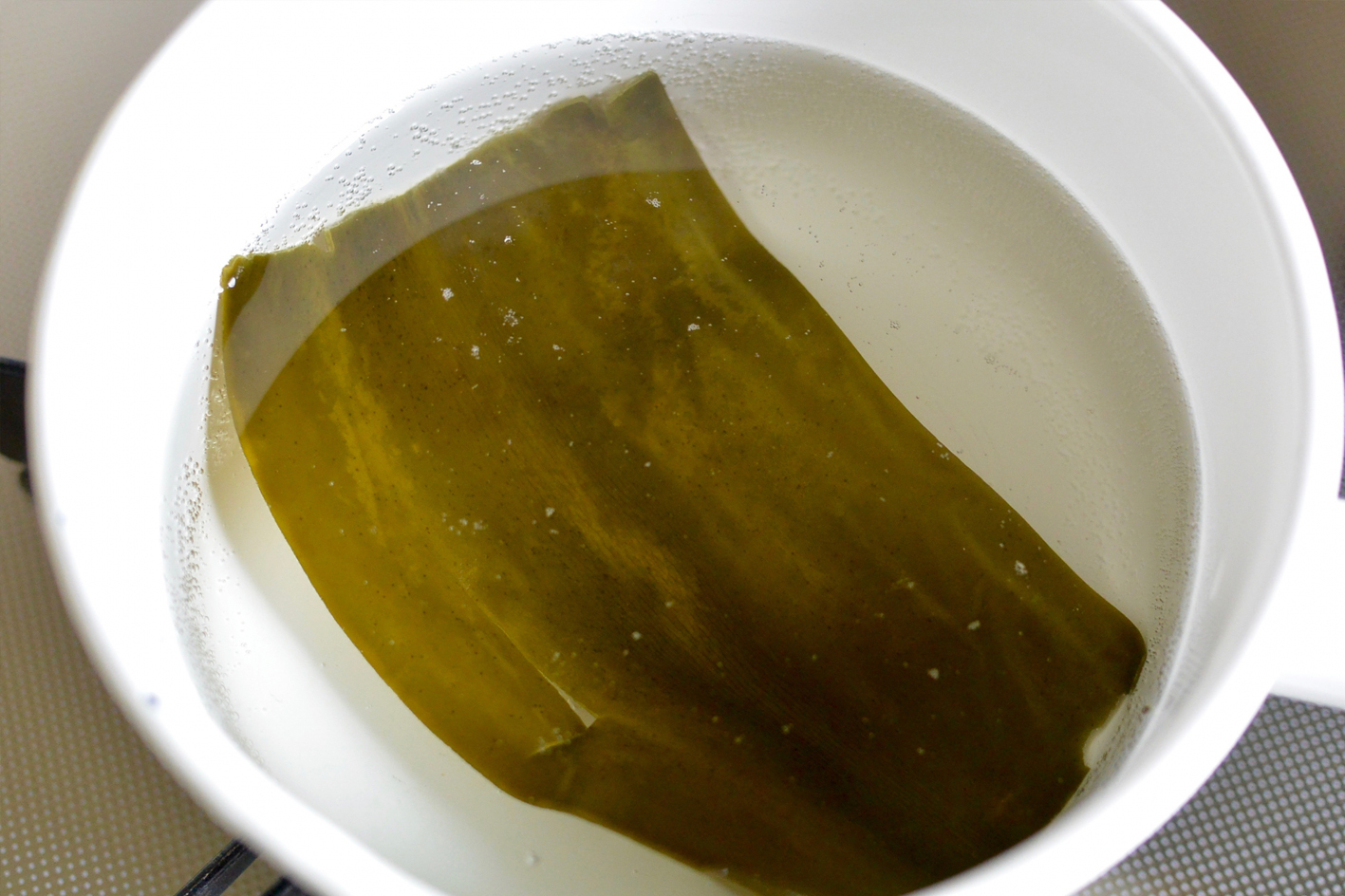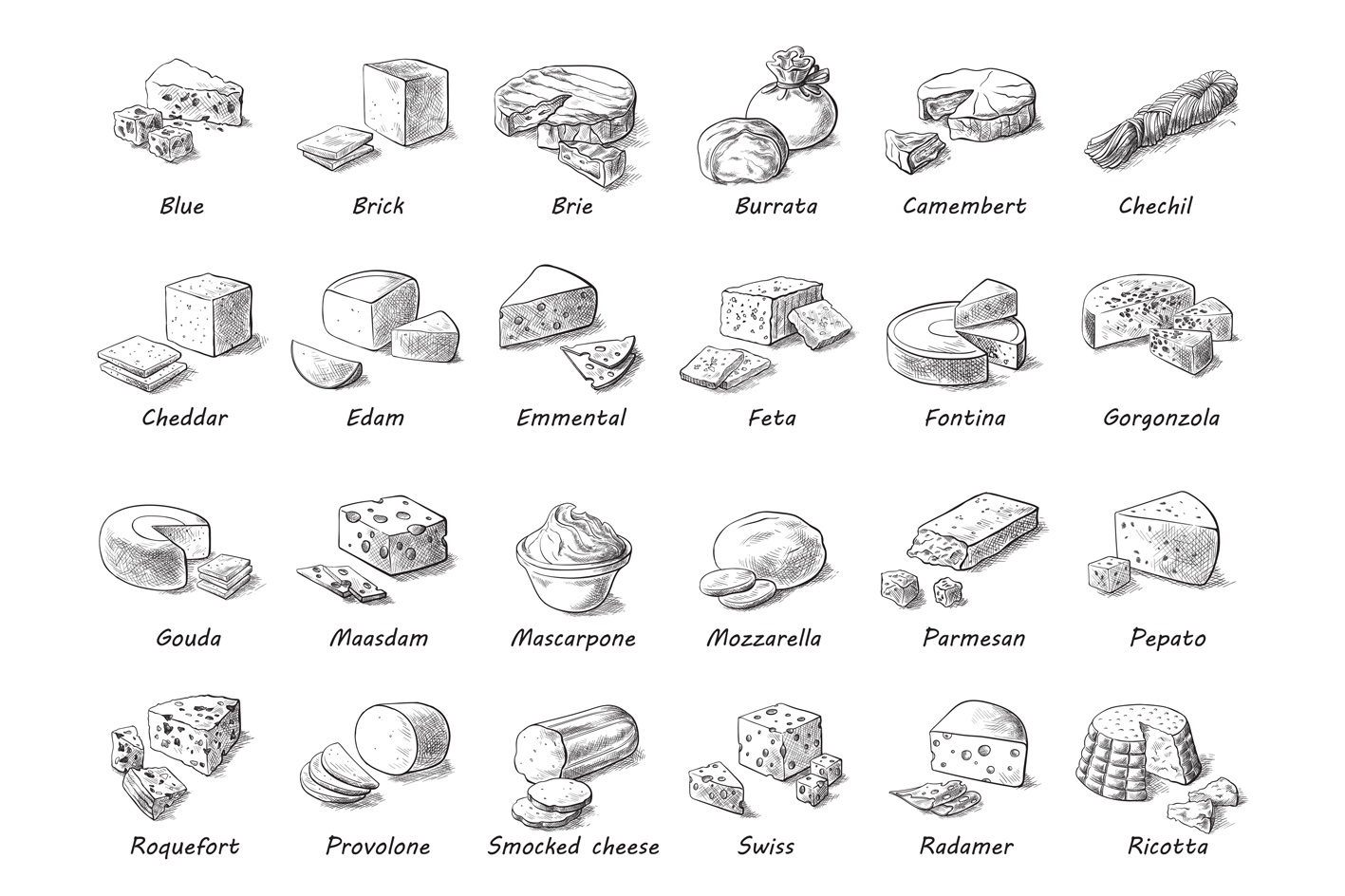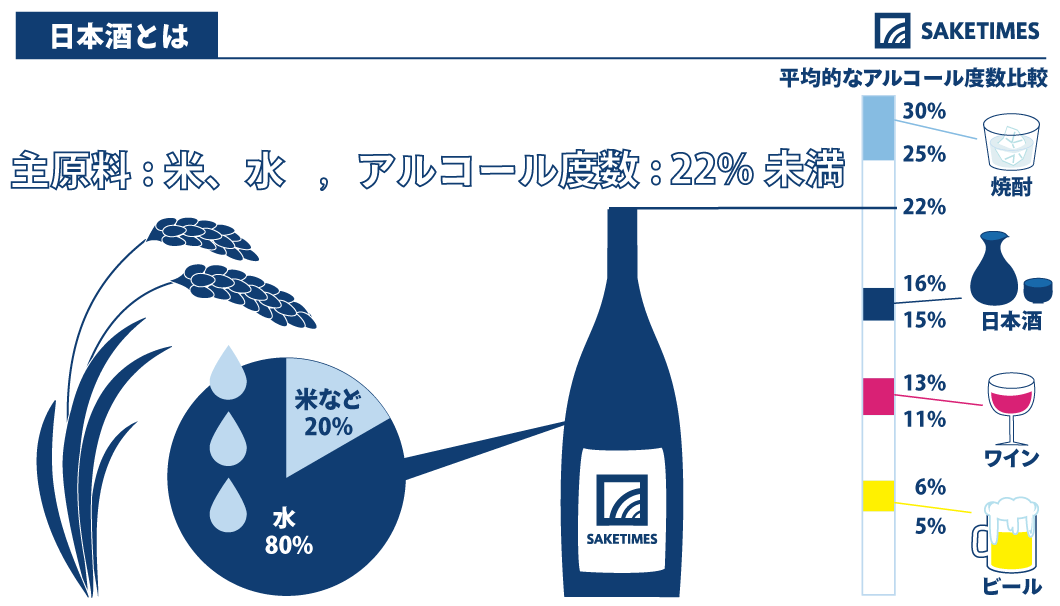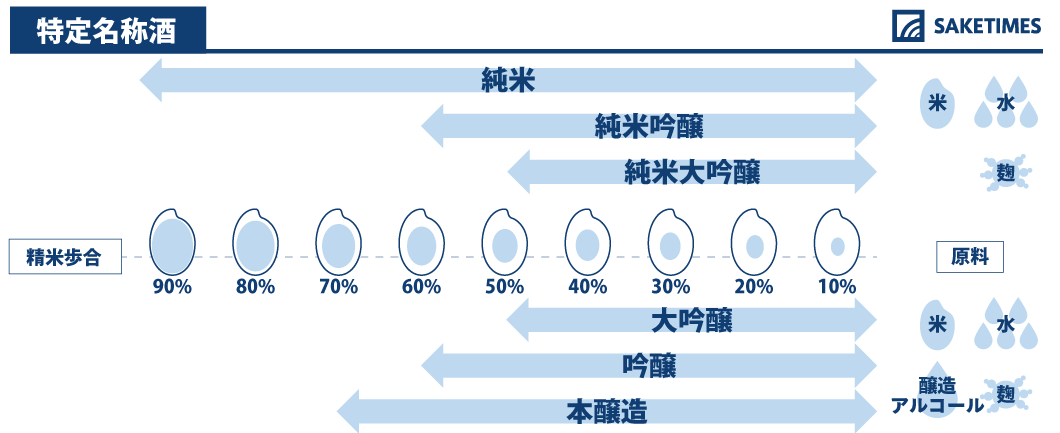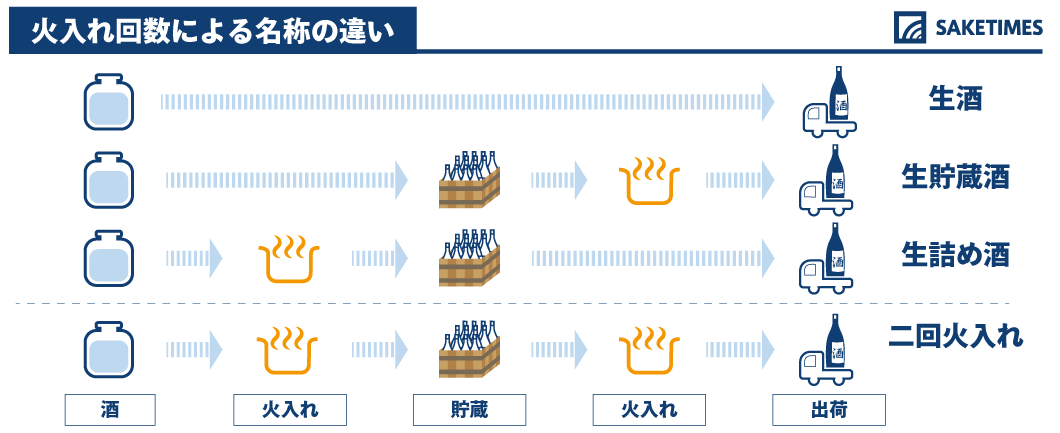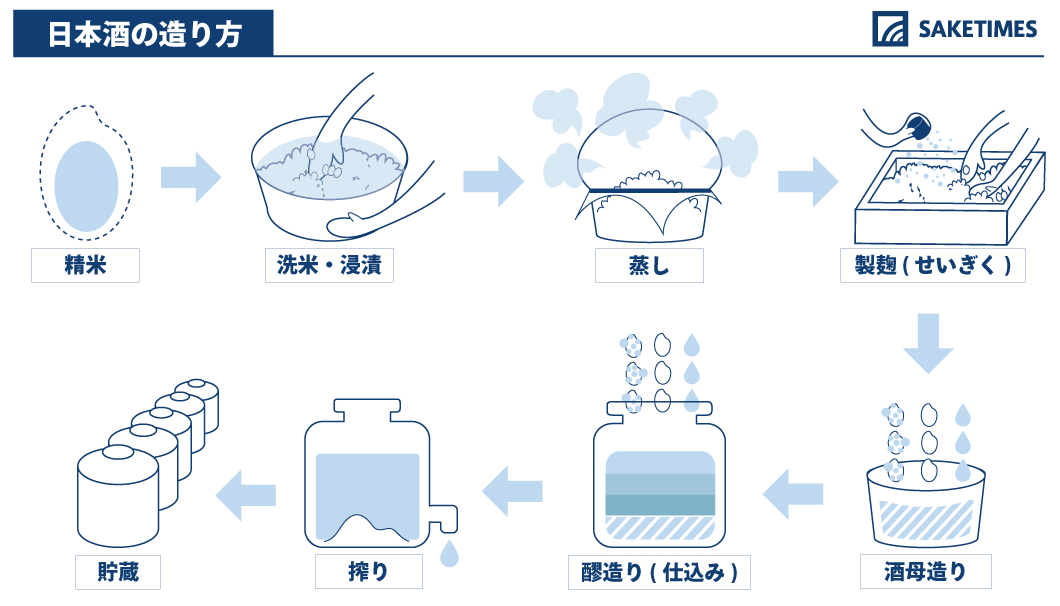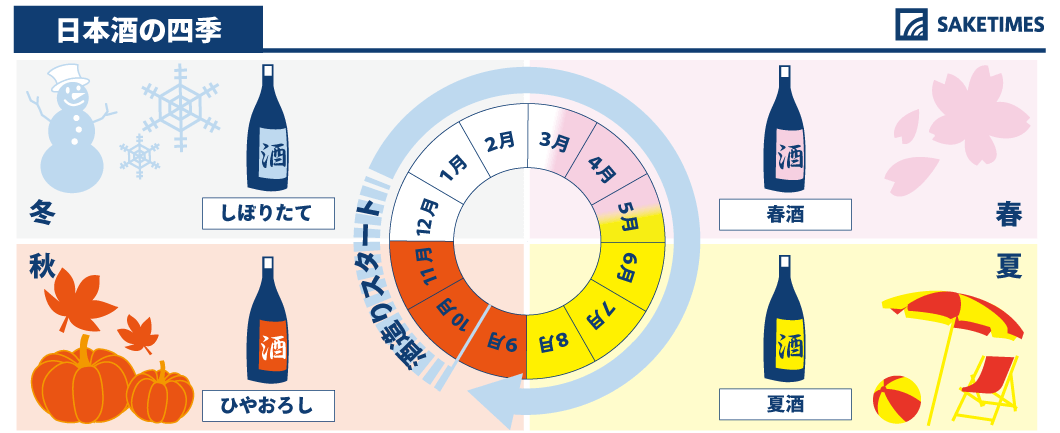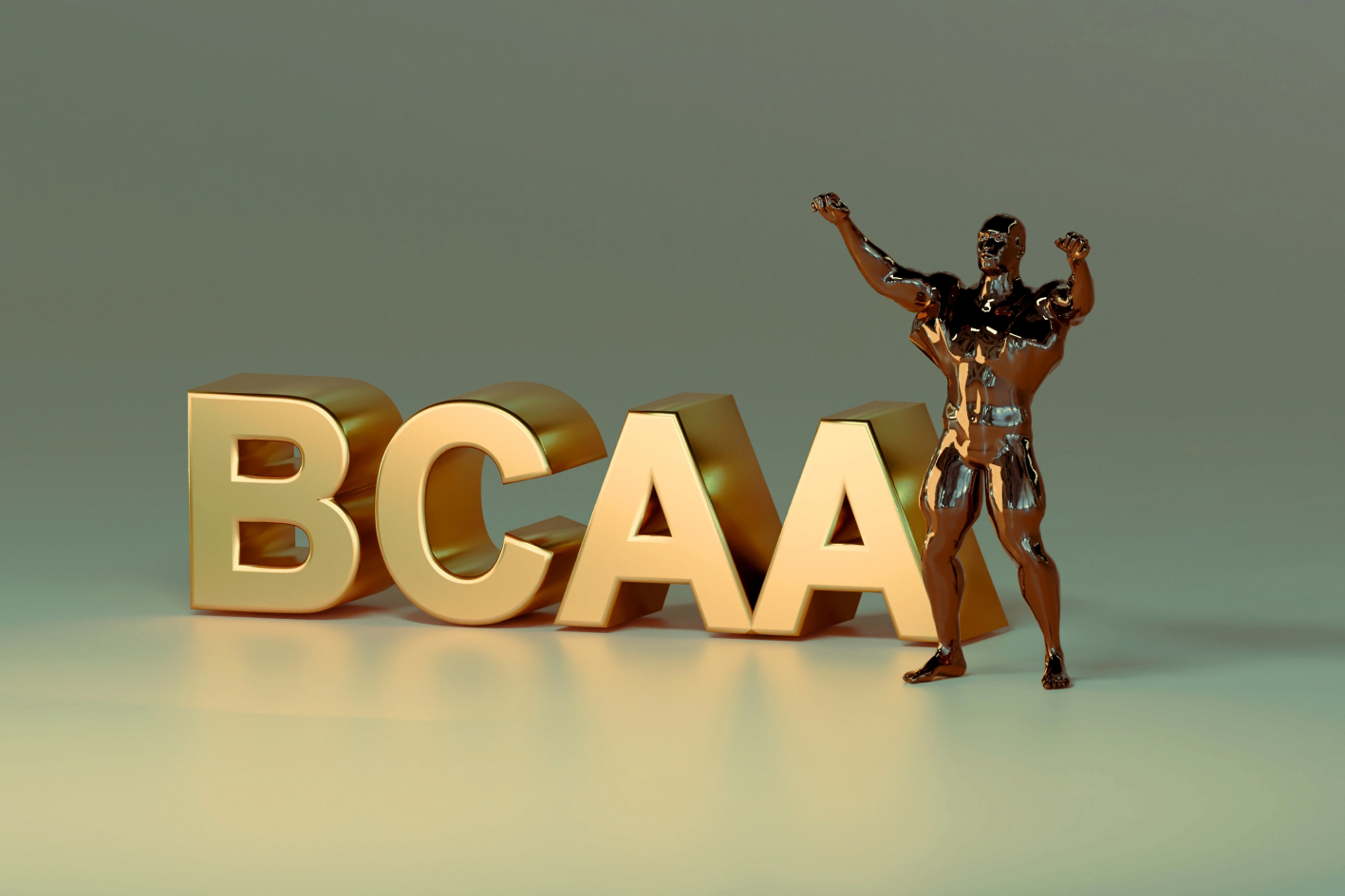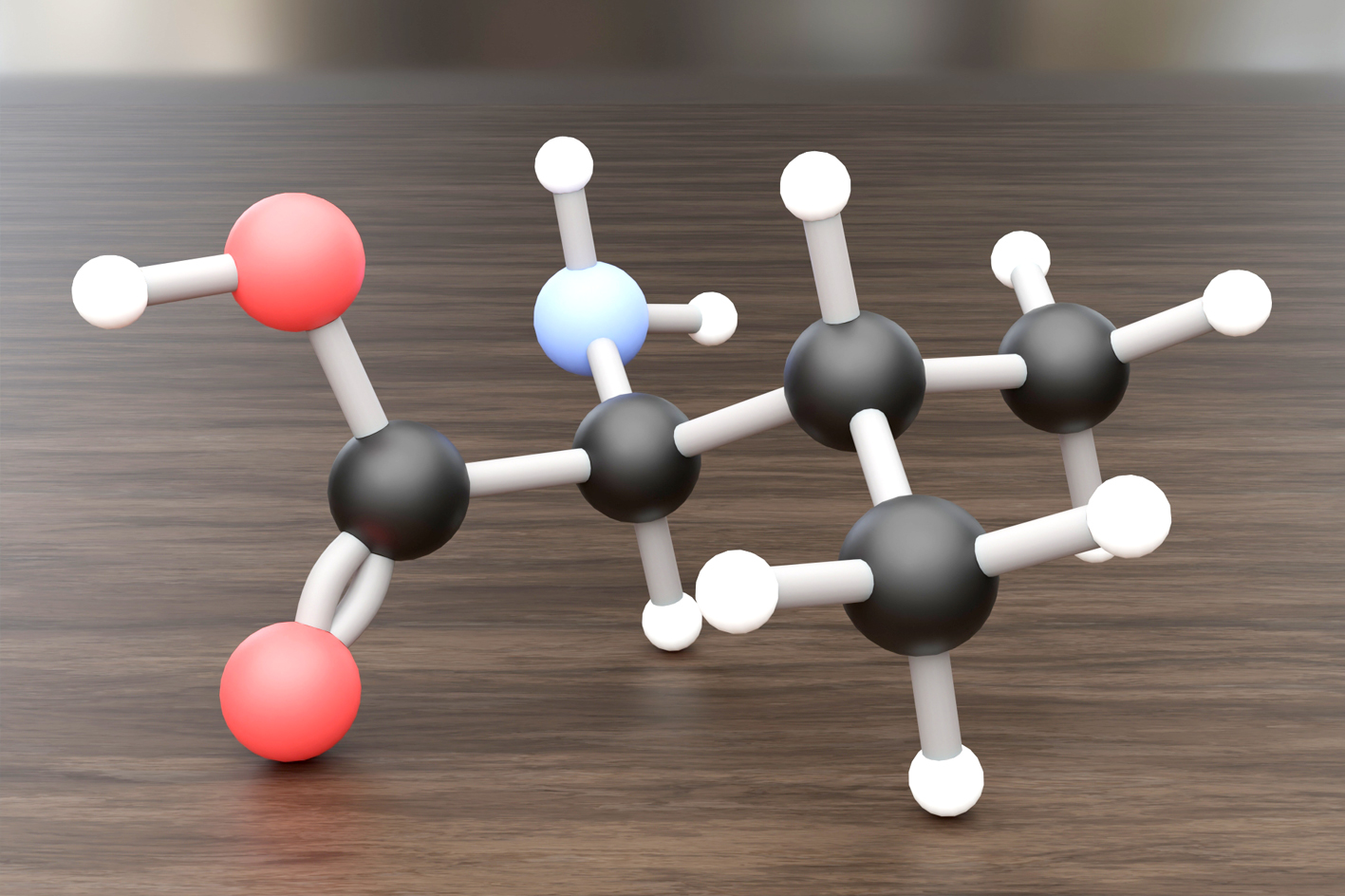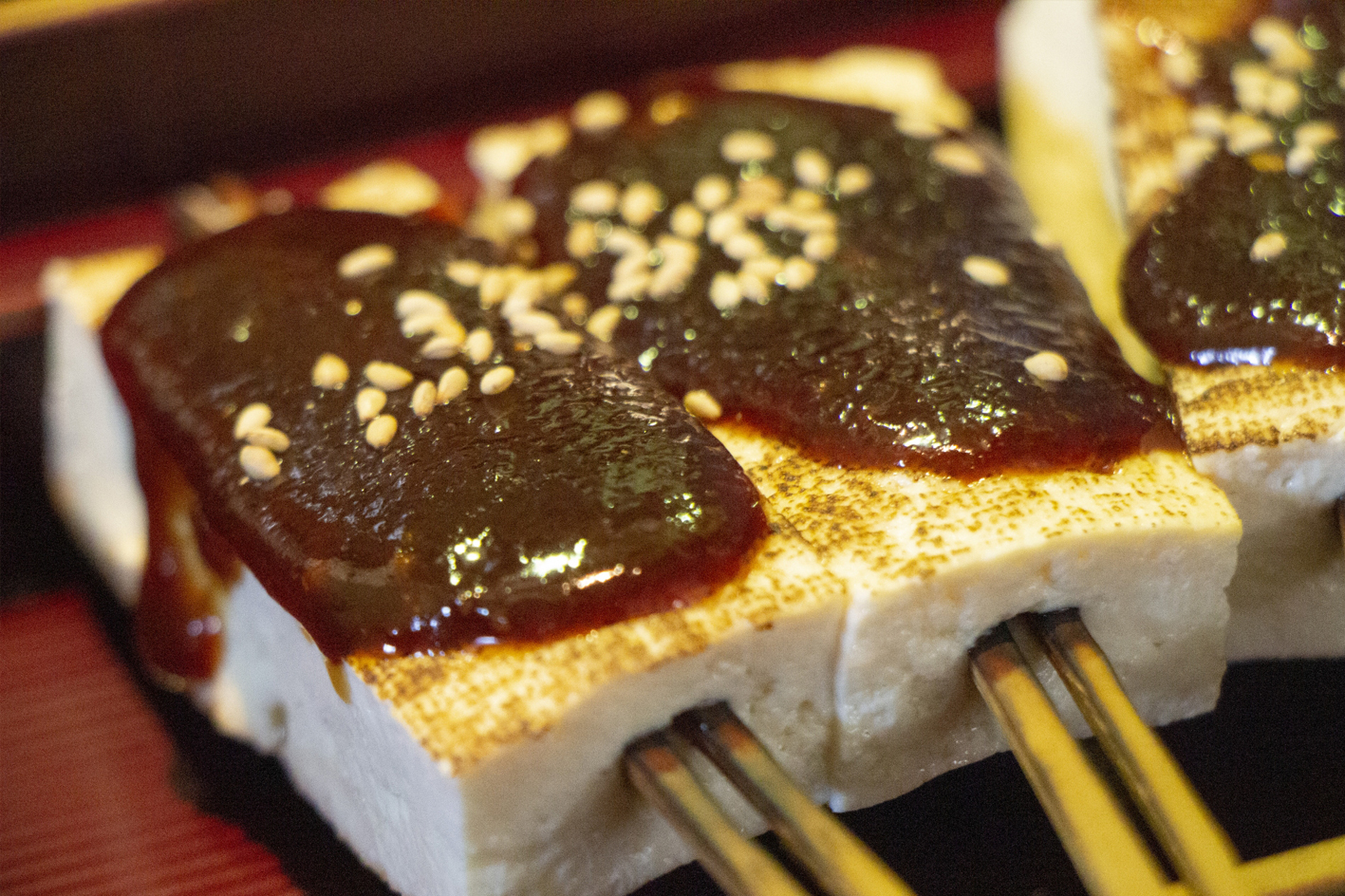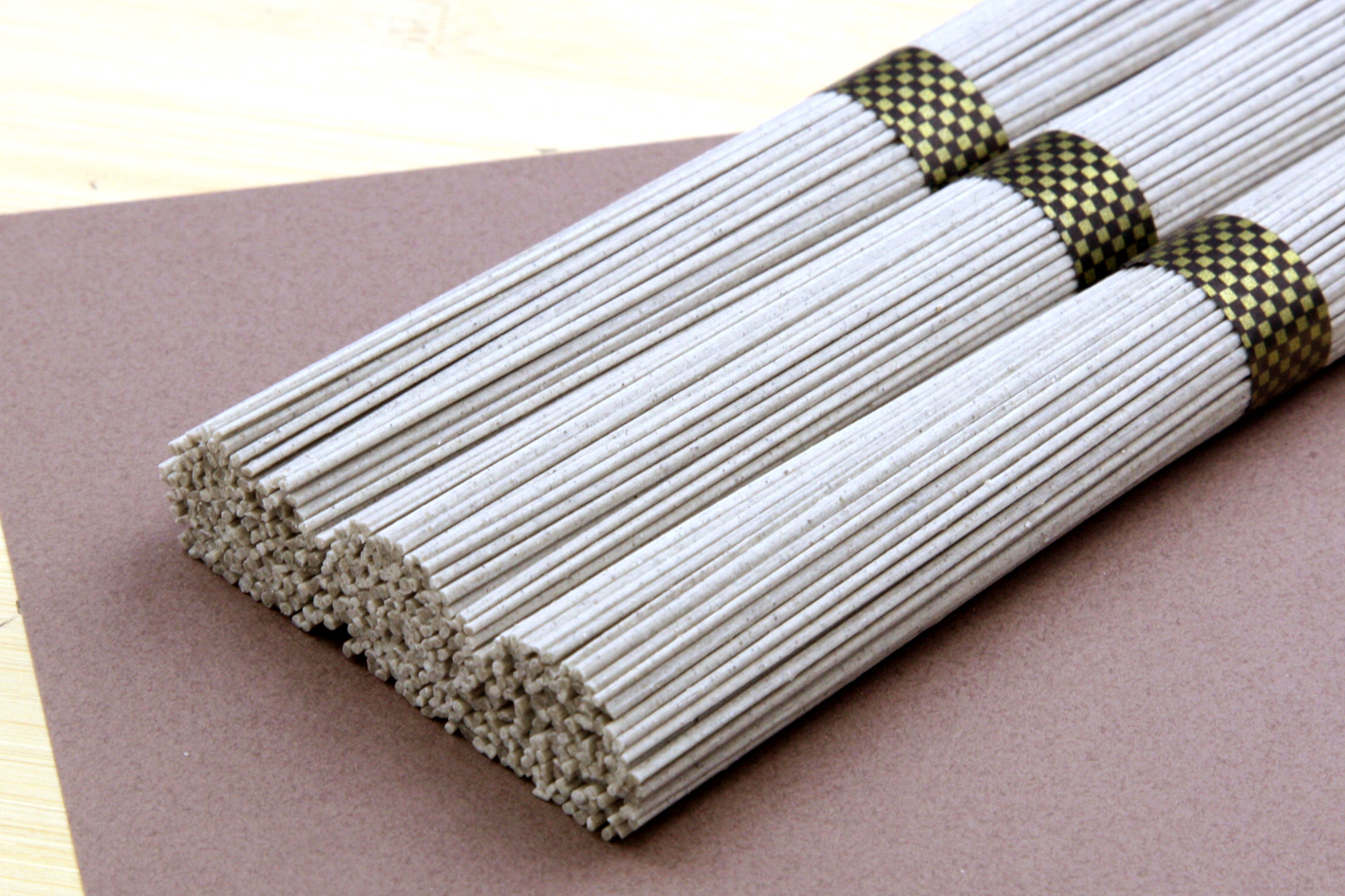【お!いしい けんぶんろく】 Vol.42
麺究者への道/ビールについて研究してみる
夏の終わりが近づくにつれ、台風の接近や不安定な天候に悩まされます。
そして、この夏一番の悩みと言えば…
今年は、本当にたくさんのご注文を頂戴しました。
暑さが厳しかったことや、暑い日が続いたせいか、今年は8月中旬頃までご注文を多くいただき、製造と発送を交互におこなう日々でした。
その出荷のピークも過ぎた8月中旬頃、なんとか今年も乗り切れたと安堵し、今後の製造に向けて設備の見直しや製造環境の改善など、検討し始めた矢先、なんと、肝心要の乾燥用のボイラーが故障…
製造のピークを見計らったように、まったく言うことを聞いてくれなくなったボイラー。
手延べ麺を乾燥させるのになくてはならない存在です。
年々暑さが厳しくなり、また不安定な天候が続くことから、製造環境の改善に経費がどれくらい掛かるかと考え、「ボイラーはもう少し頑張ってくれるかな?」と思ったのが悪かったのかどうか、一番はじめに根を上げてしまいました。
さあ、困りました。
知り合いの方にお聴きしたり、さらにそのお知り合いの方に修理ができる方をご紹介いただいたり…
色々なツテを頼って、見ていただいたところ、どうやら故障ということでなく、ボイラーの煙を排出する煙突(正確には煙道(えんどう))が詰まってしまっていて、そのせいでボイラーが不完全燃焼していたようです。
原因が分かれば、まずは煙突掃除です。
なんといっても、少なくとも30年選手のボイラーですので、型が古く、メンテナンス用の開口部は設けられていません。ボイラーと煙突の接続部のボルトを一本一本外し、煙突を取り外すところから…
硫黄と煤の塊をなんとか除去。
何とか作動するところまでは回復していただきました!
業者さんと一緒に、みんな煤で真っ黒になりながら頑張ったのは、ある意味いい経験となりました(笑)。
一安心ではありますが、内部の部品には劣化も見られるようで、新しいボイラーへの入替は避けられないようです。設備の見直しを図らなければいけない、今日この頃です。
これが目下、一番の悩みの種です。。。
さて、先日のブログでご紹介したマンガ「もやしもん」でも、ビールについてのお話があります。
とっても良いお話で、思わずビールを飲みたくなりました(笑)。
小豆島にもクラフトビールの醸造所があり、こちらはとても近くなのですが、車社会の小豆島。
車で行ったら飲めなくなってしまいますので、見学に伺い、お土産を買って今回のブログで調べたうんちくを読み返しながら自宅で味わってみたいと思います。
言われてみればビールも発酵食品のひとつなんですね。
(大)麦を発酵熟成させてつくるのですから素麺づくりに活かせる部分は無いかと色々と調べてみました。
今回も楽しい内容になったと思いますので、最後までご覧いただけると幸いです。

【目次】
① ピラミッド建設の報酬だった!ビールの歴史
② 鎖国中にもたらされ、冷蔵庫の普及により消費が増えた日本のビール
③ ビールの味わいや香りを決める、原料について
④ つくり方により個性を生み出す!ビールの製法
⑤ ビールの種類は世界に100以上!日本のビールの定義とは?
⑥ 《美味しい手延べ素麵》ビールのおつまみにふし麺のおやつ 編
① ピラミッド建設の報酬だった!ビールの歴史
ビールは麦芽・ホップ・水を主原料とした醸造酒で、アルコール度数が低く、炭酸ガスを含み、ホップ独特の香りや苦味を持つのが特徴です。
ビールの誕生は紀元前8000~4000年までさかのぼるとも言われています。
人類最初の文明とされるメソポタミアで、放置してあった麦の粥に酵母が入り込んで自然発酵したのが起源と考えられています。
紀元前3000年頃のシュメール人が、ビールづくりの模様をくさび形文字で粘土板に残しています。
当時は、まず麦を乾燥させて粉にしたものを焼いてパンをつくり、それを砕いて水を加え自然発酵させていたようです。
同じ頃エジプトでも、肥沃なナイル河畔で収穫される大麦を原料にビールがつくられ、広く飲用されていたとのことです。
ピラミッドを建造する労働者にビールが配られていたとも言われています。
当時のビールはホップは使用されず、薬草やはちみつなど様々な原料が使われていました。
栄養食品としてや、神様へのお供え物としても用いられていたそうです。

紀元前1700年代に制定された初めての成文法「ハムラビ法典」にも、ビールに関する法律が制定されているそうです。
この頃には各所に醸造所がつくられ、ビアホールのような店もあったようで、その取り締まり規則や罰則などが公布されました。
ギリシャやローマでは、麦類が生育しにくい気候風土のためか、ワインが主流となっていました。
北ヨーロッパでは、古代ゲルマン人が定住生活に入った紀元前1800年頃すでにビールがつくられていた記録が残っているそうです。
ゲルマン人やケルト人は、麦類を麦芽に加工する、現代にも通じる製法でビールをつくっていたようです。
ビールづくりにホップが使われるようになった時期については諸説ありますが、紀元前1000年頃、コーカサスに住んでいた民族から始まったという説が有力とのことです。
中世に入ると、ゲルマン民族の大移動によりヨーロッパ各地にビールが広がりました。
「ビールは液体のパン」「パンはキリストの肉」と考えられ、教会や修道院でビールづくりがさかんになりました。
当時のビールは、栄養補給や医療にも利用されていたようです。
11世紀後半になると、ビールづくりにホップを使用すると品質が飛躍的に向上すると分かってきて、ホップのビールが次第に広まりました。
技術の進歩もあり、一般庶民にも飲まれるようになって、15世紀以降には民間でもつくられるようになりました。
中世まではビールが腐敗しないように、9月~3月ごろの涼しい時期にビールづくりがおこなわれていました。
しかし気温が低すぎると発酵がうまく進まないなどのトラブルもあったそうです。
15世紀にドイツのミュンヘンで、下面発酵のビールが誕生します。
当時のビールは、高温で短時間、貯蔵と発酵を行う上面発酵のビールが主流でした。
低温で長時間、貯蔵と発酵を行う下面発酵ビールはその後のビールづくりを大きく変え、現在も世界の主流となっています。
1516年ドイツで「ビール純粋令」が交付されました。
「大麦・ホップ・水の3つの原料以外は使用してはならない」と定めることにより、その後ドイツビールの品質維持向上に貢献しました。
現在でもドイツでは下面発酵ビールの製造においてこの法律が守られています。
19世紀後半、ドイツのリンデが冷却機を発明し、下面発酵ビールが四季を通してつくれるようになりました。
またフランスの細菌学者パスツールが発明した低温加熱殺菌法により、ビールの長期保存が可能になって市場が拡大しました。
一方、デンマークのハンゼンが発見した酵母の純粋培養法により、ビールづくりに適した酵母だけを分離できるようになり、近代的な大量生産への道が開かれたとされています。

<参考サイト>
・ビールの豆知識|ビールの歴史
https://www.brewers.or.jp/tips/histry.html
・ビールの歴史をわかりやすく解説|ビールの発祥から現在までを説明
https://www.sakesen.com/blog/history-of-beer/
・ビールの歴史を教えてください。
https://www.suntory.co.jp/customer/faq/001716.html
② 鎖国中にもたらされ、冷蔵庫の普及により消費が増えた日本のビール
日本にビールが入ってきたのは江戸時代です。
鎖国政策のもと、唯一開港していた長崎県の出島でオランダからビールがもたらされ、蘭学者たちが試飲や試作をしたと言われています。
日本で初めてビールを醸造したのは幕末の蘭学者・川本幸民で、物理・化学分野の翻訳もしていた中で、ビールの醸造実験にも取り組んだとされています。
日本にビール醸造所が初めて設立されたのは1869年、横浜の外国人居留地で開設された「ジャパン・ヨコハマ・ブルワリー」です。
1870年にはアメリカ人の醸造師ウィリアム・コープランドが、現在のキリンビールの前身となる「スプリング・バレー・ブルワリー」を創設しました。
1872年、大阪で渋谷庄三郎が日本人では初めてビールの醸造・販売を本格的に開始したのを皮切りに、各地にビール会社が誕生します。
北海道に設置された開拓使により1876年「開拓使麦酒醸造所」が開業され、開拓使の廃止後に設立された「札幌麦酒会社」が、現在のサッポロビールです。
1889年に設立された「大阪麦酒会社」は、後にアサヒビールとなっています。
明治20年代に入ると近代化が進み、日本のビール総生産量が輸入量を超え、ビール産業は著しく成長していきました。
1899年、ビアホールが銀座にオープンしました。
当時ビールを提供するレストランは高級店であったため、ビールだけを気軽に飲める業態として発案されたビアホールは庶民に大人気となり、一時期の東京には約2,000軒のビアホールがあったそうです。
1950年代後半~1970年代にかけての高度経済成長期には、ビールの消費量が爆発的に増えました。
ビールはお店で飲むのが主流でしたが、家庭用冷蔵庫の普及により自宅での消費が急増したためです。
昭和40年代には全国で10のビール工場が新設され、製造量は10年間で2倍に増えました。
しかし1994年に過去最高の製造量を記録したのをピークに、飲酒人口の減少や消費者の嗜好の多様化・個性化により、ビールの製造量は減少傾向が続いています。
一方、1994年にビール製造免許に係る最低製造数量基準が年間2,000キロリットルから60キロリットルに引き下げられたことにより、各地に小規模なビール醸造所が登場し、独自のビールをつくり始めました。
1990年代後半には「地ビール」ブームが巻き起こりましたが、価格が高いこともあり、ブームは数年で衰退してしまいます。
そんな中、2000年代にアメリカで「クラフトビール」が人気を集めるようになるのに伴い、日本の小さな醸造所でつくられた地ビールも「クラフトビール」と呼ばれ、注目されるようになりました。
大手メーカーのビールとは異なる個性的で多様な味わいが好まれ、さらなる広がりを見せています。

<参考サイト>
・つい話したくなるビールの歴史と豆知識。ビールは常にイノベーションとともにあった
https://nf-startup.jp/report/details/3067/
・日本のビールの歴史と国内の大手ビールメーカーを知ろう!
https://tanoshiiosake.jp/9219
・クラフトビールと地ビールの違いとは?歴史や人気の理由も解説!
https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/jibeer/
・意外と知らなかった!「地ビール」と「クラフトビール」の違いとは
https://www.fujizakura-beer.jp/craft-beer-difference/
③ ビールの味わいや香りを決める、原料について
ビールの主な原料は、麦芽・ホップ・水、そして酵母です。
その組み合わせや量、使うタイミングや温度などにより、味わいや香りが変わります。
ビールの原料について、詳しく調べてみました。
【麦芽】
発芽した大麦の芽と根を取り乾燥させ、さらに熱風に当てながら焙燥(ばいそう)したもので、「モルト」とも呼ばれます。
大麦には、穀粒の実り方が二列の「二条大麦」と、六列の「六条大麦」があります。
ビールづくりに使われるのは、粒が大きく均一で、アルコールの原料となるデンプンの含有量が多い二条大麦で、別名ビール大麦とも呼ばれます。
小麦やライ麦、オーツ麦が使われるビールもあるそうです。
麦を発芽させることで、種子中の糖化酵素(アミラーゼ)が活性化し、麦芽に含まれるデンプンを糖に変えます。
その糖分を酵母が食べる、つまり発酵することにより、アルコールと炭酸ガスができるのです。

【ホップ】
多年生のつる性の植物で、松ぼっくりに似た花のような形をしためしべの「毬花(まりはな)」という部分が使われます。
ビールに苦味と香りを付けたり、泡のもちを良くしたり、腐敗を防いだりする役割を果たします。
北半球の涼しい地域で多く栽培され、8~9月頃に収穫されます。
香りの良い「アロマホップ」と、苦み成分の多い「ビターホップ」の2種類があります。

【水】
ビールの約90%を占める原料である水は、地域ごとに成分が異なり、その地でのビールの味わいに大きな影響を与えます。
日本で多く飲まれている淡色のビールには、カルシウムやマグネシウムなどの含有量が比較的少ない軟水が適しています。
硬水は、発酵も旺盛になりやすいことや、麦芽から多くの成分を溶け出させることなどから、濃色のビールづくりに向いているそうです。
【酵母】
ビールのもとである麦汁を発酵させてビールにする微生物。
麦汁に含まれる糖分をアルコールと炭酸ガスに分解する役割を持ち、発酵の副産物としてエステルという香り成分を生み出します。
ビールづくりに用いられるビール酵母は、上面発酵酵母と下面発酵酵母の2系統に分けられます。
上面発酵酵母は20℃前後で発酵し、発酵終期には酵母が液体の表面に浮いてきます。
味も香りも個性的なものが多く、多様性があります。
ヨーロッパなどでは上面発酵ビールが根強く飲まれています。
下面発酵酵母は10℃前後でゆっくりと発酵し、発酵終期には酵母が底に沈みます。
さっぱりした味わいですっきりしたのど越しが特長です。
15世紀に南ドイツで登場し、低温で発酵するため寒い時期にもビールづくりが可能なことや微生物の汚染リスクが低いことなどから19世紀にはビールづくりの主流となり、今や世界のビールの生産量の約9割を占めています。
主原料以外の副原料には様々なものがあり、アルコールのもとになるものと、香味付けに使われるものの2つに分けられます。
【アルコールのもとになる副原料】
米やトウモロコシからとったデンプン(スターチ)や、糖類があります。
これらの使用比率が高いと、酒税法では「発泡酒」とされます。
【香味付けに使われる副原料】
ラズベリーやチェリー、イチゴやリンゴなどの果物や、シソやハーブなどがあります。
これらの原料を使用すると、酒税法では「発泡酒」となります。

<参考サイト>
・ビールの原料って??
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/seminar/r5/2305/material.htm#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E9%BA%A6%E8%8A%BD,%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%82%E3%
・ビールの豆知識|ビールの造り方
https://www.brewers.or.jp/tips/production.html
・ビールの原料|4つの原材料の組み合わせで味わいが変わる!クラフトビールメーカーが解説
https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/material/
・これからビール通になりたい方へ
http://www.ji-beer.co.jp/app/Blogarticleview/index/ArticleId/43
④ つくり方により個性を生み出す!ビールの製法
ビールはどのようにつくられているか、調べてみました。
【製麦(せいばく)】
まずは麦を発芽させて麦芽をつくります。
デンプンやタンパク質を分解する酵素が生成されたり、大麦の成分を分解しやすい状態にしたりする工程で、ビールの色や香りはこの過程で特徴づけられます。
製麦は大きく3つの工程に分けられます。
<浸麦(しんばく)>
大麦を約15℃の水に2日間ほど浸すことで、発芽を促し、生育に必要な水分を吸わせます。
この間に水を入れ替えることで、大麦に含まれる雑味が溶け出し、また粒についているほこりも洗い流されます。
<発芽>
発芽室で15℃前後に保たれるよう冷風を送り、定期的に大麦を混ぜて発芽を促します。
硬い大麦の粒が発芽によりやわらかくなります。
<焙燥>
発芽した大麦を熱風で乾燥させて発芽を止めます。
約50℃から約80℃まで徐々に温度を上げます。
大麦は香ばしく仕上がり、雑菌が繁殖できないほど乾くため長期保存が可能になります。
またビールの色や香りの成分もつくり出されます。
焙燥の温度や時間を調整することで、多様な味わいが生まれます。
焙燥が終わったら、大麦から渋味や雑味のもとである伸びた根っこを取り除きます。
【仕込み】
麦芽やホップ、またビールの味を変化させるオレンジピールや果実などの副原料を使用して、糖やアミノ酸を含んだ麦汁をつくります。
仕込みは大きく5つの工程に分けられます。
<粉砕>
麦芽を細かくすることで、デンプンを糖化させやすくします。
ただし細かくしすぎるとろ過しにくくなり、また、穀皮と呼ばれる大麦の表面にある苦み成分が麦汁に溶けだしてしまうため、細かくなりすぎないように粉砕します。
<もろみづくり>
粉砕された麦芽をお湯と一緒に仕込み樽に投入し、これを撹拌しながら適度な温度に保ちおかゆのような状態にします。
<糖化>
麦芽に含まれるデンプンを酵素によって糖に分解します。
この工程を「糖化」と言います。
同時にタンパク質はうま味成分のアミノ酸に分解されます。
糖化が最も進む約65℃を維持することで、おかゆ状から透き通った色のサラサラな状態へと変化します。
<濾過>
穀や麦芽の粒などの固形物を、大きなざるのようなろ過装置で取り除き、透き通った状態にしていきます。
この時、一番最初に搾り出された麦汁は「一番麦汁」と呼ばれ、すっきりとして渋みのない飲みやすい味わいになります。
さらにこの後、残った固形分にお湯をかけてエキス分を抽出したものが「二番麦汁」で、多くのビールはこれも使用しています。
<煮沸>
ろ過された麦汁を煮沸釜に移し、ビールの苦味や香りを付けるホップを添加して煮沸します。
加熱によりタンパク質が凝集して、徐々に透き通った麦汁に変化します。
煮沸する時間によって、苦みや香りの付き方が変わります。
また煮沸は、好ましくない香りを飛ばしたり麦汁を殺菌したりする効果も期待できます。
ホップは煮沸の序盤に入れると苦味が出ますが香りが付きにくく、終盤に入れると苦味はあまり出ず、香りが残ります。
ホップを投入するタイミングや量により、ビールの風味に個性が生まれます。
【発酵】
仕込み段階で糖化してつくられた糖を酵母により分解し、アルコールと炭酸ガスをつくります。
まず麦汁を冷却機で発酵に適した温度まで冷やします。
発酵方法は主に、約10℃前後で6~10日間ほどの「下面発酵」と約20℃前後で3~6日間ほどの「上面発酵」の2つに分けられます。
適温になった麦汁に酵母を加え、同時に酸素を供給することで、酵母が増殖して発酵が進みます(主発酵)。
約1週間程度で「若ビール」と呼ばれる状態になりますが、これはまだ味にコクや深みのないものです。
【熟成】
若ビールを貯酒タンクへ移し、数日間熟成します。
熟成することで、好ましくないにおいの成分が別の物質に変換されます。
また熟成中も発酵が進み(後発酵)、炭酸ガスが発生します。
【熱処理・濾過】
不純物や固形物を除去するために熱処理やろ過をして、ビールの風味を保つため酵母を死滅させ、濁りの原因となる物質を取り除きます。
熱処理には、ビールを容器に詰める前に殺菌する方法と、詰めてから容器ごと殺菌する方法があります。
熱処理していないビールは「生ビール」と呼ばれます。
熱処理はかつてはビールづくりに不可欠な工程でしたが、醸造技術が発達し、現在日本で流通しているビールの多くが生ビールです。
また最近では、あえてろ過をせず酵母が生きたままの「無ろ過ビール」もあり、濃厚なコクとフルーティな香りの独特な味わいが楽しめます。
【充填】
完成したビールを缶や瓶、樽などの容器に詰めてしっかりと密封し、出荷します。

<参考サイト>
・ビールの作り方をわかりやすく解説|製造工程を詳しく説明
https://www.sakesen.com/blog/how-to-make-beer/
・ビールのつくり方を分かりやすく解説!工程から発酵や熟成の方法、豆知識まで
https://yonasato.com/column/guide/detail/craft_beer/process/
・ビールの製造方法とは? 工程ごとに詳しく解説
https://tanoshiiosake.jp/9571
・ビールの豆知識あれこれ! 雑学でビールをもっとたのしく
https://tanoshiiosake.jp/7026
⑤ ビールの種類は世界に100以上!日本のビールの定義とは?
ビールの種類のことを「ビアスタイル」と呼び、その数は100種類とも150種類とも言われています。
製法の紹介でも触れたように、発酵方法による分類では大きく2つに分けられます。
「上面発酵ビール」は「エール」とも呼ばれ、豊かな香りと豊潤な味わいの傾向があります。
「下面発酵ビール」は「ラガー」とも呼ばれ、すっきりとした味わいの傾向があります。
この他、自然界に存在する野生酵母を使って自然発酵させる、ベルギーの「ランビック」などのビールもあり、「ワイルドエール」として上面発酵に分類されることもあります。
「エール」と「ラガー」それぞれの、代表的なビールについて調べてみました。
【エール】
<ペールエール>
「ペール」とは「淡い」を意味し、イギリスで誕生した当時に飲まれていた他のビールより淡い色合いだったことが名前の由来と言われる。
モルトのコクを感じられる「イングリッシュ・ペールエール」と、ホップの香りがふんだんに感じられる「アメリカン・ペールエール」の大きく2つに分けられる。
<IPA(アイピーエー/インディア・ペールエール)>
イギリス発祥で、多彩な派生スタイルを持つ、アルコール度数高めのビール。
ホップを大量に使用してつくるため、ホップ由来の香りと苦味が際立つ印象的な味わい。
<ポーター>
18世紀初頭のロンドンで、「古くなった酸味のあるブラウンエール」と「つくりたての若いブラウンエール」、「ペールエール」の3種類を混ぜたものが始まりとされる。
茶系の色味とコクが特徴の「ブラウンポーター」と、より濃色でコーヒーやチョコレートを思わせる香ばしい風味を持つ「ロブストポーター」がある。
<スタウト>
アイルランド発祥で、「ポーター」から派生した、コーヒーのようなロースト香が特徴のビール。
「ドライスタウト」や「スイートスタウト」「フォーリンスタイルスタウト」「オイスタースタウト」など、様々な種類がある。
<ヴァイツェン>
小麦麦芽を使ったドイツ伝統の白ビールで、「ヴァイス」とも呼ばれる。
酵母をろ過した透明で澄んだ「クリスタルヴァイツェン」、無ろ過で白く濁った「ヘーフェヴァイツェン」などがある。
ホップ由来の苦味が少なめで、バナナやクローブのような香りが感じられる。
<アルト>
デュッセルドルフで18世紀頃に発展した、下面発酵なみの低温で熟成される銅褐色のビール。
「アルト」はドイツ語で「古い」の意味。麦芽由来の焙煎香と、まろやかなコクが感じられる味わい。
<ケルシュ>
ドイツのケルン地方の限られた醸造所で厳格なルールのもとにつくられたビールだけが名乗れる、ビールとしては珍しく原産地統制呼称が認められた、伝統的なビアスタイル。
淡い色と酵母由来のフルーティーな味わいが特徴で、なめらかな口当たり。
<ベルジャンホワイト(ベルギーホワイトビール)>
ベルギー発祥で、中世から親しまれている、麦芽にしない小麦と大麦麦芽でつくられる白ビール。
煮沸時にコリアンダーシードとオレンジピールを加えるため、柑橘系の甘くさわやかな香りとスパイシーな風味が楽しめる。
苦味が少なく、フルーティーで飲みやすい。
<アンバーエール>
アメリカ西海岸発祥の、琥珀色のエールビール。
「アメリカンアンバーエール」「アメリカンスタイルアンバーエール」とも呼ばれる。
焙煎モルトによるカラメルのような香りと濃厚なコク、ホップ由来の苦味が特徴で、肉料理とよく合う。
【ラガー】
<ピルスナー>
19世紀、チェコのピルゼン発祥。
現在、世界のビールの主流となっており、日本の大手メーカーがつくるビールの大半はこの「ピルスナー」と言われる。
アルコール度数は低めで、透き通るような黄金色とキレのあるさわやかなのどごし、ホップの苦味が特徴。
<シュヴァルツ(シュバルツ)>
ドイツ発祥の黒ビール。
ロースト麦芽の、ビターチョコを思わせる香ばしさや甘み、ほろ苦さが特徴。
シャープでスッキリとした味わい。
<ボック>
ドイツのアインベック発祥。
アルコール度数の高さが特徴で、14%を超えるものも。
苦味は少なめで、香りや味わいはモルトの個性により異なる。銅色から黒色と比較的濃い色合い。
<アメリカンラガー>
爽快なのどごしと軽い飲み口で、苦味やクセの少ないスッキリとした味わいが特徴。
淡い黄金色。

ビールの定義は国によって異なるそうです。
日本では酒税法により、麦芽・ホップ・水と、その他政令で定める物品(麦・米・トウモロコシ・デンプン・糖類など)を用いて発酵させた、アルコール分20度未満のお酒で、麦芽の比率が50%以上のものと定義されており、この定義から外れたものは「発泡酒」とされます。
外国から輸入されたビールに「発泡酒」と表示されている場合がありますが、原料に小麦麦芽や果実などを使っており「ビール」の定義に当てはまらない、といった理由からとのことです。
また「第3のビール」や「新ジャンル」と呼ばれるビールテイスト酒類もあります。ビールは税率が高いことから、1990年代初頭に低税率の発泡酒が生まれましたが、何回かの税率改定やビールの麦芽比率の定義の改定などもあり、発泡酒よりも税率の低い第3のビールが開発されました。
第3のビールは法律上、麦以外の原材料を用いて発酵させたものは「その他の醸造酒」、発泡酒に大麦由来のスピリッツ(純度の高いアルコール)を加えたものは「リキュール」に、それぞれ分類されます。
2023年の酒税法改正により、現在は発泡酒と第3のビールは同額の酒税になっています。
また2026年10月にはビールと発泡酒の税率が一本化されるとのことです。
最近よく耳にする「ノンアルコールビール」は、ビールとどのような関係なのでしょうか。
ノンアルコールビールとはアルコール分1%未満の「ビールテイスト飲料」のことです。
日本の大手メーカーがつくる多くのものはアルコール度数0.00%ですが、酒税法ではアルコール分が1%未満であれば酒類にはならないため、アルコールが含まれているノンアルコールビールもあるのだそうです。
製造方法はいくつかあり、日本の大手メーカーで多く採用されているのは、抽出した麦芽エキスに糖類や香気成分などを加えて調合する、アルコール発酵をさせない方法とのことです。
他には、ビールの発酵工程においてアルコール度数が1%を超えないように、アルコールを生成しにくい専用酵母を使ったり、途中で酵母を取り除いたり、低温下においてアルコール発酵を止めたりする方法や、通常のビールからアルコール分を除去する方法などがあります。
<参考サイト>
・ビールのスタイルは世界に100種類以上! 人気のビアスタイルをかんたんな解説とともに紹介
https://tanoshiiosake.jp/12575
・初心者でもわかる!ビールの種類(ビアスタイル)をビールメーカーが徹底解説
https://yonasato.com/column/guide/detail/beer_style_290319/
・ビールの豆知識|ビールの種類
https://www.brewers.or.jp/tips/type.html
・ビールの基本 ビールの種類
https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/daigaku/genre/bas/bas01.html
・ビールとは、どのようなお酒ですか?
https://www.suntory.co.jp/customer/faq/005769.html
・ビール・発泡酒に関するもの
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/abc/abc-beer.htm
・なぜビールなのに「発泡酒」って書いてあるの?【ビールの定義の話】
https://www.nipponbeer.jp/column/definition/
・ビールの「定義」とは?「発泡酒」や「第三のビール」との違いって?
https://tanoshiiosake.jp/3394
・「第三のビール」の魅力を知ろう! 「ビール」や「発泡酒」との違いとは?
https://tanoshiiosake.jp/7970
・ビールと発泡酒の違いは?第3のビール、クラフトビールについても解説
https://www.shufoo.net/plus/shopping_tips/591
・ビアスタイルを知ろう!<8>【ノンアルコールビール】
https://www.nipponbeer.jp/column_tag/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB/
・アルコール分0%でも本格的!「ノンアルコールビール」の味わい秘訣とおすすめ銘柄
https://tanoshiiosake.jp/7830
・ノンアルコール飲料って本当にアルコール0%?定義・醸造法や味わいについて解説
https://www.nihon-trim.co.jp/media/30417/
⑥ 《美味しい手延べ素麵》ビールのおつまみにふし麺のおやつ 編
手延べ素麵をつくるとき、素麵と一緒に生まれる「ふし麺」。
和風のクルトンのように、汁物にして食べる方が多いふし麺ですが、今回は小豆島の子どもたちには馴染み深い(?)食べ方をご紹介します。
「素麵の島」のおやつ『ふし揚げ』。
ふし麺をごま油やオリーブオイルで素揚げして、砂糖やきなこをまぶすだけで立派なおやつのできあがりです。
ポリッとした食感と、ふし麺の塩味と砂糖の甘みがほどよい、お手軽お菓子です。
揚げたてより、冷ましてから食べるのがおすすめです。
他にも醤油味やトウガラシを少し絡めたりして、お好みの味にすれば、立派な?ビールのアテにもピッタリなおつまみになりますよ。
数量限定で、あるときのみの販売となりますがご容赦ください。

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.41
栄養成分の機能性について/アミノ酸②
いや〜熱い!
暑さが厳しい折、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
石井製麺所では7月の発送シーズンのピークを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きそうとのことで、8月5日現在もたくさんのご注文を頂戴しております。
まだまだ、石井製麺所の素麵で少しでも涼しく美味しく元気よくお過ごしいただければと思います。
さて、今回のブログのお話は、4つ前のブログのテーマ「アミノ酸①」の続きになります。
アミノ酸が人の体に必要不可欠で、食べ物から積極的に摂らなければいけないということを学びました。
そのアミノ酸の働きで、食品に「うま味」を加えると聞かれたことがあるのではないでしょうか。
しかもそれを発見したのは日本人だとか。
グルタミン酸をはじめ、イノシン酸やグアニル酸というのは聞いたことがありますが、実はその他にもあるそうです。
このお話を調べたくてアミノ酸について調べていると、長くなりそうでしたので2回に分け、今回がその第二弾というわけです。
ところで、皆さんは、「もやしもん」というマンガをご存じでしょうか?
2004年に始まったそうですから今から20年前のマンガと言うことになりますが、発酵・熟成の勉強をするなら「読んだ方が良いよ」とお聞きしました。
そこには発酵熟成の理論や日本酒、ワインなどの詳しいお話をはじめ、日本の食糧事情や農業、酵母や菌のお話に加えてアミノ酸のお話もあるそうです。
ただ実は、昔、(原作の一部が)アニメ化されたときに見ていたことがあって、当時は面白いな〜と思っていただけでしたが、今になってその世界に踏み入れるとは思いもしませんでした。
最近はマンガをあまり読むことはありませんが、とても勉強になるとのことですので、一度、時間を作って読んでみたいと思います。
(追記)そして…思わずAmazonで全巻セットをポチってしまいました。便利な世の中ですね。
さてさて、お話を元に戻して。
小豆島の手延べ素麵は小麦粉とごま油の香りが特徴で、そこに「うま味」たっぷりのお出汁を利かせためんつゆが、素麵の美味しさをより一層引き立ててくれると思います。
新麺の開発に向けての勉強ではありますが、今回の「うま味」成分について学んでみると、自分好みの美味しいめんつゆができるのではないかと思っています。
「うま味」成分をいくつも掛け合わせると「うま味」の相乗効果といって、「うま味」の組合せは「1+1=2」ではなく、その何倍にも美味しさが膨らむそうですよ。
ぜひ今回のブログをお読みいただき、美味しいめんつゆやお出汁を利かせたお料理のお役に立てていただければと思います。
私も早速、「うま味」成分のひとつを多く含む干し椎茸と小豆島の醤油をベースに、オリジナルの美味しいめんつゆを作ってみたいと思います。
今回も最後までお楽しみいただければと思います。

【目次】
① 食べ物の味をつくり出すアミノ酸
② アミノ酸を増やし、より美味しくする発酵と熟成
③ 代表的なうま味成分と、うま味の相乗効果とは
④ うま味を発見したのは日本人
⑤ うま味を多く含む食品とは
⑥ 日本人と外国人の味覚の違いとは
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島の美味しい出汁セット 編
① 食べ物の味をつくり出すアミノ酸
食べ物の味は、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」の5つの基本味に分類されます。
人間にとって味を感じることは、生命維持のための欠かせない感覚です。
人体に有害なものの酸味や苦味などを感知することで危険な食物を避け、糖分の甘味やミネラルの塩味などを感じて栄養素を積極的に摂取するために必要なことだそうです。
うま味は、タンパク質を摂取したことを体に知らせるシグナルの役割を果たしており、うま味を感じることによって唾液や消化液が分泌され、タンパク質の消化をスムーズに進めることができるとのことです。
タンパク質には「味」がありませんが、細かく分解されてペプチドやアミノ酸になると味を持つようになります。
タンパク質を構成するアミノ酸は一般的には無味ですが、タンパク質が分解されて生じる遊離アミノ酸は味を持つそうです。
アミノ酸の中でうま味成分となるものは、グルタミン酸とアスパラギン酸です。
【グルタミン酸】
体内で合成できない必須アミノ酸。
体内で抗酸化作用を発揮するグルタチオンの材料のひとつ。
多くのアミノ酸がグルタミン酸をもとに合成されます。
世界で最初に見つけられたうま味成分で、昆布出汁から発見されました。
昆布の他にも、トマトやブロッコリーなどの野菜類、チーズなどの発酵食品に多く、他にもゼラチン、大豆製品、アーモンド、豚肉などに多く含まれています。

【アスパラギン酸】
体内でアミノフェラーゼという酵素によって生成される非必須アミノ酸。
エネルギー生産の場である「TCA回路」の最も近くに位置するアミノ酸のひとつで、エネルギー源として利用されます。
アスパラガスから発見されたのが名前の由来です。
醤油や味噌など発酵食品のうま味はアスパラギン酸によるものです。
肉類や、桜エビ、ゼラチン、大豆製品、タラ、落花生などに多く含まれています。

その他、甘味や苦味などを持つアミノ酸もあります。
【その他の味】
<甘味>グリシン・アラニン・トレオニン・プロリン・セリン
<苦味>フェニルアラニン・チロシン・アルギニン・イソロイシン・ロイシン・バリン・メチオニン・リシン
<参考サイト>
・うま味の基本情報
https://www.umamiinfo.jp/what/whatisumami/
・旨味とアミノ酸の関係とは?旨味を構成する2つのアミノ酸を徹底解説
https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/umami-amino-acid#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%20%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%EF%BC%92%E3%80%81%E6%97%A8%E5%91%B3%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B2%E3
② アミノ酸を増やし、より美味しくする発酵と熟成
食べ物の味は、アミノ酸の種類や組み合わせにより決まります。
アスパラギン酸はうま味と酸味を持っており、グルタミン酸と組み合わせることでさらに美味しくなることが知られています。
たとえば完熟トマトは、グルタミン酸とアスパラギン酸が4:1の割合で含まれていると最も美味しいそうです。
また同じ食材でも、加工方法によってアミノ酸の量が変わるので、味も変わります。
食べ物の中のアミノ酸の数と種類が多いほど美味しくなります。
食べ物の中のアミノ酸を増やすには、タンパク質を分解する必要があります。
その方法には「発酵」と「熟成」の2つがあります。
【発酵】
食材に付着した菌やカビなどの微生物がタンパク質や糖質を分解して、うま味のもととなるアミノ酸やアルコールなどをつくり出すことにより、うま味や風味、栄養価が増したり、保存性が高まったりします。
麹菌や乳酸菌、酵母菌といった微生物によって、味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、ワインなどの発酵食品がつくり出されます。
【熟成】
食品がもともと持っている酵素の力で、タンパク質の構造を壊してアミノ酸へ変換します。
肉や魚を適切な環境下に置くと、タンパク質が分解されてアミノ酸などのうま味成分が増えて、より美味しくなります。
ただし温度や雑菌の管理は難しいため、家庭で熟成肉や熟成魚をつくることは避けたほうが良いようです。

③ 代表的なうま味成分と、うま味の相乗効果とは
うま味物質は、アミノ酸系と核酸系に大きく分けられます。
核酸は、ヌクレオチドとも呼ばれるリン酸を含んだ物質で、生物の代謝や運動エネルギー源となるアデノシン三リン酸(ATP)が有名です。
三大うま味成分とされるグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸のうち、イノシン酸、グアニル酸は核酸系に分類されます。
この3つにアスパラギン酸とコハク酸を加えて五大うま味成分とすることもあり、コハク酸は有機酸系に分類されます。
有機酸とは、窒素を含まない炭素化合物で、エネルギー代謝サイクルに重要な物質です。
【イノシン酸】
カツオ節のうま味成分として発見され、カツオ節に多く含まれることで知られています。
体内のATPが酵素により分解された後の生成物で、肉や魚など動物性の食材に多く含まれます。
筋肉中にもともと含まれるアデニル酸が、動物の死後、酵素の働きによりイノシン酸に変化して増えます。

【グアニル酸】
干しシイタケなどの乾燥キノコやドライトマト、ズワイガニ、ウニなどに多く含まれます。
乾燥キノコの戻し汁にはグアニル酸の元となるリボ核酸が抽出され、それを一定の温度帯で加熱するとグアニル酸に変わるそうです。
生のキノコ類は細胞壁が壊れていないので、リボ核酸が抽出されにくく、グアニル酸の生成量が低いとのことです。

【コハク酸】
コハク酸脱水素酵素という形で体内に存在しています。
貝類や清酒のうま味成分で、酸味や苦味と混ざったようなうま味となります。
コハク酸をメインとした調味料は一般的ではありませんが、美容や健康への働きもあるため化粧品や入浴剤にも使われているそうです。

うま味物質は単独で使うよりも、アミノ酸であるグルタミン酸と、核酸系のイノシン酸やグアニル酸を組み合わせることで、うま味が飛躍的に強くなることが知られており、それを「うま味の相乗効果」と呼びます。
グルタミン酸とイノシン酸の比率が1:1の時にもっともうま味が強くなるそうで、単独で味わうときに比べて約7〜8倍とされています。
世界各地で古くから、うま味を組み合わせて出汁をとることが経験的に行われてきました。
例えば、和食では昆布(グルタミン酸)とカツオ節(イノシン酸)、洋食ではトマト(グルタミン酸)と海老(イノシン酸)とムール貝(コハク酸)、セロリ・タマネギ・ニンジン(グルタミン酸)と牛肉(イノシン酸)、中華料理では白菜・ネギ(グルタミン酸)と鶏肉(イノシン酸)、など。

<参考サイト>
・うま味の成分
https://www.umamikyo.gr.jp/knowledge/ingredient.html
・旨味とは?主要な5つの旨味成分と多く含まれている代表的な食材
https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/umami-component
・イノシン酸とは?鰹節に多く含まれているイノシン酸の生成メカニズム
https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/inosinic-acid
④ うま味を発見したのは日本人
うま味は基本味の一種で、甘味・酸味・塩味・苦味の4つの基本味を混ぜ合わせてもつくることができない、独立した味です。
基本味は長年、甘味・酸味・塩味・苦味の4つであると考えられてきました。
1908年、池田菊苗博士が昆布出汁の主要な味の成分であるグルタミン酸の抽出に成功し、その味を「うま味」と命名しました。
これに続いて、カツオ節に含まれるイノシン酸、干しシイタケに含まれるグアニル酸も、うま味を持つことが解明されました。
池田菊苗博士は、グルタミン酸を主成分とした調味料(グルタミン酸ナトリウム)の製造法特許を取得しました。
この功績により特許庁の「日本の十大発明家」の一人に選ばれています。
1909年には最初のうま味調味料が市販され、1940年代までには世界各地でも販売されるようになり、現在では世界100カ国以上で広く使われているそうです。
1985年に開催された「第一回うま味国際シンポジウム」を機に、「うま味(UMAMI)」という用語が国際的に使用されることになったそうです。
うま味は、欧米では長らく味覚として捉えられていませんでした。
ようやく味覚として認められたのは2002年以降、うま味の受容体が発見されてからだそうです。
人間は舌にある味蕾により味を感じます。
味蕾とは、味を感じる味細胞が数十個集まっている器官です。
味細胞にあるタンパク質分子である味覚受容体の中で、グルタミン酸により強く活性化されるものがあることが分かったのが2002年とのことです。
ちなみにうま味の相乗効果の分子メカニズムが解明されたのは、2008年。
イノシン酸などの核酸系のうま味成分が、うま味受容体においてアミノ酸とは異なる部位に結合し、受容体の活性を増強することで、受容体がグルタミン酸のうま味をより強く受け取るようになることが分かりました。

<参考サイト>
・食とアミノ酸
https://www.ajinomoto.co.jp/amino/life/shoku.html
・うま味の知識
https://www.umamikyo.gr.jp/knowledge/discovery.html
・世界で認められてこなかった「旨味」が味覚研究の鍵になっている
https://www.meiji.net/it_science/vol377_yasuka-toda
⑤ うま味を多く含む食品とは
うま味は、私たちが普段から口にする様々な食品に含まれています。
その中でもうま味を多く含むいくつかの食品について、調べてみました。
【昆布】
褐藻類に属し、北海道を中心に広く東北の一部にかけて収穫されます。
グルタミン酸を豊富に含み、アスパラギン酸も含みます。
主に出汁用として使われるのは、真昆布、羅臼昆布、利尻昆布です。
2 年成長したものを7月から9月にかけて収穫し、その日のうちに乾燥します。
昆布出汁の取り方には、「水出し」と「煮出し」があります。
「水出し」は、昆布を水に入れてラップや蓋をして冷蔵庫で一晩寝かせます。
「煮出し」は、鍋に水と昆布を入れて30分ほど置いてから火にかけ、沸騰直前で昆布が浮いてきたら取り出します。
昆布のうま味は60℃で最も抽出され、80℃を超えると抽出されにくくなるそうです。
昆布を取り出した後の出汁は、臭みをなくすため沸騰させたら完成です。
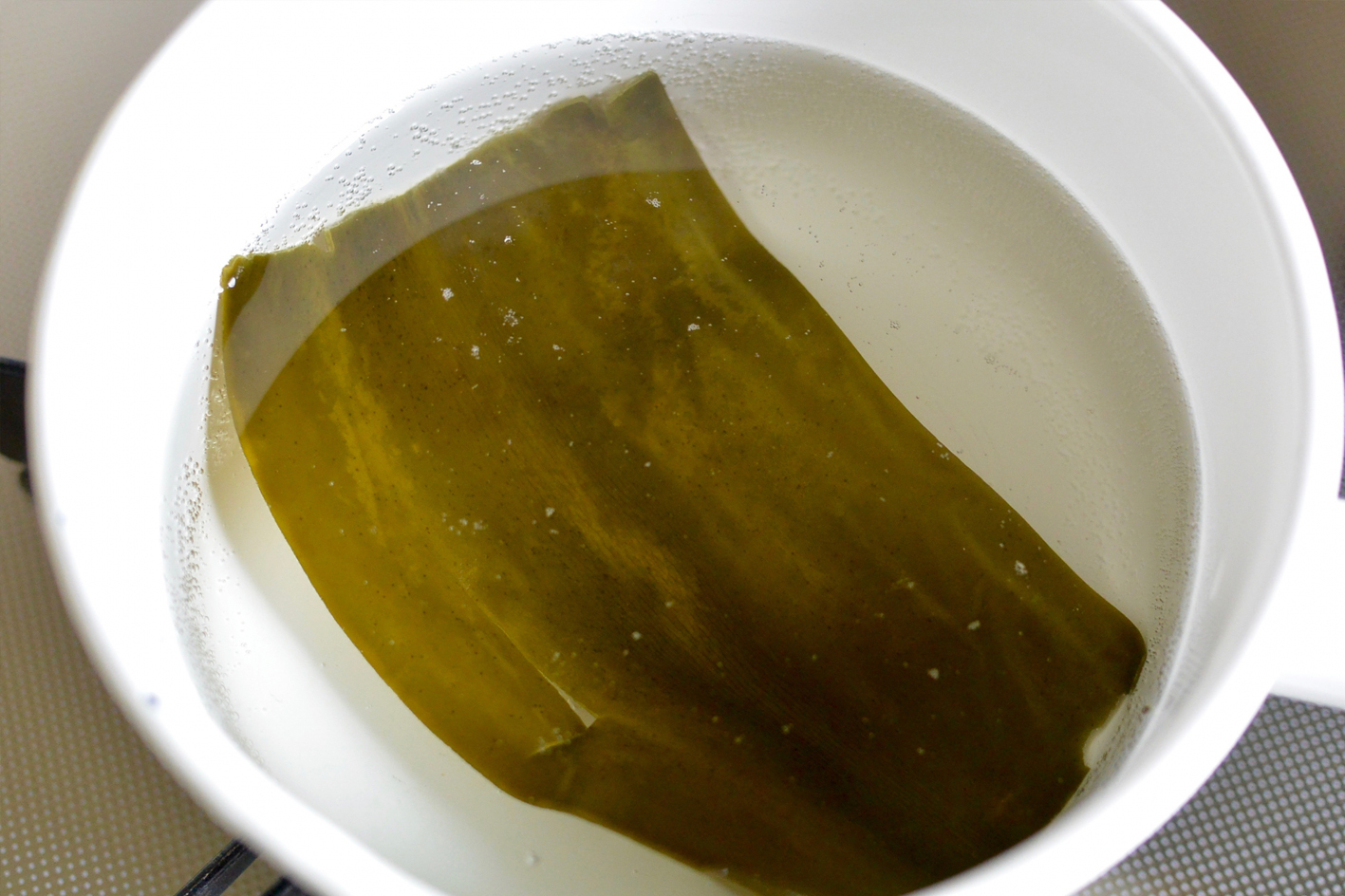
【カツオ節】
タンパク質が豊富なカツオを乾燥させて、発酵を誘発する有益なカビを含浸させることにより、深く豊かな風味を生み出しています。
数カ月かけて完成したカツオ節は、削り機で削られ和食の出汁に使用されます。
生のカツオよりもイノシン酸が豊富に含まれ、昆布出汁のグルタミン酸と合わせるとうま味が相乗的に増します。
薄く削ることで、水に溶けやすい性質を持つイノシン酸の抽出を短時間で行うことができ、水に溶けにくい他のアミノ酸の雑味や濁りを防ぐそうです。
カツオ節の出汁の取り方は、鍋に水を入れて火にかけ、気泡がポコポコ湧いてくる程度に沸騰したら火を止め、すぐにカツオ節を入れ、蓋をせず10分置きます。
厚削りの場合は、火を止めずに弱火で10分~20分煮出します。
ザルにキッチンペーパーを敷いてゆっくり出汁を濾したら完成です。
カツオ節を混ぜたり搾ったりすると苦味や生臭さが出てしまうそうです。

【干しシイタケ】
生のシイタケにはグルタミン酸やイノシン酸が豊富に含まれています。
乾燥させることでグアニル酸が生成し、また水分が減ることでうま味成分が凝縮されます。
干しシイタケは風味豊かで独特の香りがあり、その戻し汁は出汁として利用されます。
干しシイタケのうま味は10℃を超えると破壊され始めるそうなので、水に干しシイタケを入れてラップや蓋をして冷蔵庫で一晩寝かせて出汁を取るのが良いそうです。

【醤油】
大豆・小麦・塩を主原料とし、微生物による発酵によってつくられる液体発酵調味料。
醤油のうま味は、大豆と小麦に含まれるタンパク質が麹菌の酵素で分解され、グルタミン酸を始めとする約20種類のアミノ酸に変化することで生まれます。
基本味の5味をすべて兼ね備え、300種類以上の香り成分を持ち、料理に深い味わいを与えます。

【味噌】
原料である大豆にはタンパク質が豊富に含まれており、麹菌の働きにより、味噌ができるまでの発酵過程で、その約30%がさまざまな種類のアミノ酸に分解されていきます。
グルタミン酸が最も多く含まれ、次いでアスパラギン酸が多く含まれます。
発酵期間が短い白味噌はアミノ酸の量は少なく、発酵期間が長くなるほどアミノ酸が増えていきます。

【トマト】
グルタミン酸を多く含み、熟すにつれてさらに増えます。
ドライトマトは、うま味が凝縮されています。
世界中でトマトを用いた調味料が使われています。
トマトソースは一般的に肉や魚と一緒に食されるため、肉や魚に含まれるイノシン酸との相乗効果でうま味が一層強く感じられます。
【チーズ】
チーズは熟成期間が長くなればなるほど、タンパク質がアミノ酸に分解され、うま味成分が増加します。
通常2年間、最高級品では4年間も熟成させる「パルミジャーノレッジャーノ」というチーズには、昆布に含まれるのと匹敵する量のグルタミン酸が含まれています。
他にも「エメンタール」や「チェダー」「カマンベール」などにも豊富だそうです。
熟成させていないフレッシュチーズには特有の味を持つ遊離アミノ酸がほとんど含まれていないため、あっさりとした味わいです。
【生ハム】
加熱工程のないハムで、イタリアのパルマハム、スペインのハモン・セラーノ、中国の金華ハムなどが有名です。
原料となる生の豚肉にはイノシン酸が豊富に含まれていますが、豚肉を塩漬けした後長期間熟成させることによりイノシン酸は減少し、グルタミン酸が増加します。
さらに水分が減少するのでうま味が凝縮されます。
<参考サイト>
・うま味を多く含む食品
https://www.umamiinfo.jp/richfood/
・うま味成分とは?種類の違いや含有量の多い食品も紹介
https://www.furutaya.com/blog/umami-ingredients/
・今日からできる!5つの素材別だしの取り方とだしがら有効活用方法
https://www.kobayashi-foods.co.jp/washoku-no-umami/stock-cooking
⑥ 日本人と外国人の味覚の違いとは
うま味が欧米で味覚として長年認められていなかったと前述しましたが、実際、日本人と外国人とで味の感じ方は違うものなのでしょうか?
日本人100名と外国人100名を対象に行われた「味覚力調査」(AISSY株式会社・2015年)によると、「うま味」についての日本人の正答率は71%で、外国人の正答率の34%の2倍以上だったそうです。
さらに「味覚力調査」の全体の傾向を見ても、外国人に比べて日本人の方が「味覚を感じる力が強い」ということが分かったとのことです。
また、世界各国の代表的な料理を比較したところ、日本の料理はうま味が強いという結果が出たそうです。
緑茶と紅茶、コーヒーの比較でも、緑茶は旨味の強さが特徴と言えるようです。

<参考サイト>
・日本人100名vs.外国人100名「味覚力調査」を実施/日本人の「旨味」正答率71%、外国人の正答率34%の2倍以上
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000012897.html
・日本人の味覚力は外国人の倍以上だった!
https://dime.jp/genre/416112/#google_vignette
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島の美味しい出汁セット 編
小豆島の原風景とも言える、山あいの、川沿いに田畑が広がる中山(なかやま)に、 知る人ぞ知る美味しいシイタケを育てる「箭木(やぎ)椎茸園」があります。
その原木シイタケを使った干しシイタケを、美味しいめんつゆやスープに使えるようにとご相談させていただき、現在は干しシイタケを仕入れ、石井製麺所の手延べ麺とセットにしています。
ご相談に伺った際にはシイタケの栽培現場も見学させていただきました。
ほだ場(収穫場)一面にずらっと並べられたクヌギの原木は、 柔らかい日の光を浴びて、次に育つシイタケのために静かに力を蓄えているのでしょうか。
案内をしていただいたのは、五代目の箭木槙也さん。
代々ご家族でシイタケ農家を営まれており、現在は四代目であるお父様(箭木宏中さん)と、 親子二人で力を合わせて、原木の切り出しから乾燥(干しシイタケ)まで手掛けていらっしゃいます。
石井製麺所は海近くにある製麺所ですが、小豆島は車で少し走ると山の景色に出会います。
その山間の奥深いところに「箭木椎茸園」さんがあり、ここまで奥深く来たのは初めてでした。
シイタケ栽培に対するお考えをお聴きすると、「いかに雑菌に負けないように、シイタケ菌を原木内に行き渡らせるか」が勝負…とのこと。
原木の伐採と植菌の時期、木の種類や太さに応じたシイタケ菌の品種の選び方など、 目には見えない小さな菌のために心を配る、その仕事の一端を教えていただきました。
そんな箭木さんの育てる干しシイタケは、小豆島の産直でも人気で、島民にとって特別な一品です。
肉厚でうま味が詰まったシイタケは、いつもの食卓をちょっと贅沢なものにしてくれます。
「傘の裏側に黄色は、美味しい干しシイタケ茸の目印」 小豆島の“とっておき”の干しシイタケです。

【干しシイタケのうま味成分は、そうめん・うどんと相性バッチリ!】
箭木さん直伝の出汁の取り方は、 「干しシイタケを冷水で“5時間”かけてゆっくり戻す」こと。
干しシイタケのうま味成分グアニル酸の性質を踏まえた、これがベストな方法なのだそうです。
その干しシイタケのうま味を活かしためんつゆやお出汁で美味しい手延べ麺を召し上がってみてはいかがでしょうか。
いつもより時間をかけて、ちょっと贅沢な味をお楽しみください。
《美味しい出汁で味わう<夏>セット》 https://141seimen.thebase.in/items/86095113
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.40
麺究者への道/チーズについて研究してみる
先日、石井製麺所のお客様に「乾平うどん」のDMをお届けさせていただいたのですが、「乾平うどん」のご評価も色々いただくことができ、忙しくも嬉しい日々を過ごしております。
今だけの「小豆島カレーうどんセット」も販売しております。
宝食品様の「オリーブ牛ビーフカレー」のレトルトと、丸島醤油様の「味醤油」と「乾平うどん」をセットにした、まさに小豆島のカレーうどんのために集めたセットです。
セットを考える中で、色々と試食もしてみましたが、美味しくいただけるセットになっていると思いますので、こちらもぜひお試しください。
詳しくはブログを最後までご覧ください。
さて、現在、「発酵」や「熟成」の技術を活用した新麺開発を考えているため、「発酵・熟成」について色々調べているところですが、本当に「発酵・熟成」というジャンルは奥が深いですね。
前々回のブログ「麺究者への道」では、日本の食文化において「発酵・熟成」には欠かせない、日本酒について調べてみましたが、今回は打って変わって、「チーズ」です。
素麵とチーズでは、食べ方も全然違いますし、和と洋で世界観も異なります。
チーズは「発酵・熟成」の申し子とも言えるのではないでしょうか。
科学的な技術や知識など無かったときから「菌」や「酵母」といった、そのままではほとんど目に見えないものを活用するって、一体誰が始めたんでしょうか。
素麵づくりでは目に見えて、しかも手に取れる「小麦粉」「水」「塩」といった組合せを一日で麺に仕上げていきますが、気温や湿度、気圧など様々な要因と組合せながら安定した品質に仕上げていくことは、大変なことです。
「菌」のように目に見えない不確定なものを活用して、味わい、色、形、匂いなどなど均一に仕上げるのですから、膨大な経験知の集積だと思います。
コラムのネタを調べていると、その技術や製造方法など本当に興味深いものが多く、なにより産地というものが大変重要視されていることに気付きます。
以前にもブログで書きましたがGIといわれる産地を守る規格で、その製造方法はもちろん品質や味わいも守られています。
小豆島手延べ素麵も小豆島を代表する特産品で、日本三大素麵に数えられる産地です。
この産地としての誇りだけでなく、島の製麺所のみなさんと小豆島の手延べ素麵を守り、続け、そして進化させていきたいなと、改めて感じる回となりました。
今回も素麵からは少しお話が離れてしまいますが、一緒にチーズの世界を勉強してみませんか。
最後までお付き合いをお願いいたします。

【目次】
① 世界各地で発展するチーズ、始まりはメソポタミア地域
② 重要なのは発酵と熟成!チーズの定義と製法
③ ナチュラルチーズの7つのタイプとは?
④ 地理的表示(GI)で保護されるEU産チーズとは?
⑤ 産地由来が多い!世界のチーズの名前
⑥ 日本のチーズ「蘇」とは?「醍醐」もチーズ?
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島のカレーうどんといったらコレ? 編
① 世界各地で発展するチーズ、始まりはメソポタミア地域
チーズが生まれたのは紀元前4000年頃で、人類最古の食品の1つと言われています。
古代エジプトの壁画にチーズの製造法が描かれていたそうです。
紀元前6000年頃から、人類は家畜化した山羊や羊の乳を搾り食用とするようになっていました。
自然界に存在する乳酸菌の働きにより乳が固まり水分が分離するのを発見したのが、チーズづくりの起源とされています。
乳は水分が多く栄養豊富で傷みやすく、搾りたてでなければ飲むことができなかったため、乳を保存する方法の1つとしてチーズが生まれたようです。
紀元前4000年頃、メソポタミア地域(チグリス川、ユーフラテス川流域)から東西に広がっていき、世界各地でそれぞれの気候風土や生活様式に根差したチーズが生み出されてきました。

ヨーロッパへはトルコ・ギリシャを経て伝わり、ローマ時代には平民や兵士たちも毎日チーズを食べるほど広く普及していたようです。
チーズづくりは大切な産業になり、紀元前36年以後には詳細なチーズの製造法の記録があるとのことです。
品質が改良され種類も増え、裕福な階層では少なくとも13種類のチーズが食べられていたそうです。
現存するヨーロッパ最古の料理書を書いた美食家マルクス・ガビウス・アピシウスも、チーズ料理について書き残しています。
ローマのヨーロッパ制覇に伴いチーズはヨーロッパ全土に広がりました。
チーズの製法は秘伝のような形で伝えられ、中世の修道院や封建領主によっても守られ、それぞれの地方で多彩な種類のチーズが生まれました。
メソポタミア地域からシルクロードに沿って、パキスタン、インド、モンゴル、中国へ伝わったルートもあります。
インドでは紀元前3000年のものとされる「ベーダの賛歌」に、チーズを勧める歌があるそうです。
また、紀元前2000年頃のアラビアに、チーズ誕生にまつわる民話があります。
アラビアの商人が、羊の胃袋でつくった水筒に乳を入れラクダの背にくくりつけて旅に出ました。
1日の終わりに乳を飲もうとすると黄色っぽい液体と白い塊になっており、その固まりを食べてみると非常に美味しかった、というものです。
羊の胃袋にある「レンニン(キモシン)」という酵素が乳を凝固させ、歩いている間に揺られてチーズになるという原理は、今でもチーズ製造に利用されているものです。

日本へは、飛鳥時代に中国を経て百済(くだら)から伝わったとのことです。
6~7世紀頃、仏教とほぼ同時期に、乳牛を飼うことが伝えられ、チーズの原型「蘇」が日本にもたらされました。
牛乳を煮詰めて固めたもので、栄養価が高いことから珍重され、身分の高い貴族しか口にすることのできない貴重なものでした。
平安時代には蘇を天皇に献上する制度ができ、盛んにつくられるようになりました。
その後、権力が武家に移るにつれてこの制度もなくなり、蘇もつくられなくなっていったとのことです。
江戸時代、八代将軍徳川吉宗はオランダ人の勧めにより、1727年にインドより白牛を輸入し、現在の千葉県南房総市に牧場をつくり、その牛の乳から「白牛酪(はくぎゅうらく)」をつくり始めました。
牛乳を煮詰め乾燥させて団子状に丸めたもので、バターという説もありますが、よりチーズに近いものと考えられています。
疲労、衰弱、栄養不足からの回復のため、削って食べたり、湯に溶かして飲んだりしていたそうです。
現在私たちが食べているような西洋型のチーズは、1875年に、北海道の開拓庁の試験場で、アメリカのエドウィン・ダンが、チェダーチーズの製法を指導したことが始まりとされています。
1904年頃から函館のトラピスト修道院でもつくられるようになりました。
昭和初期までチーズの消費量はごくわずかで、ほとんどが輸入品でした。
日本で本格的につくられるようになったのは、1933年、北海道製酪販売組合連合会(現在の雪印メグミルク株式会社)が、北海道の遠浅にチーズ専門工場をつくってからだそうです。
ゴーダチーズの生産を本格的に開始し、1934年には「雪印北海道チーズ」(プロセスチーズ)が発売されました。
戦争によりチーズ生産の一時中止を経て、戦後、食生活の洋風化や生活水準が向上した1950年後半からチーズの消費は急激に伸びました。
ピザやチーズケーキの広まり、ワインブームや健康機能への注目などもあり、チーズは日本人の食生活に定着しています。

<参考サイト>
・世界のチーズの歴史
https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/history/world/index.html
・チーズの歴史
https://www.j-milk.jp/findnew/chapter3/0101.html
・【Milk Knowledge】世界のチーズこぼれ話
https://www.j-milk.jp/knowledge/products/hn0mvm0000005mj6.html
・チーズの歴史
https://www.qbb.co.jp/enjoy/cheese/history
・日本のチーズの歴史
https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/history/japan/
② 重要なのは発酵と熟成!チーズの定義と製法
チーズは、乳酸菌や酵素の働きにより、乳のタンパク質(カゼイン)を固めたもので、原料となる乳の種類や発酵形式により様々なチーズができます。
「FAO/WHO(国連食糧農業機関/世界保健機関)」による定義では、チーズとは、フレッシュまたは熟成した、固形または半固形の製品で、以下のいずれかの方法でつくられたものです。
(a)凝乳酵素(レンネット)または微生物や植物由来の凝固剤の作用により、乳、脱脂乳、部分脱脂乳、クリーム、ホエイクリーム、バターミルク、またはこれらの混合物を凝固させ、この凝固物より分離する乳清(ホエイ)を部分的に流出させてつくるもの。
(b)乳および、乳から得られる原料を用い、凝固を引き起こす加工技術により、(a)に限定されている製品と同じ化学的、物理的、官能的な特徴を持つ製品。
凝乳酵素とは、反芻動物の第4胃から抽出した酵素のことで、微生物からつくるものもあります。
チーズは「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」の2つに分けることができます。
【ナチュラルチーズ】
牛や山羊、羊などの乳に乳酸菌や凝乳酵素を加え、乳のタンパク質を凝固させて凝乳(カード)をつくり、そこから乳清の一部を取り除いたものです。
ナチュラルチーズは、時間の経過に伴いワインのように熟成変化していき、複雑な風味を持ちます。
原料や製法、風土の違いなどにより、世界中で1000種類以上あるそうです。
【プロセスチーズ】
1種類または数種類のナチュラルチーズを砕き、タンパク質を溶かす働きのある乳化剤を加えて加熱・溶融・乳化し、再び成形して冷却したものです。
加熱することにより熟成に関与する微生物や酵素の働きを止めるため、保存性に優れ、品質が安定しています。
スライス、キャンディ、ブロックなど様々に形状を変えられ、幅広い料理に利用されています。
日本で多く消費されているのがプロセスチーズです。

チーズの製造には乳酸菌が欠かせません。
搾った乳を温かいところに置いておくと、乳酸菌の働きにより乳糖が乳酸に変わるため酸っぱくなります。
これが乳酸発酵という、チーズづくりの基本的な工程の1つです。
乳酸発酵によりpHを下げることで有害微生物の繁殖を防いだり、チーズ特有の味や香りをつくり出したりします。
チーズがどのようにつくられているか、種類や産地により異なる部分もありますが、一般的な製法について調べてみました。
【ナチュラルチーズ】
<加熱殺菌>
原料となる生乳を加熱殺菌します。牛乳は食品衛生法により、「保持式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること」と規定されています。チーズ製造の場合は、63℃で30分の低温長時間殺菌か、72~75℃で15秒の高温短時間殺菌が一般的です。
もともと乳の中にいた乳酸菌は他の雑菌とともにいなくなってしまうため、次の工程で改めて純粋培養した乳酸菌を加えます。
<凝固>
乳酸菌や凝乳酵素を加えると、タンパク質が固まりプリン状になります。
固まったものを凝乳と呼びます。
<カード切断>
凝乳をカットすることで表面積を大きくし、水分(乳清)を出しやすくします。
柔らかく仕上げるチーズは乳清をあまり抜かず、硬く仕上げるものはカードを細かく切って乳清をより多く分離します。
<攪拌・加熱>
カード全体を静かに攪拌し、徐々に温度を上げていくと、カードが収縮して弾力のあるカード粒となります。
<型詰・プレス>
カード粒を型に詰めて圧搾し、さらに水分を出します。
熟成しないフレッシュタイプのチーズはここで完成です。

<加塩>
雑菌の繁殖を抑え風味を良くするため、塩を加えます。
表面に塩を擦りこむか、または塩水に浸します。
白カビタイプやウォッシュタイプのチーズでは、この後周囲から微生物を付けていきます。

<熟成>
熟成庫に置き、各チーズに適した温度、湿度、期間で熟成させます。
チーズに存在する微生物や酵素の働きで、タンパク質が分解されアミノ酸になり、香りや旨みがどんどんつくられます。

【プロセスチーズ】
<粉砕>
原料となるナチュラルチーズを細かく粉砕します。
1種類の場合から数種類の場合まで様々です。
<加熱・溶融・乳化>
75~120℃で加熱しながら乳化剤である溶融塩(リン酸ナトリウムなど)を加え、溶かします。
加熱により発酵熟成が止まるので、風味や品質が安定し、長期保存が可能になります。
<型詰・成型>
熱いうちに型に流し込み、いろいろな形に成型します。
<冷却>
冷やして固めます。
ナチュラルチーズの多種多様な風味や香りを特徴づけるのに重要な工程が、熟成です。
ヨーロッパなどにはチーズの熟成を専門に行う「チーズ熟成士」という職業があり、チーズの本場フランスでは、職人にとって最高の栄誉である「M.O.F(フランス最優秀職人)」の称号の対象となっているそうです。
熟成士は生産者からチーズを買い入れ、独自の熟成庫で温度や湿度の管理、反転(チーズを均等に熟成させたり形を整えたりするための作業)やブラッシング(外側のカビや微生物の量を調節する作業)などをしながら、丁寧にチーズを熟成して市場に送り出しているとのことです。

<参考サイト>
・チーズの定義
https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/teigi/
・チーズの作り方
https://www.chesco.co.jp/cheese/dictionary/make/
・チーズの製造方法
https://www.j-milk.jp/findnew/chapter3/0303.html
・チーズができるまで
https://cheese-fun.jp/basic/process/
・牛乳はどのように殺菌されているのですか?
https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_012_463/
・LTST殺菌
https://www.cheese-professional.com/article/news/detail.php?KIJI_ID=1240
・チーズ学
https://www.j-milk.jp/knowledge/nutrition/berohe000000efu5.html
・チーズの熟成について
https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/made/mature/
・チーズ熟成士
https://www.lammas.jp/page/14#:~:text=%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%86%9F%E6%88%90%E5%A3%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA,%E5%B0%82%E9%96%80%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%86%E8%81%B7%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E4%B8%81%E5%AF%A7%E3%
・チーズ熟成士
https://www.order-cheese.com/content/category/fromager-affineur
・「熟成士 Affineur ~アフィナー~」とは
https://www.lecomptoir.co.jp/blogs/about-cheese/cheese-affineur
③ ナチュラルチーズの7つのタイプとは?
ナチュラルチーズは、さらに7つのタイプに分けられます。
【フレッシュタイプ】
熟成させないため、他の6タイプに対して「非熟成タイプ」とも呼ばれます。
水分が多くてやわらかく、ミルクの香りとさわやかな酸味があり、つくりたての風味を楽しむチーズです。
代表的なものは、モッツァレラ、リコッタ、カッテージ、クリームチーズ、マスカルポーネなど。
モッツァレラは、熱湯の中で固まった凝乳を練るという製造工程が一般的だそうです。
シンプルな味わいで、弾力と食べ応えがあります。
リコッタは、モッツァレラをつくる際の乳清を加熱してつくるそうです。
カッテージはやわらかいそぼろのような口当たりが特徴。
クリームチーズは原料にクリームを使用しており、脂肪分が高めでこってりとした濃厚な味わいです。
マスカルポーネは原料のクリームを加熱しクエン酸を加えたものを凝固させてつくります。
ややクリーム色で、口当たりなめらかでほのかな甘みがあります。
【白カビタイプ】
白カビを表面に植え付け、乳酸菌とともに熟成させます。
外側から内側へと熟成していき、熟成が進むにつれ中がクリーム色になり、とろりとして味や香りも変化します。
表皮に分厚い白カビをまとい、中身はやわらかく食べごたえのあるカマンベールや、ブリー、バラカなどが代表的です。
【青カビタイプ】
ブルーチーズとも呼ばれます。
内部に青カビを植え付け、乳酸菌とともに熟成させます。
内部は大理石のような美しい青い模様になり、青カビが独特の香りと風味を生みます。
イタリアのゴルゴンゾーラ、フランスのロックフォール、イギリスのスティルトンは世界3大ブルーチーズとされています。
他に、ババリアブルー、ダナブルーなどがあるそうです。
ゴルゴンゾーラには、やわらかくてマイルドな味わいの「ドルチェ」と、青カビの風味がしっかりしている硬めの「ピカンテ」の2種類があります。
ロックフォールは、原料である羊の乳の独特な甘味と、洞窟で熟成させることで生まれる複雑な風味が特徴の個性的なチーズです。
スティルトンは、塩味が聞いたシャープな味わいとのことです。
【ウォッシュタイプ】
熟成の際に表面を塩水やビール、ワイン、ブランデーなどで何回も洗いながら、内部を熟成させます。
独特の強い香りがする個性的なチーズ。
表面はオレンジ色で、内部はクリーム色です。
代表的なものは、マロワル、エポワス、ラングル、リヴァロ、ポン・レヴェックなど。
エポワスは地酒であるマール・ド・ブルゴーニュで洗うため、香ばしさと複雑な風味があります。
【シェーブルタイプ】
「シェーブル」とはフランス語で山羊の意味。
濃厚でコクのある山羊の乳でつくられます。
小型で乾燥熟成したものが多いそうです。
熟成が若いうちはさわやかな味わいで、熟成が進むに連れて酸味がまろやかになり、より複雑な風味に変化します。
代表的なものは、ヴァランセ、クロタン・ド・シャヴィニョル、サント・モール・ド・トゥレーヌ、バノンなど。
ヴァランセはかつてスラッとしたピラミッド型をしていましたが、エジプト遠征で敗北したナポレオンの命令により、上部が切られたピラミッド型になったと言われるチーズです。
サント・モール・ド・トゥレーヌは、薪のような細長い形をしたチーズで型くずれしないよう中心に藁を入れて熟成します。
表面は木炭がまぶされているためグレー色なのが特徴です。
【セミハードタイプ】
殺菌乳を凝乳酵素で固めた後、プレスして水分を取り除き、乳酸菌により時間をかけて熟成させます。
くせのない味わいで、食べ頃が長く続き、水分量が少なく保存しやすい硬質のチーズです。
代表的なものは、ゴーダ、マリボー、サムソーなど。
【ハードタイプ】
1〜3年と長期熟成させてつくる、水分量がとても少なく硬いチーズです。
粉状にして使われることもあります。
代表的なものは、チェダー、エメンタール、ラクレット、エダム、パルミジャーノ・レッジャーノ、コンテ、パルメザンなど。
パルミジャーノ・レッジャーノは「イタリアチーズの王様」とも呼ばれます。
最低熟成期間が12カ月と長く、旨味とコクがギュッと詰まっています。
コンテは山の中でつくられ、「山のチーズ」とも呼ばれます。
直径約55〜75cmの大きい車輪型で、マイルドで食べやすい味わいです。
雪に覆われる冬を越すために保存食として食べられていた歴史もあるそうです。
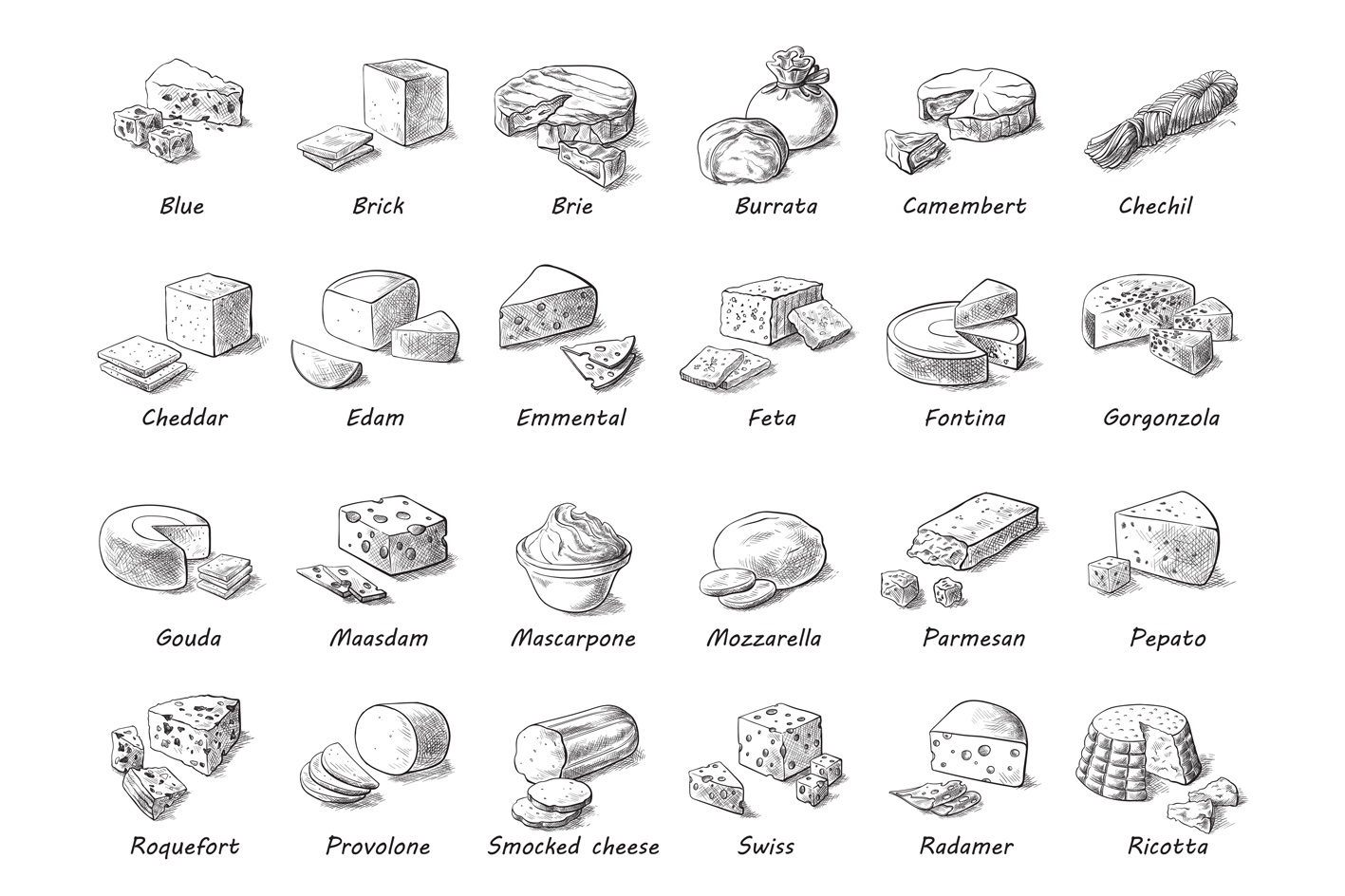
<参考サイト>
・チーズの種類
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/know/lovable-milk/cheese/
・チーズの種類
https://www.qbb.co.jp/enjoy/cheese/type/
・チーズの種類やタイプを分類!歴史から製造方法、食べ方までプロが解説
https://macaro-ni.jp/108364
④ 地理的表示(GI)で保護されるEU産チーズとは?
チーズはヨーロッパで多く生産・消費されており、EUでの年間生産量は1000万トン以上にも上り、その9割以上がEU域内で消費されています。
今後の販路としてEU域外での市場拡大を目指す中で、地理的表示(GI)制度で保護されるものがEU産チーズ全体の約1割あるとのことです。
GI制度は、地域特有の伝統的生産方法や生産地の自然的な要因によって、他にはない特性、高い品質、評価を獲得しているものについて、地理的表示(知的財産)を保護し、生産者と消費者の利益を守るものです。
EUと日本は、地理的表示を相互に保護しています。
例えばEUのチーズの地理的表示は日本でも保護されていて、次のような場合は規制の対象となります。
【ゴーダ・ホラント】
オランダ産でない非GIゴーダチーズにオランダの国旗等を付け、消費者に「ゴーダ・ホラント」と誤認させるような表示を行うこと。
【ゴルゴンゾーラ】
「○○県産ゴルゴンゾーラ」真正の産地を記載している場合であっても✕
「ゴルゴンゾーラへのオマージュを込めた国産ブルーチーズ」~種、~タイプ、~スタイル等の表現を伴う場合であっても✕
こうした地理的表示の保護が及ばない場合もいくつかあるそうです。
【パルメザン】
「パルミジャーノ・レッジャーノ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、英語翻訳の「パルメザンチーズ」は粉チーズの代名詞として浸透しているため規制の対象から外されており、「パルメザン」や「パルメザンチーズ」は使用できるとのことです。
ただしイタリアの国旗とともに表示するなど誤認混同を生じる恐れのある表示は規制の対象となります。
【カマンベール】
「カマンベール・ド・ノルマンディ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、「カマンベール」は日本ではすでに一般的な名称となっているため、規制の対象外となっており使用可能だそうです。
ただし「ノルマンディ風カマンベール」のような誤認混同を生じるおそれのある表示は規制の対象となります。
【モッツァレラ】
「モッツァレッラ・ディ・ブファーラ・カンパーナ」は日本で保護されるEUの地理的表示ですが、「モッツァレッラ」は日本では一般的な名称と考えられるため、規制の対象外だそうです。

<参考サイト>
・【レポート】地理的表示(GI)で保護されたEU産の伝統的なチーズについて
https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_001169.html
・地理的表示の相互保護-パルメザンは使える?
https://tsujinoka.com/2024/05/23/%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%9A%84%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BF%9D%E8%AD%B7%EF%BC%8D%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%81%AF%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%9F/
⑤ 産地由来が多い!世界のチーズの名前
「1つの村に1つのチーズ」と言われるほど多くの種類のチーズがあるフランスでは、昔からの伝統的な製法でつくられているチーズを「AOP(EU統一の原産地名称保護)」チーズとして認定しています。
「チーズの教本2019」という本に載っているAOP指定のチーズ46種類のうち、チーズを産出する町や村の名前が付けられているものが31種類あるそうです。
いずれも大都市ではなく小さい村や地方名です。
世界のナチュラルチーズの名前の由来について、いくつか調べてみました。
【産地の村や地方の名前に由来するもの】
<フランス>
「カマンベール」「ロックフォール」「ブリー」「フルム・ダンベール」「ボフォール」「ブルー・デ・コース」「ブルー・ドーベルニュ」「リヴァロ」「ポン・レヴェック」「ブリ・ド・モー」「クロミエ」「マンステール」「クロタン・ド・シャヴィニョル」「ラングル」「エポワス」「モン・ドール」「アボンダンス」「マリボー」
<イタリア>
「パルミジャーノ・レッジャーノ」「タレッジョ」「ゴルゴンゾーラ」
<イギリス>
「チェダー」
<オランダ>
「エダム」「ゴーダ」
<スイス>
「グリュイエール」「エメンタール」
【製造方法に由来するもの】
「モッツァレラ」引きちぎるの意味。引きちぎって成形することから。
「クラッレ・リヨネ」リヨンの平手打ちの意味。打ちつけるようにつくることから。
「リコッタ」二度煮るの意味。モッツァレラ製造時に出た乳清を加熱して固めることから。

※写真はPhoto ACより「モッツァレラチーズ トマト バジリコ」
【形状に由来するもの】
「クロシェット」鈴の意味。
「ボントン」樽の栓の意味。
「テート・ドゥ・モアン」修道士の頭形の意味。
「プロボローネ」ボール形の意味。
「テティージャ」小さな胸の意味。
「バラカ」馬蹄形の意味。
「カチョカヴァッロ」馬のチーズの意味。葦の葉でくくり、長い棒に吊るして熟成させる様子が、馬にまたがった姿に似ていることから。

※写真はPhoto ACより「カチョカヴァッロ」
【色に由来するもの】
「ダナブルー」青カビを使ったブルーチーズ。
「ババリアブルー」青カビを使ったブルーチーズ。
「フロマージュ・ブラン」フレッシュタイプの真っ白なチーズ。

【人名に由来するもの】
「サン・ネクテール」サン・ネクテール元帥がルイ14世にこのチーズを献上したと言われている。

※写真はAdobe Stockより「サン・ネクテール」
【料理名にもなっているもの】
「ラクレット」フランス語で削るという意味の「ラクレ」が由来。
切り口をあたためトロリとなったところを削いで食べるスイス料理の名前。

<参考サイト>
・チーズの名前を知れば産地が分かる
https://www.cheese-professional.com/article/column/detail.php?KIJI_ID=1475
・チーズで世界旅行
https://www.meg-snow.com/cheeseclub/knowledge/world_journey/
・乳と乳製品のQ&A
https://nyukyou.jp/dairyqa/2107_190_416/
⑥ 日本のチーズ「蘇」とは?「醍醐」もチーズ?
日本に飛鳥時代に伝わった、チーズの原型とされる「蘇」は、時を超えて2020年にSNSでそのレシピが話題になりました。
古代の法典である「延喜式(えんぎしき)」によると、牛乳をごく弱火で焦げないように8時間ほど煮詰め、元の10分の1くらいの容量になるまで水分を飛ばし、木型に流し込んで冷やし固形状にするそうです。
蘇は貴族や官人などしか食べられない高級食材でした。
聖徳太子が食べていたという説もあります。
美容や健康に良いとされ、平安時代には藤原道長が51歳で大病を患った際、蘇に蜜をかけた「蘇蜜煎」を食したそうです。
また、太政大臣の位についた時の宴で、甘栗と組み合わせた「蘇甘栗」を宮中より賜ったとのことです。
「蘇」は「酥」とも書かれ、「涅槃経(ねはんきょう)」という仏教の経典には「乳より酪(らく)、酪より酥(そ)、酥より醍醐(だいご)をつくる。醍醐は最上の美味」と記されています。
中国の本草書に「醍醐は酥の精なり」という言葉もあり、「蘇」をさらに煮詰めてつくった「醍醐」は最上級の物を意味し、「醍醐味」という言葉の語源であるとされています。
「醍醐」はチーズかバターオイルのようなものと考えられています。

※写真はPhoto ACより「蘇を作っている」
<参考サイト>
・古代日本人も味わった「醍醐味」 チーズの歴史を探る
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30615860X10C18A5000000/
・古代チーズ「蘇」
http://nara-shokubunka.jp/yamato/19-04.html
・SNSでよみがえる古代チーズ「蘇」って何?60分で作る簡単レシピ
https://macaro-ni.jp/87575
・農林水産省 蘇(そ)
https://traditional-foods.maff.go.jp/menu/so
・藤原道長も愛した古代チーズ「蘇(そ)」
https://torori.jp/cheese-trivia-so/
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》小豆島のカレーうどんといったらコレ? 編
冬にご好評をいただく「手延べ半生うどん」、その夏用として販売を開始した「手延べ乾平(かんぴら)うどん」。
「乾平うどん」は、夏にも調理しやすいように茹で時間を短くした平らな麺が特長です。
でも、「ただ平たい麺」にしたわけではありません。
折角なら、夏に美味しいうどんメニューに何かないかと、身近な方々に好みなどをお聴きしたところ、「夏はカレー」をよく食べるという声があり、そのひとつのメニューとしてカレーうどんを食べることが多いと伺いました。
そこで、平たくした麺を、今度はカレーうどんとして美味しく食べられるようにするには?と色々試した結果、平麺の厚みや幅、麺の長さなども試行錯誤して、ようやく完成したのが「乾平うどん」です。
折角できた「カレーうどんにピッタリなうどん」ですから、今度はこれを使って小豆島らしさを加えてみようと行き着いたのが今回の「小豆島カレーうどん」セットです。
人気の高い宝食品様の「オリーブ牛ビーフカレー」のレトルトパックカレーを活かして、丸島醤油様の「味醤油」をベースのだしに使うことで、カレーうどんにピッタリなカレースープを作ることができます。
できたカレースープをゆでたての「乾平うどん」に掛ければ小豆島のカレーうどんのできあがりです!
暑くて食欲の落ちる夏でも、スパイスの利いたカレーうどんを食べて元気にお過ごしいただければと考えています。
今回のテーマの「チーズ」をトッピングして召し上がっていただいても濃厚さが増して美味しいと思います!

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/
《小豆島カレーうどんセット》 https://141seimen.thebase.in/items/87804234
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.39
栄養成分の機能性について/微量ミネラル
このブログを書いている週末、快晴だった七夕から約1週間過ぎても梅雨の明けきらない小豆島といった感じです。
製麺時、空気が乾燥しすぎるのも難しいのですが、やはり湿気が多いのは手延べ製法にとっては大敵です。
夏場も製造する石井製麺所では、湿気の多いこの時期は空をにらみながらの製造が続きます。
現在は、製造の合間を縫って出荷(いえ、出荷の合間を縫って製造)する毎日です。
さて今回は、以前に書いたブログ「多量ミネラル」の続きで、「微量ミネラル」についてです。
鉄分について調べていると「ヘム鉄」「非ヘム鉄」があるとのこと。
そういえば、小学生の頃、貧血気味で鉄分のタブレットをよく食べて(飲んで)いたことを思い出しました。
当然、子どもの頃には詳しいことは知らず、母親(病院の先生)から渡されるタブレットを摂っていました。
病気や体質など、どうしても生まれ持ったものがありますが、コラムのネタを調べながらブログを書いていると、新製品のための知識やネタだけでなく、食べ物の大切さや栄養のこと、自分や家族の体調管理にも活かせそうです。
例年のこの時期は、こまめな水分補給も心掛けてはいるのですが、暑さからか調子を崩してしまうことも多く、スムーズな製麺のためには体調管理が大切だと思い知らされます。
まあ、無理して製造している間は「健康的」とはいえないかも知れませんが、せめて夏場の食事には気をつけたいものです。
現在は、製麺現場の見直しを図りつつ、より美味しく、より効率的に製麺できるように取り組んでいるところです。
色々と見直したい点もあり、取り組み始めたばかりですが、これからも家族で健康的に“健康によりそう麺”をつくり続けたいと思います。
今回も最後までお付き合いただけましたら幸いです。
写真は「素麵の日」でもある七夕の小豆島での青空です。
梅雨、早く明けて欲しいですね。

【目次】
① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?
② 「微量ミネラル」それぞれの働きについて
③ 必須ミネラル以外の、体に必要なミネラル
④ 人体を構成する元素について
⑤ 日本人と欧米人の必要なミネラルの違い
⑥ 薬膳の解釈を裏付けるミネラルの存在
⑦ 《美味しい素麵》手延べきくらげ麺 編
① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?
ミネラルは、身体にとって重要な役割を担っている五大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)の1つで、身体にごく微量に存在しています。
「無機質」とも呼ばれます。
人体の約95%は主要4元素(酸素、炭素、水素、窒素)で構成されており、残りの約5%はミネラルで構成されているそうです。
「ミネラル」という言葉は、英語で鉱山・鉱石を意味する「mine」に由来しているとされます。
ミネラルに関する発見は、18世紀頃、血液に鉄が含有されていることや、骨がカルシウムやリンから構成されていることがわかってきたことに始まったそうで、20世紀には、甲状腺腫がヨウ素の欠乏で起こることが解明されるなど、多くのミネラルの欠乏症が発見され、その生理作用や食品含有量がわかってきたそうです。
ミネラルは自然界に100種類以上存在しており、その中でも体内でさまざまな働きをする栄養素で通常の食事からでは不足しがちなものを「必須ミネラル」と言います。
現在、必須ミネラルは16種類とされ、このうち13種類について厚生労働省が摂取基準を定めています。
ミネラルは体内で合成できないため食物として摂る必要があります。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、
◎1日の推奨量や目安量が約100mg以上のミネラルを「多量ミネラル」
種類:ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン
◎1日の推奨量や目安量が100mg未満のミネラルを「微量ミネラル」
種類:鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン
と分類しています。
ミネラルが不足すると欠乏症やさまざまな不調が発生しますが、摂りすぎた場合にも過剰症や中毒を起こすものがあります。

<参考サイト>
・身体の調整に欠かせない栄養素~ミネラル~
https://www.mpc-lab.com/blog/20200619#:~:text=%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%86%E3%81%88%E3%81%A7%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%AC%A0%E3%81%AA%E8%BA%AB%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%80%82&te
・e-ヘルスネット ミネラル
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-035.html
・ミネラルの種類とそれぞれの働きを解説!ミネラルを含む食べ物も紹介
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=249&category=health#:~:text=%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%92%E3%83%88%E3%81%AE,%E3%81%AB%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%81%A7%E
・ミネラルとはどのような栄養素?種類別の働きについて解説
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/6010/
・ミネラル類
https://himitsu.wakasa.jp/contents/minerals/
② 「微量ミネラル」それぞれの働きについて
8つの「微量ミネラル」それぞれの働きや過不足による影響について、調べてみました。
【鉄】
ヘモグロビンや酵素の構成成分で、酸素と結合して全身に運ぶ役割を担っており、身体の成長、細胞の機能、一部のホルモンの合成に必要とされています。
女性に不足しがちな成分で、貧血の中で一番多いのが鉄欠乏性貧血です。
不足すると無力感や食欲不振などを引き起こすことがあります。
鉄は、体内への吸収率が高く動物性食品のレバーや肉、魚類に多く含まれる「ヘム鉄」と、卵や植物性食品(野菜や海藻類)に多く含まれる「非ヘム鉄」の2種類に分けられます。
非ヘム鉄はビタミンCやタンパク質を多く含む動物性食品と組み合わせることで吸収率がアップすると言われています。
健康な人が通常の食事で過剰症となる心配はまずありません。

【亜鉛】
肝臓、膵臓、骨、前立腺などに存在します。
発育や成長を助けたり、インスリンを合成したりするのに不可欠で、皮膚代謝や糖代謝、免疫にも関わる成分です。
欠乏すると味覚障害や皮膚炎、食欲不振、免疫機能の低下などを引き起こすことがあります。
牡蠣に豊富に含まれているほか、肉類や魚介類、豆類、種実類、穀物、味噌にも多く含まれます。
栄養バランスのとれた食事をしていれば不足しにくいとされています。
過剰摂取すると、胃の障害や免疫障害、神経症状が出ることがあるほか、銅や鉄の吸収を妨げることがあります。
【銅】
成人の生体内に存在する中で約50%が筋肉や骨、約10%が肝臓に分布しています。
エネルギーの生産や鉄の代謝、コラーゲン、エラスチンの成熟、神経伝達物質の生産、活性酸素の除去などの働きをしています。
鉄の吸収や貯蔵の際に働くほか、骨髄でヘモグロビンを産生するのにも関わっています。
欠乏すると貧血や成長障害などが起こることがありますが、通常の食事をしていれば不足することはないとされています。
銅の欠乏症には先天的なものと後天的なものがあります。後天的なものには、鉄投与に反応しない貧血、白血球減少、好中球減少、骨異常、成長障害、神経系の異常、コレステロール・糖代謝の異常などがあります。
過剰摂取による悪影響についてはほとんど報告されていないとのことです。
銅は、亜鉛と同様に牡蠣に多く含まれ、他の食品ではイカやエビ、貝類、牛レバー、ナッツ類、きなこに多く含まれています。

【マンガン】
体内では多くの酵素の構成成分として、抗酸化や糖質・脂質・タンパク質の代謝に関わっており、酵素の働きをサポートするのに欠かせない成分です。
また、骨の石灰化を促す働きがあり、カルシウム、リンとともに骨の形成に関わっています。
その他、耐糖能、生殖能、脂質代謝、成長および脳機能への関与が報告されています。
一般的な食生活をしていれば不足や過剰摂取はあまりないそうです。
吸収量は鉄の影響を受け、鉄が少ないと増加すると言われています。
マンガンが不足すると、骨代謝、糖脂質代謝、運動機能、皮膚代謝に影響が及ぶと考えられています。
マンガンを多く含む食品は、あおのり、きくらげ、生姜、干しエビ、アーモンドなどです。

※写真はPhotoACより「有明海の海苔養殖」
【ヨウ素】
甲状腺ホルモンの構成成分で、細胞の新陳代謝や成長促進を担っています。
日本人の食生活では、海藻類などヨウ素が含まれている食品を取る機会が多くあります。
そのため、海藻などを過剰に食べ続けた場合などに、甲状腺機能低下などのリスクがあるとされています。
またヨウ素が欠乏しても甲状腺機能低下が起こるほか、妊娠中に欠乏すると、死産や流産、胎児の先天異常などを招く恐れがあります。

【セレン】
強い抗酸化作用をもつ酵素の構成成分で、抗酸化システムに重要な役割を担っており、生活習慣病の引き金になる活性酸素の発生を抑制し、細胞 組織の酸化や老化を防ぐ働きがあります。
また、血圧をコントロールする「プロスタグランジン」の生成に関与し、カドミウム、水銀、ヒ素などの有害重金属の毒性を軽減する働き、精子の形態維持などの作用もあります。
海藻類や魚介類、肉類、卵黄に豊富に含まれており、体内に吸収されやすいため、通常の食事で欠乏する可能性は低いと考えられています。
土壌に含まれるセレンの量が低い地域では、克山病という心筋症やカシン・ベック症という関節症の一種などが見られ、セレン欠乏の関与が疑われています。
過剰摂取すると、脱毛や爪の変形、胃腸障害、神経障害、心筋梗塞などのリスクがあるとされています。

【クロム】
肝臓、腎臓、血液、脾臓に存在し、正常な糖代謝、脂質代謝を維持するのに重要な成分で、インスリンの働きを活性化したり、血中コレステロール値を下げ、中性脂肪を正常に保ったりする働きがあるとされていますが、加齢とともに減少してしまいます。
食品に幅広く含まれており、通常の食事で不足することはまれですが、加工食品を多く食べる人には不足する可能性もあります。
吸収率が低く、過剰摂取が問題となることはあまりないそうです。
干しひじき、わかめ、まいわし、あさりなどの水産物に多く含まれています。

【モリブデン】
いくつかの酵素の構成成分です。
糖や脂質の代謝などに関わるほか、体内で尿酸を作り出すために必要な酵素の働きを助けるとされています。
穀類や豆類、種実類に豊富に含まれており、一般的な食事をしていれば、欠乏や過剰摂取はほとんど見られないとのことです。

<参考サイト>
・私たちの体を守る「微量ミネラル」の重要性
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/life/172.html
・微量ミネラル
https://www.tanaka-cl.or.jp/aging-topics/topics-041/
・ミネラルの種類とそれぞれの働きを解説!ミネラルを含む食べ物も紹介
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=249&category=health
・ミネラル(無機物)とは何?体内での役割や摂取しやすい食材の選び方
https://www.house-direct.jp/column/about-mineral01/
・ミネラルについての解説
https://hfnet.nibiohn.go.jp/mineral/
③ 必須ミネラル以外の、体に必要なミネラル
厚生労働省が摂取基準を定めている13種類の必須ミネラル以外にも、体に必要なことが明らかになっているミネラルが4種類あるそうです。
それらはタンパク質やビタミンなど他の栄養素に含まれており、それらと同時に摂取できるため、個別の摂取基準が定められていないとのことです。
【硫黄】
タンパク質に含まれており、皮膚、髪、爪を形成する働きがあります。
また、ビタミンB群とともに糖質・脂質の代謝に働きかけ、有害ミネラルの蓄積を防ぐなど重要な働きをしています。
肉、魚、卵、アブラナ科の野菜、ネギ類に多く含まれます。
ニンニク、玉ねぎ、ニラなどの臭いは硫黄の成分によるものです。
通常の食事をしていれば不足することはありません。

【コバルト】
ビタミンB12の構成成分で、赤血球の色素生成など、造血の働きがあり、悪性貧血の予防に役立ちます。
また、神経の機能を正常に保つビタミンB12の働きを助け、集中力を高めたり記憶力を維持したりするのに役立つとされています。
肉やレバー、魚介類、乳製品など、ビタミンB12を含む食品に含まれています。
動物性食品に多く含まれるため、菜食主義者に不足しがちと言われています。
不足すると、貧血や食欲不振、消化不良、手足のしびれなどの症状が現れることがあります。

【フッ素】
虫歯の予防などに効果があるとされ、歯の治療や歯磨き粉などにも使用されています。
歯の再石灰化を促進する効果が期待され、エナメル質を強くして、虫歯菌が作る酸によるダメージから歯を守る役割を担っています。
同時にたくさん摂取することで、歯に縞模様が出るフッ素症になる危険性が指摘されています。
海外では摂取基準が示されることもあります。
抹茶やいわし、さんまなどの魚介類に含まれています。

【塩素】
胃酸の成分として消化の過程で働くほか、体液の浸透圧維持に重要な役割を果たしています。
殺菌効果や消化を促進する効果、膵液の分泌を促進する効果などがあるとされています。
体内では主に塩化物イオンの形で存在しています。
食塩から摂取できるため、不足することはほとんどありません。
塩素は漂白剤として使用されており、酸性洗剤と混ぜると塩素ガスが発生し、これを直接吸入すると呼吸器に損傷を与えるため、取り扱いには注意が必要です。

<参考サイト>
・硫黄
https://www.sapurinojikan.com/contents/component/4941/#:~:text=%E7%A1%AB%E9%BB%84%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C,%E3%81%AE%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%80%81%E3%83%8D%E3%82%AE%E9%A1%9E%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
・コバルト
https://himitsu.wakasa.jp/contents/cobalt/#:~:text=%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E7%A8%AE,%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%88%90%E5%88%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
・フッ素
https://himitsu.wakasa.jp/contents/fluorine/
・塩素
https://himitsu.wakasa.jp/contents/chlorine/#:~:text=%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%AE,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
④ 人体を構成する元素について
前述したように、人体の約95%は主要4元素(酸素、炭素、水素、窒素)で構成されています。
これらは糖質、脂質、タンパク質、核酸といった主要な有機化合物を構成する元素です。
残りの約5%を占めるのがミネラル(無機質)です。
体内でのミネラルの働きは、大きく3つに分けられます。
【①身体の構成材料として働く】
骨、歯などの身体の構成成分になる:カルシウム、リン、マグネシウム
有機化合物と結合する:鉄、リン
【②生体機能の調整を行う】
体液に溶けてph・浸透圧を調整する、神経・筋肉の興奮性の調整をする:カリウム、ナトリウム、カルシウム、リン、マグネシウム
【③タンパク質などと結合して働く】
酵素の構成成分となる:マグネシウム、鉄、銅、亜鉛、マンガン、セレン
生理活性物質の構成成分となる:鉄、ヨウ素、亜鉛、モリブデン

<参考サイト>
・無機質
https://idenwatch.com/seikagaku9-2/
⑤ 日本人と欧米人の必要なミネラルの違い
日本人と欧米人は、古くからの食習慣から生まれた、胃腸の形状、腸内環境や消化酵素などの違いから、消化できる栄養素などにも違いがあるそうです。
狩猟民族を先祖に持つ欧米人は、タンパク質や脂質が多く含まれる動物性食品を好んで食べてきました。
それらを消化・吸収するため胃酸分泌が比較的旺盛で、タンパク質を分解する際に作られる有害物質を早く体外に排出するために腸が短いと考えられています。
日本人は、稲などの穀類が良く育つ気候のもと米を主食とし、また肉食禁止の影響もあり、繊維質が豊富な食品を多く食べてきました。
このため胃が比較的繊細で、繊維質の多い食物を吸収するため腸は長い構造となっています。

日本と海外で必要とされる栄養素の違いについて、ミネラルに注目して調べてみました。
ミネラルという言葉を身近にしたものに「ミネラルウォーター」があると思います。
日本の水と海外の水は、ミネラルの含有量が違うという話を聞かれたことがあるのではないでしょうか。
日本の水道水やミネラルウォーターはほとんどが「軟水」で、海外の水は主に「硬水」です。
水1リットル当たりのカルシウムとマグネシウムの含有量を表す指標を「硬度」といい、硬度が60mg/L以下のものは軟水、120~180mg/Lの物は硬水に分類されるそうです。
海外では、ミネラル成分を含んだ石灰岩地層が多いため硬水が多いそうです。
日本の地形は傾斜が急で河川も短いため、水は地層に含まれるミネラル成分を含まないまま海やダムに流れてしまいます。
また雨が多いことから地中にある水が押し出されてしまい、血中での滞留時間が短いため、ミネラル成分豊富な硬水が少ないとのことです。
日本人の多くは軟水を飲みなれているため、硬水は独特の口当たりで飲みにくいと感じたり、体質に合わずおなかの調子が悪くなったりする人もいるようです。
ミネラルウォーターには、ミネラルの含有量に基準が設けられているわけではありません。
製品によって違いがあり、海外メーカーの硬水のミネラルウォーターが売られている場合もあるので、購入する際には種類やミネラル含有量をチェックすると良いようです。

日本人は、世界一ヨウ素を多く摂取している民族だそうです。
その理由は、海藻類を習慣的に食べているからとのこと。
「海藻は日本人にしか消化できない」という話がありますが、これは生の海苔に限ってのことだそうです。
生の海苔に含まれるポルフィラン多糖という成分を分解する消化酵素が日本人の腸内にしかないという調査報告があるそうですが、加熱すればポルフィラン多糖は壊れてしまうとのことです。
中国や韓国、東南アジアなどでは、日本と同様、海藻を日常的に食べています。
また近年、海藻はヘルシーフードとして欧米で注目の食材となっています。

<参考サイト>
・vol.04 日本人の胃、欧米人の胃【専門医が解説する胃に関する疑問】
https://www.eisai.jp/articles/stomach_mechanism/specialist_explains08
・日本に硬水が少ない理由とは?飲む際の注意点も解説
https://www.aquaclara.co.jp/lifehack/water/023/
・ミネラルウォーターとは?種類や成分など気になる5つの疑問を解決!
https://www.nihon-trim.co.jp/media/1253/#%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F
・海藻類は海外でも食べられている!注目度が高まる新たな食材の波とは
https://www.table-source.jp/column/seaweed-outside-japan/
・日本人の体の秘密 外国人は海苔が食べられないって本当?
https://world-conect.com/seaweed_foreigner_japan
⑥ 薬膳の解釈を裏付けるミネラルの存在
「薬膳」という言葉を耳にしたことはありませんか?
薬膳とは、中国の伝統医学の考えに基づいた食事のことで、体質や体調に合わせて食材を取り入れることで健康を整えるものです。
すべての食材には効能があり、現代栄養学における三大栄養素やミネラル、ビタミンなどの効能とは異なる観点で説かれています。
例えば、キクラゲは薬膳において不老長寿の妙薬として珍重されてきたそうです。
ミネラルが豊富で、乾燥キクラゲ100g中にカリウム1000mg、カルシウム310mg、マグネシウム210mg、鉄35.2mgが含まれます。
またカルシウムの吸収を促進するビタミンDが85.4μg含まれる、機能性の高い食材です。
中医学での位置づけは、食味は「甘」、食性は「平」です。
血液のめぐりをスムーズにし、疲れやすさや顔色の悪さを改善するほか、血液を浄化する効果が期待でき、がんや動脈硬化の予防に役立つとされます。
また体を潤す働きがあるので、空咳、口の乾き、乾燥肌にも有効とのことです。
今では当たり前のように三大栄養素やミネラル、ビタミンなどの考え方がありますが、そういった考えが発見される前から食に対しての探求がされていたことは本当に驚きです。
さらに、薬膳で重要視(良いとされる)される食物は現代科学をもってしても、とても有用なことが分かっているそうです。
このキクラゲのように、古くから食され、珍重されてきた食材を扱う際には現代科学と薬膳という切口で深掘りすることで、その有用性を活かせそうな気がします。
石井製麺所では、食材単体に着目するのでなく、科学的な視点、薬膳的な考えを取り入れた手延べ麺開発をおこなっていきたいと考えています。

<参考サイト>
・薬膳とは?基本の考え方や体質別のおすすめ食材をわかりやすく紹介
https://www.u-can.co.jp/%E8%96%AC%E8%86%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/column/column01.html
・薬膳とは
https://miyabi.shishin-kyoto.com/yakuzen/
・日本型薬膳を知ろう〈食材図鑑〉不老長寿の妙薬。カリウムが塩分を調整。〔きくらげ〕
https://www.saibugas.co.jp/home/and/articles/detail.php?id=83
・黒きくらげ
https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/yakuzen/ingredients/kurokikurage.html
・ 薬膳食材辞典 黒きくらげ
https://www.kampo-sodan.com/yakuzen/yakuzen-2443
⑦ 《美味しい素麵》手延べきくらげ麺 編
讃岐うどんが有名な香川県ですが、「うどん県。それだけじゃない香川県」と題して、魅力あふれる県産品の開発と掘り起こしにも力を入れています。
毎年、夏に開催される『県産品コンクール』には、香川県産の原材料にこだわった食品やスイーツ、歴史や所縁(ゆかり)を大切にした香川らしいお菓子や工芸品、最近ではオリーブ部門も設けられ、会場には事業者さんの創意工夫と想いの詰まった商品がたくさん集まります。
私たち石井製麺所も、昨年で3回目の参加となりました。
出品した『瀬戸凪《楽々膳・黒》』は、冬に食べるとよいとされる「黒の食材(ひじき・きくらげ・黒ごま)」を練り込んだ特製麺のセットです。
審査員への訴求の仕方や試食の提供時に、「きちんとお客様への説明が足りているか?」など気付きも多くあります。
そして、昨年は7票中の2票の得票をいただけたようです。
いつか最優秀賞を獲得して、お客様にご報告できる日を楽しみに、チャレンジを続けます!
昨年の出品の様子ですが、出品した「手延べきくらげ麺」は、細麺のためか夏でも人気のある手延べ麺なんですよ。
独特の食感で、冷やして食べても温かいお出汁で食べても美味しく召し上がっていただける自慢の手延べ麺です。
一度、ぜひお試しください!
《小豆島手延べきくらげ麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195855
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.38
麺究者への道/日本酒について研究してみる
今回のブログでは、日本の食文化において「発酵」「熟成」には欠かせない、日本酒について調べてみました。
お酒はたしなむ程度にしか飲めませんが、お酒の場の雰囲気は好きで、お声がけいただければ参加します(笑)。
量を飲めるわけではありませんので、質にこだわりたいところですが、日本酒の種類や違いについてはほとんど分かっていません。
そんな私が日本酒のことについて記してみます。
色々調べていて驚きだったのは、日本での歴史的な背景での扱いや拡がり方などは、素麺も日本酒も同じようなプロセスを経てきたんだなと言う点でした。
少し違うのは、お酒は「税金」の対象であり、国(税務署)が厳しく監督するもので、素麺はそこまではないという所でしょうか。
それにしても酒蔵さんの数の多いこと!
さすがに小豆島の酒蔵さんは1つだけで、製麺所の方が多いですが、日本全国には1,000以上の酒蔵さんがあり、それだけ多くの方に必要とされてきたんだと分かります。
酒蔵さんの中には、とても参考にさせていただきたいビジネスモデルのお会社様があったり、季節に合わせた楽しみ方や呼び名があるのはステキだなと思いました。
日本酒と素麺の接点などもあったりして、素麺でももっともっとできることがありそうで、ブログを書いている時間は興味の尽きないひとときでした。
というわけで、かなり片寄った情報になる(?)かも知れませんがお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

【目次】
① 進化を続ける日本酒、その起源は稲作とともに始まった
② 日本酒の定義・清酒との違いとは?
③ 原料、精米歩合、製法、香味などから分類される日本酒の種類
④ 地酒の定義と、産地ごとの特徴
⑤ 日本酒の製法、その特徴は「並行複発酵」
⑥ 風味や香りの決め手!酵母の種類
⑦ 伝統製法を守りつつ数値管理で生産を拡大した「獺祭」
⑧ 《石井製麺所の取り組み》OEM手延べ麺 編
① 進化を続ける日本酒、その起源は稲作とともに始まった
日本酒の起源は今から2000年以上も前の弥生時代、稲作伝来とともに始まったと考えられています。
古代の酒は、もろみを濾さない「どぶろく」のようなものだったそうです。
生米を口に含んで噛み、唾液中の酵素を利用して米のデンプンを糖に分解し、それを容器に吐き出して空気中の自然酵母で発酵させるというもので、「口噛み酒」と呼ばれました。
口噛み酒づくりは神社の巫女が行い、神様に捧げられていたそうです。
西暦250年頃の書物「魏志倭人伝」には、倭国の酒の記載があるとのことです。
奈良時代には米こうじを用いて米を糖化させ発酵させる方法が生まれ、これが現在の酒づくりのルーツとされています。
西暦400年頃の「播磨国風土記(はりまのくにふどき)」で、初めて「清酒(すみさけ)」の記述が登場しています。
神事や一部の上流階級への贈答品などには透き通ったお酒が使用されていたと考えられています。
日本最古の歌集「万葉集」 には「酒屋(さかや)」という言葉が使われている和歌があるそうです。
平安時代には、宮中に「造酒司(みきのつかさ)」という役所が設けられ、朝廷の行事のためにお酒がつくられていました。
鎌倉時代には、寺院で僧侶たちがつくる「僧坊酒(そうぼうしゅ)」と呼ばれる清酒が評価を集めました。
神事など特別な行事の時にだけふるまわれていたお酒が、徐々に庶民にも広まるようになりました。
室町時代に奈良県の菩提山正暦寺で確立された「菩提酛(ぼだいもと)」は、日本最古の酒母づくりの手法と言われ、この地が酒づくり発祥の地とされる所以となっています。
その特徴は、乳酸発酵によりできる「そやし水」と呼ばれる酸性水を使って酒母を育成するというものです。
雑菌がいなくなり酵母菌が活躍しやすい環境をつくることで、温暖な気候のもとでの酒づくりを可能にしたとのことです。
また室町時代には、商売としてお酒がつくられはじめ、京都の市中には小規模な「造り酒屋」が数百軒もできたそうです。
この頃には1年に5回酒づくりを行っており、量産化が可能になったとのことです。
江戸時代になると、「火入れ」による加熱殺菌方法や、安全に醪(もろみ)を発酵させる方法である「段仕込み」が一般化しました。
江戸時代中期頃までには、現在とほぼ同じつくり方が確立したとのことです。
一年中安定した品質が保てるようになると、酒づくりに最適な冬の時期に集中して酒をつくる「寒づくり」が始まって、農民が農閑期の出稼ぎで酒をつくる、「杜氏(とうじ)」「蔵人(くらびと)」が誕生しました。
杜氏は1つの酒蔵につき1人しかいない最高責任者で、蔵人は杜氏のもとで酒づくりを担う職人のことです。
伊丹や灘の酒が江戸で「下り酒」として評判を集め、日本酒の最大の生産地になったのも江戸時代のことです。
明治時代には、酒税の強化を図るため自家醸造酒の製造と自家消費が禁止され、「どぶろく」が衰退しました。
酒造技術の向上を目指し「国立醸造試験場」(現在の「独立行政法人酒類綜合研究所」)が設立され、「山廃酛(やまはいもと)」や「速醸酛(そくじょうもと)」の技術が開発されたそうです。
明治時代にはビールやワインなどが輸入されるようになり、それらと区別するため、「日本酒」という表現が使われるようになりました。
それ以前には「清酒」(澄み酒)や、単に「酒」と呼ばれていたとのことです。
それまで日本酒は一般的に木樽に詰められて輸送・販売されていましたが、1878年には瓶詰めの日本酒が登場し、1901年には一升瓶での販売も開始されたそうです。
一方、量り売りは第二次世界大戦後まで続きました。
大正時代になると、日本酒の仕込みや貯蔵にホーロー(琺瑯)タンクが使用されるようになりました。
ガラスの物質を金属の表側に焼き付けてつくるホーローは、これまで主に使用されてきた木桶(きおけ)に比べて「洗浄や殺菌の手間がかからない」「火入れ後の酒を冷却しやすく酒の過熱を防げる」などのメリットがありました。
ホーロータンクにより酒づくりが効率化されたと考えられます。
昭和時代、戦争などの影響で酒づくりは一時期低迷しましたが、戦後から高度経済成長を経て、日本酒の消費量は増加し、酒づくりにおける機械化も進みました。
1975年、酒造組合中央会により、市販の日本酒の製造年月日や原材料、製造方法などを表示する「清酒の表示に関する基準」が取りまとめられました。
当時、市販されていた「清酒」の約99%が糖類やアルコールを添加したものでしたが、公正取引委員会が行った消費者意識調査によると、清酒にアルコールが添加されていることを知っていた人は47%だったそうです。
清酒に関する苦情が多く寄せられるなど不当表示が問題になっていたことを背景につくられたこの基準によって、米と米こうじだけを主原料とする清酒と、糖類やアルコールを添加した酒類とが識別されるなど表示が適正化され、消費者が本格的な清酒を選んで購入できるようになり、清酒のイメージアップにもつながったようです。
1990年、「清酒の製法品質表示基準」が適用され、「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」といった特定名称を表示する場合の基準が定められました。ある一定の基準により分類されるこれらの清酒は「特定名称酒」と呼ばれ、それ以外の清酒は「普通酒」と呼ばれるようになりました。
この時期、生酒やにごり酒、スパークリング清酒なども増え始め、日本酒がさらに多様化するきっかけのひとつになったと考えられます。
近年、日本酒は海外からの人気が高まっており、2021年には輸出金額が1000億円を超えたそうです。
「SAKE」という呼び名で、日本を代表するお酒として広く知られるようになってきました。

<参考サイト>
・日本酒を知る
https://nihonshu-tourism.com/about-nihonshu
・日本酒を知る 日本酒の歴史
https://japansake.or.jp/sake/about-sake/history-of-sake/
・日本酒の起源はいつ?日本酒文化の歴史と変遷を紐解いてみよう
https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/history-of-nihonshu/#SAKE
・日本酒(SAKE)の歴史~起源や日本文化との関わりを紹介
https://www.wa-mare.com/column/115/
・清酒の表示について
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jbrewsocjapan1915/70/2/70_2_84/_pdf/-char/ja
・原点回帰の「新」製法? – 菩提酛(ぼだいもと)、水酛(みずもと)を学ぶ
https://sakestreet.com/ja/media/what-are-bodaimoto-and-mizumoto
② 日本酒の定義・清酒との違いとは?
「日本酒(清酒)」だけでなく、焼酎やビール、ワインなど酒税法においては、アルコール度数1%以上の飲料が「酒類」と定義されています。
さらに製法によって大きく「発泡性酒」「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の4種類に分けられ、清酒は「醸造酒」に分類されています。
酒税法における「清酒」の定義は、「米、米麹及び水を原料として発酵させて濾したもの(アルコール度数22度未満)」、あるいは「米、米麹、水及び清酒かすその他政令が定める物品を原料として発酵させて濾したもの(アルコール度数22度未満)」とされています。
清酒の製造過程において、「米、米麹及び水を原料として発酵させたもの」を「醪(もろみ)」と呼び、それを濾して清酒と酒粕に分けることで清酒がつくられます。
もろみを濾さないものは清酒ではなく「どぶろく」となります。
「日本酒」は、清酒の中でも、原料の米や米こうじに国内産米のみを使用し、日本国内で醸造したもののみを指します。
海外産の米を使用した清酒や、日本以外で製造された清酒は「日本酒」と表示することはできません。
2015年、「GI(Geographical Indication)」において、「日本酒」の呼称が国レベルの地理的表示として指定を受けました。
その背景に、日本酒は日本の明確な四季と結びつき発展してきた特別な飲料で、国民生活・文化に伝統的に深く根付いてきたことから、日本が長年育んできた日本酒の価値を保全していくため、という狙いがあるとのことです。
「日本酒」という呼称は、「清酒」の中の一部を表すブランドと言えます。
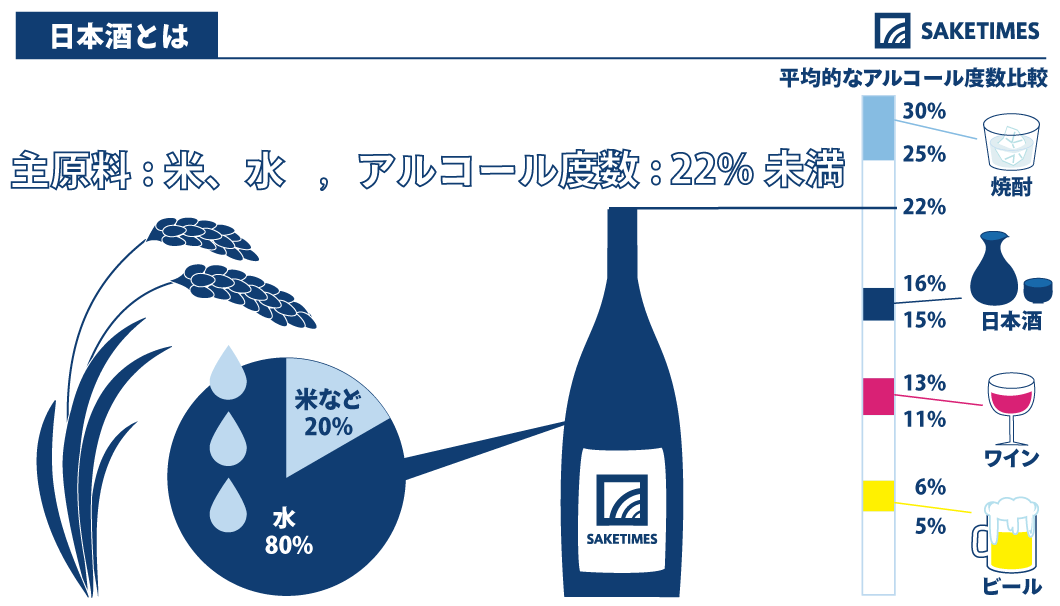
@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用
<参考サイト>
・日本酒と清酒の違いは?清酒の歴史や種類も解説
https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/know/299
・日本酒とは?清酒・日本酒の定義や種類・分類について解説
https://sakazuky.com/contents/commentary/nihonsyu/
③ 原料、精米歩合、製法、香味などから分類される日本酒の種類
清酒の中でも、原料や精米歩合など所定の要件を満たすものは「特定名称酒」と呼ばれ、大きく「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」の3つに分けられます。
精米歩合とは玄米を磨いた度合いを示すもので、残った米の比重の割合です。
米の表面近くに多く含まれるタンパク質や脂質は雑味となるので、米を磨けば磨くほど少量となり、その分高価になります。
特定名称酒に該当しない清酒は「普通酒」または「一般酒」などと呼ばれます。
特定名称酒は、さらに原料や製造方法の違いにより8種類に分類されます。
【吟醸酒】
低温でゆっくりと発酵させる「吟醸造り」が特徴。
その中でも、精米歩合60%以下のものは「吟醸酒」、さらに50%以下のものは「大吟醸酒」の2つに分類されます。
華やかでフルーティーな味わいが特徴で、その香りは「吟醸香」とも称されます。
【純米酒】
米・米こうじ・水のみを原料とし、製造過程で醸造アルコールを添加しない清酒。
米本来の旨味や甘味、まろやかなコクを強く感じられるのが特徴です。
精米歩合の要件がない「純米酒」と、精米歩合60%以下または特別な製造方法を要件とする「特別純米酒」に分類されます。
また、吟醸造りで製造された純米酒は「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」と呼ぶことができます。
【本醸造酒】
醸造アルコールが含まれている清酒。
精米歩合70%以下の「本醸造酒」と、60%以下の「特別本醸造酒」の2つに分類されます。
キリッと引き締まった味わいで、酸味や苦味が少ないのが特徴。
醸造アルコールとは、主にサトウキビを発酵させた純度の高いアルコールのことで、もろみに適量添加すると、より香り高くすっきりとした味わいになるそうです。
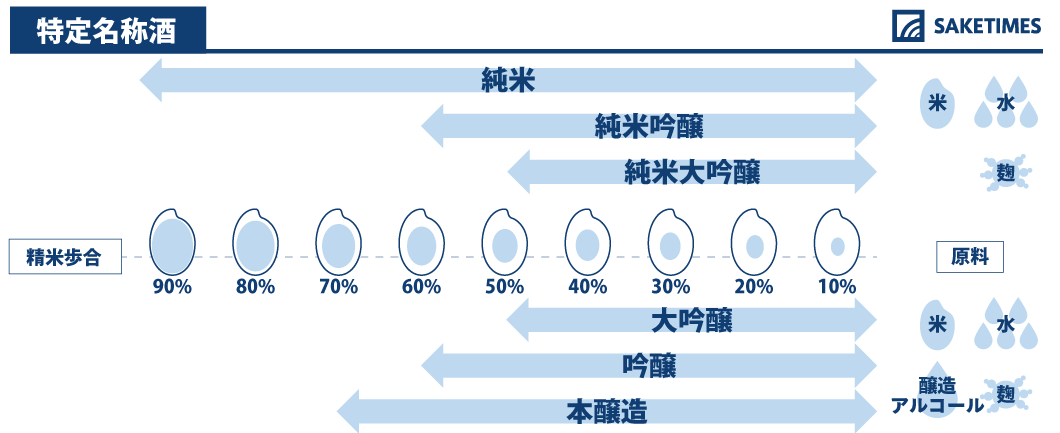
@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用
日本酒のラベルには、「生」と書かれたものがありますが、これは製造工程で行う「火入れ」という加熱殺菌のタイミングと回数の違いによるものです。
「火入れ(加熱処理)」は通常、貯蔵前と出荷前に行います。
「生酒(なまざけ)」は1度も火入れをせず、もろみを搾っただけの日本酒で、フレッシュな味わいです。
「生貯蔵酒」は出荷前に一度だけ火入れしているので、生の風味が残っています。
「生詰酒」は火入れを行ってから約半年ほど貯蔵・熟成したもので、「ひやおろし」「秋晴れ」「秋上がり」などとも呼ばれ、穏やかな香りやなめらかな口当たり、濃密な味わいが特徴です。
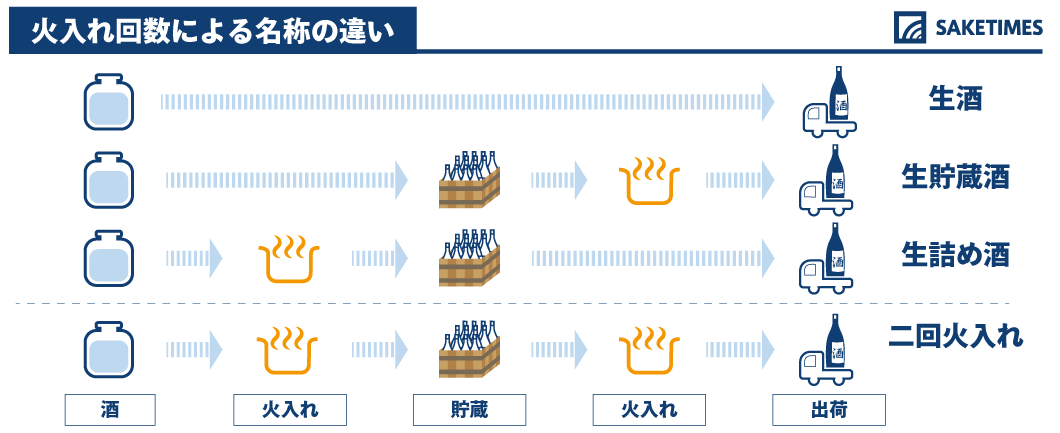
@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用
日本酒には他にもその特徴による種類があるので、いくつか調べてみました。
【生一本(きいっぽん)】
自社蔵の一つの製造場だけでつくられた純米酒。
【原酒】
一般の市販酒は、もろみを搾った後、水を加えてアルコール度数を調整します。
原酒は水を加えていないのでアルコール度数が18~20度と高く、濃醇な風味が特徴です。
【にごり酒】
もろみを目の粗い布で濾しただけの、白く濁っているお酒。
【滓酒(おりざけ)】
もろみを目の細かい布で濾したあと、タンクの底に沈殿した滓を含んだ、白く濁っているお酒。
【長期貯蔵酒】
日本酒は通常半年から1年熟成させますが、2年や3年、あるいは5年以上貯蔵させることで、甘い熟成香とまろやかな味わいとなったお酒です。
【樽酒】
樽で貯蔵し、木の香りを生かした酒。
樽の材料としては杉、特に吉野杉が重用されます。
【発泡酒】
炭酸ガスを含む、シャンパンのような口当たりのお酒。
アルコール度数は8 度ぐらいと低めです。
【貴醸酒】
仕込み水の一部または全部に酒を使ってつくる日本酒。
通常の日本酒に比べかなり糖度が高く、とろりと甘いのが特徴。
芳醇でコク深い味わいです。
手延べ素麺で言えば、「寒製」や「極細麺」「細麺」「中太麺」「太麺(ひやむぎ)」などの太さ違いや、「ばち」や「ふし」と言った副産物的な違いでしょうか。
また日本酒は、その香りや味わいにより4タイプに分けられることもあります。
【薫酒(くんしゅ)】
吟醸造りタイプの日本酒で、花のような香りと果実を思わせるフルーティな味わいが特徴。
よく冷やして飲むのがおすすめとのことです。
【熟酒(じゅくしゅ)】
熟成期間が長い古酒などで、とろりとまろやかな飲み口とスパイシーな香りが特徴。
【爽酒(そうしゅ)】
本醸造酒など、すっきりとした味わいで「辛口」とも言われる日本酒。
よく冷やして飲むのがおすすめだそうです。
【醇酒(じゅんしゅ)】
純米酒など、米本来のうまみや甘みが感じられる日本酒です。
常温で濃厚な味わいを楽しんだり、燗で芳醇な香りと甘さを楽しむのがおすすめとのこと。
手延べ素麺で言えば、「新物」や「古物(ひねもの)」などの違いでしょうか。

<参考サイト>
・日本酒にはどのような種類がある?日本酒の基本知識とあわせて解説!
https://haa.athuman.com/media/japanese/culture/1772/
・知っておきたい!日本酒の種類と違い
https://www.enoteca.co.jp/article/archives/20220722160356167/
・日本酒を知る 日本酒の分類
https://japansake.or.jp/sake/about-sake/classification-of-sake/
・リッチな甘みのデザート酒!「貴醸酒」の製法と味わいの特徴を学ぶ
https://sakestreet.com/ja/media/learn-kijoshu
④ 地酒の定義と、産地ごとの特徴
2021年現在、日本酒の蔵元数は1164場あります。
都道府県別では1位が新潟県、2位が長野県、3位が福島県。
生産量は1位が兵庫県、2位が京都府、3位が新潟県だそうです。
必ずしも、蔵元数と生産量は一致していないんですね。
日本酒の銘柄は1万以上あると言われています。
全国的に流通するメーカーの製品や日本酒の主生産地である兵庫県の灘や京都府の伏見以外でつくられる日本酒のことを、明確な定義が確立されているわけではありませんが一般的に「地酒」と言います。
江戸時代は、灘や伏見の酒が樽詰めされて全国に流通していました。
それ以外の地域でつくられた酒は「地酒」と呼ばれ、少し格の低いものとして扱われていたそうです。
地酒が全国的に認知されるようになったのは昭和の終わり頃で、地方への旅行が活発になり、地方の魅力が注目され、地酒などの特産品が脚光を浴びるようになりました。
各地域の蔵元がその土地の米や水でつくる地酒には、その土地の気候風土の影響を受け、それぞれに個性的な味わいがあります。
地域ごとの特徴を調べてみました。
【北海道】
寒冷な気候が酒づくりに適しています。
新鮮な海の幸と相性のよい淡麗辛口が特徴ですが、近年は濃厚で芳醇なお酒も人気があるそうです。
【東北】
日本有数の米どころで、酒造米の開発もさかん。
岩手県では、日本最大の杜氏集団である「南部杜氏」の技を受け継いだ製法で地酒がつくられており、米の旨みが凝縮された豊潤でコクのある味わいだそうです。
【関東】
他のエリアより蔵元は少ないながら、多くの水源や河川に恵まれており、高品質な日本酒がつくられています。
茨城・東京・千葉・神奈川は淡麗辛口、栃木・群馬・埼玉は淡麗甘口の傾向とのことです。
【中部】
米、気候、水といった条件が揃っている日本海側は、米どころ新潟を中心に、高級酒の生産量も多く、新鮮な魚介類に合う淡麗辛口が主流。
軽やかでなめらかな味わいを引き出す、ミネラル分の少ない軟水を使い、雪深い時期に仕込んでゆっくり発酵させます。
新潟は日本三大杜氏の1つ「越後杜氏」の発祥地としても有名です。
山間部である長野や山梨では、寒暖差と豊富な水を生かした酒づくりが行われています。
【近畿】
兵庫の灘、京都の伏見の二大産地や、酒づくり発祥の地とされる奈良を有するエリア。
兵庫県は「酒米の王様」と呼ばれる酒造好適米「山田錦」の産地でもあり、伊丹市・神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の5市の“「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷”は日本遺産に認定されています。
伊丹は、江戸時代に初めて濁りのない清酒「伊丹諸白(もろはく)」がつくられたことから清酒発祥の地とされています。
良質な米とミネラル豊富な水、高度な酒づくりの技術でつくられる伊丹の酒はとりわけ珍重され、江戸で人気を博したそうです。
また、西宮市の今津郷・西宮郷から神戸市東灘区の魚崎郷・御影郷・灘区西郷へと続く「灘五郷」は日本最大の清酒酒造地帯で、灘五郷の酒は国内シェアの約25%を占めています。
江戸時代、酒の需要が高まると、消費地への海運に利点を持つ沿岸部の灘で酒づくりがさかんになりました。
六甲山の伏流水が酒づくりに適しており、また冬に吹く六甲おろしを利用して蒸米を短時間で冷ませたことも、生産量を増やすのに役立ったそうです。
灘の酒は力強い味わいで、「おとこ酒」とも呼ばれる豊潤辛口が特徴です。
京都府伏見は、良質な伏流水に恵まれていることに加え交通の要所でもあったことから、古くから酒づくりがさかんで、現在も数多くの酒蔵が立ち並びます。伏見の酒はまろやかで口当たりが良く「おんな酒」と呼ばれる濃淳甘口です。
大手酒造メーカー以外にも有名な地酒をつくる蔵がたくさんあります。
【中国】
灘・伏見と並ぶ酒どころとされる広島県西条市では、温和な気候風土のもと、口当たりの柔らかな甘口でふくよかな香りと旨みが調和した味わいの高品質な酒づくりが行われています。味の濃い食べ物との相性が良いそうです。
山口県には、国内外で人気の「獺祭(だっさい)」の蔵元があります。
【四国】
四万十川・吉野川などの伏流水を利用した酒づくりが行われています。酒豪が多いとして知られる高知では辛口が好まれ、瀬戸内海側では、白身魚を中心とした淡白な食文化に合う、口当たりが良くやわらかな甘口が好まれるそうです。
【九州・沖縄】
日本酒よりも焼酎文化が根付く地域ですが、九州北部は冬場の気温が低く、酒づくりに適した気候です。
福岡は「山田錦」の有数な産地でもあり、豊かな水源を利用して高品質な酒づくりが行われています。
泡盛が有名な沖縄は熱帯気候で日本酒づくりは難しいと言われますが、日本酒の蔵元が1軒だけあるそうです。
 ※写真は、JR上越線 越後湯沢駅にある「ぽんしゅ館」の一部
※写真は、JR上越線 越後湯沢駅にある「ぽんしゅ館」の一部
<参考サイト>
・図解■ 日本酒の酒蔵数、国内売上、輸出額【都道府県別】
https://www.alcholog.com/?p=3254
・日本酒と地酒は何が違う? 地酒の定義やたのしみ方
https://tanoshiiosake.jp/8969
・地酒と日本酒ってどう違う? 地域ごとの特徴や楽しみ方も紹介
https://magazine.asahi-shuzo.co.jp/know/442
・日本酒の地域別の特徴を解説!地酒の楽しみ方もご紹介
https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/regional-characteristics/
・日本遺産ポータルサイト 「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story097/
・酒粕ピザや飲み比べも! 日本遺産認定 伊丹で日本酒文化を学び味わう旅。-兵庫テロワール旅-
https://www.hyogo-tourism.jp/review/253
・灘の酒【歴史・風土編】:日本酒生産量トップを独走する兵庫が誇る酒どころ
https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900138/
⑤ 日本酒の製法、その特徴は「並行複発酵」
「日本酒は冬につくられるもの」というイメージをお持ちの方も多いと思います。
1年で最も寒い12月から2月頃に酒をつくることを「寒づくり」と言います。
秋に収穫した米を使い、温度管理がしやすく菌が繁殖しにくいことから多くの酒蔵が寒づくりを行っています。
昔は、日本酒は年間を通じてつくられていました。
四季によって大きく変わる日本の気候に応じて、季節に応じた製造技術が編み出され、旧7月・8月につくられた「菩提酒」、旧7月から9月の「新酒」、旧10月頃の「間酒」、旧11月・12月の「寒前酒」、旧11月から1月末の「寒酒」、旧2月から3月の「春酒」といった名称も生まれたそうです。
江戸時代中頃になると貯蔵技術が進み、多くの酒蔵が、酒をつくりやすく質も安定しやすい冬季の醸造を採用しました。
冬場は農民の手が空き労働力が確保しやすいこと、1673年に米の凶作による酒造統制の一環として寒づくり以外の醸造が禁止されたことなどにより広まったと考えられています。
寒い冬につくられたものが美味しい、農閑期の副業としてつくられる、などの点は、素麺づくりに通じるものがあるように思います。
日本酒は、米や水といった原料を酵母によりアルコール発酵させてつくられます。
その工程はとても複雑なものです。
ビールやワインなど他の醸造酒との大きな違いは、もろみが糖をアルコールに変えるアルコール発酵と同時に、でんぷんを糖に分解する糖化が行われる「並行複発酵」で、これは高度な技術や経験、知識が必要とされる醸造法です。
酒づくりの工程の中で重要なものを表す「一麹(いちこうじ)二酛(にもと)三造り(さんつくり)」という言葉があるそうです。
約60日間かけて行われる全16工程の具体的な内容について調べてみました。
【①精米(原料処理)】
酒米の表層に含まれる脂質やタンパク質は雑味の原因となるため、食用米よりも多く表面を削ります。削り取る割合は、日本酒の種類により異なります。例えば精米歩合40%にするためには、約48時間もの時間を要するそうです。
【②枯らし】
冷暗所で2〜3週間ほど保管することで、精米後の米の温度を下げ、米の内部の水分を均一化します。
【③洗米】
米の表面の糠(ぬか)や米くずを洗い落とします。
洗米時に酒米は1〜2%消耗するため、磨かれた割合が高い米ほど細心の注意が必要とのことです。
【④浸漬】
酒米に水を吸わせ、蒸しの際に必要な水分を米に吸収させて糖化させやすくします。
浸漬の時間は、米を削る割合や品種、水の温度、天気、気温、湿度などにより異なります。
過剰な吸水を防ぐため、秒単位で計測しながら浸漬を行う蔵もあるそうです。
【⑤蒸米】
水をしっかりと切り酒米を熱い蒸気で蒸して、酒づくりに適した水分量に調整していきます。
こうじ菌が内までしっかり入り込むよう、外側が硬く、内側が軟らかい状態を目指します。
蒸米はこうじ用と仕込み用に分けられます。
蒸米の出来ばえは、製麹やもろみ仕込みに大きな影響を及ぼすため、特に細心の注意が必要だそうです。
蒸し後は、蒸米の温度を下げる放冷を行います。
【⑥製麹(せいきく)】
「一麹、二酛、三造り」の「一麹」にあたる工程。
こうじ菌を蒸米に繁殖させることと、酵母に対する栄養源の供給、こうじ由来の香味成分の生成区を目的として行われる製麹は、日本酒の品質に最も影響するとても重要な工程です。
こうじづくりは、室温30℃〜38℃前後、湿度60〜70%に保持された「麹室(こうじむろ)」と呼ばれる部屋で、下記の手順で行われます。
「引き込み」床(大きなテーブル)に布を敷き、蒸米を広げて温度を均一にする
「種付け」蒸米にこうじ菌の胞子をふりかける
「床もみ」蒸米の一粒一粒に均等にこうじ菌が付くように混ぜ、再び蒸米を積み上げて布で包む
「切り返し」蒸米のかたまりをほぐし、バラバラにする
「盛り」数時間後、蒸米を一定量ずつ木箱などに入れる
【⑦酒母(しゅぼ)づくり】
「一麹、二酛、三造り」の「二酛」にあたる工程。
アルコール発酵に欠かせない酵母を大量に培養します。
近代的な成法である乳酸添加法(速醸系酒母)でつくる場合は、小型タンクにこうじ・蒸米・水・酵母・乳酸を入れ、櫂棒(かいぼう)で均一になるようにかき混ぜ「酒母」をつくります。
タンクは厳重な温度管理のもと、蓋をせず開けた状態で約2週間かけ酵母を培養します。
速醸系に対して、昔ながらの製法である生酛系の場合は、空気中に漂う乳酸菌を取り込み、繁殖させて増やします。
非常に時間がかかるため、蒸米を糖化しやすいようすりつぶしていました。
これは「山卸し」と呼ばれるとても大変な作業でしたが、明治時代、酒造技術の進化とともに、多くの蔵元が山卸し作業を廃止するようになり、これを略して「山廃」と呼ぶようになりました。
現在、日本酒のおよそ90%が速醸系で、残る10%が生酛系です。
その内訳は山廃仕込みが8%、生酛仕込みが2%とのことです。
【⑧もろみ仕込み】
酒母に、こうじ・蒸米・水を徐々に加え発酵させて、アルコール発酵を行うためのもろみをつくります。
必要な原料を「添(そえ)」「仲(なか)」「留(とめ)」の3回に分けて仕込むことから、「3段仕込み」と呼ばれます。
3段階に分けるのは、酒母にある乳酸が急激に薄まらないよう分けて仕込むことで、酵母数や酸、アルコールが雑菌に汚染されるのを防ぐためだそうです。
「添仕込み(1~2日め)」
酒母に、こうじ・蒸米・水を加えてかき混ぜ、もろみの温度が均一になるようにします。
約12℃の低温発酵で、泡や香味の状態を観察できるよう小さなタンクで仕込みます。
2日めは仕込み作業はせず、温度管理しながら酵母の増殖を待ちます。
「仲仕込み(3日め)」
「添仕込み」の2倍の量のこうじ・蒸米・水を加え、大きなタンクにもろみを移し、徐々に温度を下げて約8℃にします。
「留仕込み(4日め)」
「仲仕込み」のさらに2倍の量のこうじ・蒸米・水を加えます。約6℃で管理します。
この後、約3週間〜5週間かけて発酵を進ませ、もろみを完成させます。
大きなタンク内では並行複発酵が進んでおり、発酵により温度が徐々に上がるため、櫂棒で均一に混ぜながら温度調節していきます。
【⑨搾り(上槽)】
アルコール発酵が終了したもろみを搾り、原酒と酒粕に分けます。
搾りは「槽搾り」、「袋搾り」、「にごり酒」などいくつかの種類に分かれます。
さらに抽出する部分によって、「あらばしり」、「中取り」、「せめ」など異なる商品として出荷されることもあるそうです。
搾り後は、「滓(おり)」と呼ばれる細かな米粒やこうじなどの固形物が残っており、これをタンクに沈殿させる「滓引き」を行います。
この際、滓を少し混ぜて少し濃厚でしっかりした味の「おりがらみ」と呼ばれる商品に仕上げることもあります。
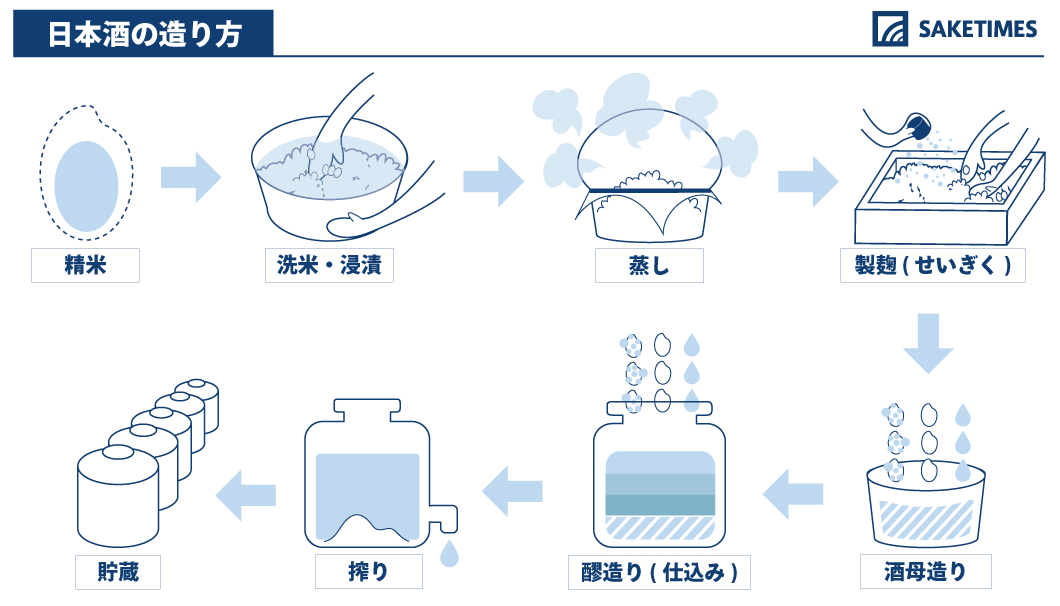
@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用
【⑩ろ過】
搾った原酒の中の残存物を取り除きます。
ろ過しないものは「にごり酒」となります。
【⑪火入れ】
60~65℃程度の低温で加熱し殺菌します。
品質劣化の原因である、糖化酵素や火落ち菌などの微生物を殺菌・除去すると同時に、酵素の働きを止めて酒質の劣化を防ぎます。
【⑫貯蔵(熟成)】
火入れした日本酒を酒造タンクで熟成させます。
アルコールと水の分子が融合してまろやかな酒質になります。
熟成期は数週間から、長い場合は1年かかるものもあります。
お酒の種類によりマイナス5℃〜25℃の範囲で厳格に温度管理し、お酒の味わいを調整していきます。
熟成期間を置かずすぐに出荷されるものは「新種」、「しぼりたて」、冬場につくって春に搾り、夏まで熟成させて秋に出荷するものは「ひやおろし」と呼ばれます。
素麺でも季節に合わせて呼び名を考えてみるって、いいんじゃないでしょうか。
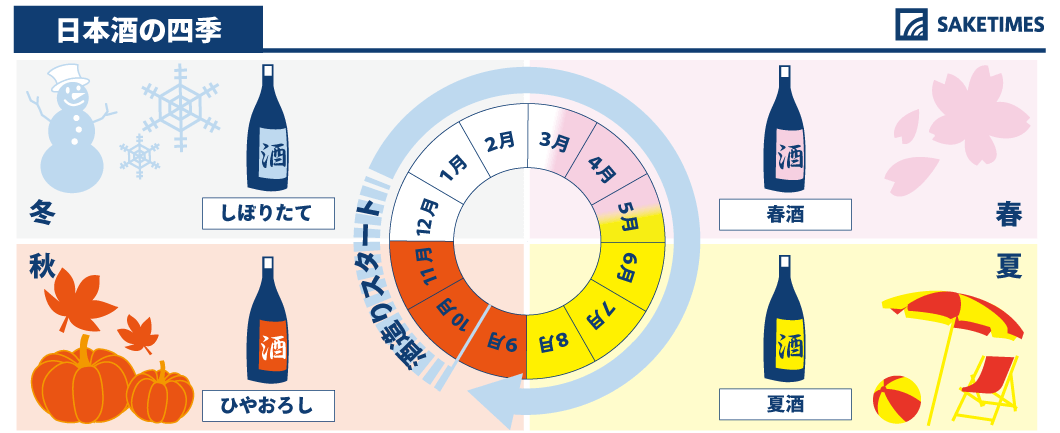
@SAKETIMES(https://jp.sake-times.com/)より引用
【⑬調合】
タンクごとに異なる酒質を一定化するための調合を行います。
蔵によっては、製造年ごとにブレンドすることもあるそうです。
【⑭割水】
調合後に仕込み水を加え、アルコール度数と香味のバランス調整を行います。
【⑮ろ過(2回目)】
割水後に脱色や香味の調整のため、ろ過をすることがあります。
【⑯火入れ(2回目)と瓶詰め】
多くの場合、お酒の酒質を安定させ、保存性を高めるため、瓶詰めの直前に2回目の火入れを行います。
ところで、皆さんは酒蔵さんの入口にある「杉玉」の意味をご存じでしょうか?
私は、知りませんでした(汗)
杉玉は2月~3月ごろに飾られ始められるそうで、「今年も新酒ができましたよ!」という目印なのだそうです。
元々、杉玉を飾り始めたのは奈良県にあるお酒の神様を祭る大神神社(おおみわじんじゃ)の文化だったそうです。
大神神社では、毎年11月14日になると「おいしいお酒ができるように」という願いを込めて杉玉を飾ったのが由来だそうで、その風習が江戸時代の初期頃から全国の酒蔵に広がり、今ではさまざまな場所で杉玉が見られるようになったとのことです。
なんと!素麺の発祥の地と言われる「大神神社」は杉玉の発祥の地でもあるんですね。
ご縁を感じずにはいられません。

<参考サイト>
・寒造りの確立と杜氏の発生 勘と経験を駆使した技能集団による酒造り(江戸時代)
https://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/industry/history/history05.html
・寒造り 【かんづくり】
https://www.kuramotokai.com/glossary/word/%E5%AF%92%E9%80%A0%E3%82%8A
・日本酒を知る 日本酒の製造工程
https://japansake.or.jp/sake/about-sake/sake-brewing-processes/
・日本酒造りの60日間を分解 味の違いはどこで生まれる?
https://sakura-wks.com/blog/how-to-make-sake/
・日本酒の作り方を解説 製造工程をわかりやすく説明
https://www.sakesen.com/blog/how-to-make-sake/
・日本酒の山廃仕込みと生酛づくりをわかりやすく解説|生酛、山廃酛、速醸酛までを説明
https://www.sakesen.com/blog/making-raw-sardines/
⑥ 風味や香りの決め手!酵母の種類
日本酒づくりに使われる「清酒酵母」は、生物学上は「サッカロマイセスセレビシエ」という名称の、大きさ5~10ミクロンの微生物で、清酒もろみ1グラム中に1~2億個ほど存在し、アルコール発酵しているそうです。
酵母にも色々な種類があり、日本酒の風味を決めるのは米よりも酵母と言われることもあるほど、重要な役割を果たしています。
明治以前は、種菌を使わず、空気中や道具に付着している「蔵付き酵母」により自然発酵するのを待つ製法のため、その蔵独自の風味を生み出す一方でお酒の質が安定しないといった問題も多くありました。
こうした課題を解決するためにできたのが「きょうかい酵母」です。
全国の優秀な酵母を科学的に培養し、日本醸造協会(当時の醸造協会)から全国の蔵元へと頒布することにより、各地で安定した質の清酒が醸造されるようになったそうです。
きょうかい酵母の名前には基本的に「6号酵母」「7号酵母」のように連番が付けられています。
また、もろみの表面に炭酸ガスによる泡が形成される性質を持たない「泡なし酵母」が開発され、その名前には「01」が付けられています。
きょうかい酵母の代表的なものは、下記のとおりです。
【1~5号酵母】
明治~大正時代にかけて販売されていた酵母。
【6号酵母】
発酵力が強く香りはやや低い。端麗な酒質に向く味わい。現在、日本醸造協会から頒布される中で最も古い酵母。
【7号酵母】
発酵力が強く香りは華やかで、普通酒から吟醸系の清酒まで幅広く使うことができ、現在最も広く使用される酵母。
【9号酵母】
「熊本酵母」とも呼ばれる、酸が低く香りが華やかで吟醸系の清酒に向く酵母。
【1801号酵母】
非常に華やかな香りで、ムレ香という不快な香りの原因となる成分量が少ないため、近年では鑑評会出品酒にもよく使われる酵母。
【赤色清酒酵母】
赤色に発色するため、ピンク色の濁り酒をつくるのに使われる酵母。
また各都道府県が設置する試験研究機関でも、独自に酵母の開発や培養、頒布を行っているそうです。
代表的なものを調べてみました。
【AK-1】(秋田県)
1991年の全国新酒鑑評会で、秋田県から25蔵の金賞受賞数を出すのに貢献した酵母。のちに「きょうかい1501酵母」としても登録。
【HD-1】(静岡県)
1986年の全国新酒鑑評会で、静岡県から17蔵が入賞(うち10蔵が金賞)を取得するのに貢献した酵母。
【長野C酵母(アルプス酵母)】(長野県)
1997年の全国新酒鑑評会で、長野県が都道府県1位の金賞受賞数を出すのに貢献した酵母。
【EK-1】(愛媛県)
2002年の全国新酒鑑評会で、愛媛県から13蔵が入賞(うち11蔵が金賞)を取得するのに貢献した酵母。
これらのほかにも、東京農業大学の「花酵母」など研究機関が開発した酵母や、酒造会社が独自に開発した自社酵母など、多種多様な酵母があります。
<参考サイト>
・熊本酵母の誕生。酔って楽しむお酒から、味わうお酒へ
https://kumamoto-sake.com/material/yeast.html
・新・酵母のはなし
https://www.jozo.or.jp/yeast/story/
・実は味の決め手?日本酒造りに使われる「酵母」を学ぶ
https://sakestreet.com/ja/media/learn-yeast-for-sake-1
・No.6 ナンバーシックス
http://www.aramasa.jp/collection/no.6.html
・酵母によって日本酒の香りが変わる!酵母の働きや種類を紹介
https://chibasake.com/blogs/topics/5243
・日本酒造りにおける「酵母」のはたらきとは?酵母の役割と種類について
https://www.sawanotsuru.co.jp/site/nihonshu-columm/knowledge/nihonshu-yeast/
⑦ 伝統製法を守りつつ数値管理で生産を拡大した「獺祭」
国内外にその名を知られる地酒に「獺祭」があります。
その生産量は30年前の約70倍にも達するとのことで、その蔵元「旭酒造」を擁する山口県は、2021年の日本酒輸出額が都道府県別で1位となっています。
大量生産する大規模な酒造メーカーがつくる日本酒は、機械化により味が落ちるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、旭酒造は伝統を守りながら質を落とさず生産量を増やす、独自のビジネスモデルを築いていることでも注目されているそうなので、調べてみました。
旭酒造では1年365日酒をつくり続ける「四季醸造」を行っています。
2015年に建設された12階建ての本社蔵と、第二蔵を併せて540万リットルの酒を、160人の蔵人でつくっているとのことで、これは同規模を製造する企業平均の3倍以上に当たる人数だそうです。
原料処理の最初の工程である洗米やこうじづくりなど、重要な工程は徹底した手作業にこだわっています。
品質を管理するために、約350本ある仕込みタンクすべてのもろみのデータ分析を毎日行っているとのこと。
酒づくりのプロセスをデータ化した数値管理により、味わいにブレがなくなり、ノウハウが蔵人全員にまんべんなく蓄積するため、杜氏の経験や勘に頼ることのない再現性の高い生産が可能となっているそうです。
作業時間は午前8時半から午後5時半までと、一般的な会社員のようなスケジュールです。
うまくいかなかった部分は原因を分析し、次の仕込みに活かす、というPDCAサイクルを回す酒づくりを行っているため、品質が安定するとのことです。
2023年3月、旭酒造はアメリカ・ニューヨーク郊外に酒蔵を建て、日本と同様手作業にこだわった製法で純米大吟醸の製造を始めたそうです。
石井製麺所とは全く規模も業種も異なりますが、1年間を通じて製造・販売できるビジネスモデルの構築は大変勉強になります。
いつか、旭酒造様にも見学へ行ってみたいと考えています。

<参考サイト>
・3倍以上の人手で実現する『獺祭』の品質と製造量 – 山口県・旭酒造(獺祭)
https://sakestreet.com/ja/media/sakagura-asahi-shuzo-yamaguchi
・「獺祭」を日本一にした”掟破り”PDCAの秘密
https://toyokeizai.net/articles/-/176256
・勘に頼らず「数値管理」で生産拡大した獺祭 成功した酒蔵の経営戦略
https://smbiz.asahi.com/article/13777316
・【獺祭の米国製造】優秀なスタッフを送り込んだうえに、なぜ会長まで行くのか?
https://diamond.jp/articles/-/327144
⑧ 《石井製麺所の取り組み》OEM手延べ麺 編
『OEMとは、メーカーが他企業の依頼を受けて製品を代わりに製造すること、またはその業務を行う企業を指す言葉』です。
自社で独自製法による「しょうどしま長命草素麺」を開発・販売して以降、その製法のおかげもあり様々な食材を練り込んだ自社製品を開発してきました。
現在では、島内外のお会社様や農家さんなど、実に19種類の手延べ麺をつくってきました。
北は北海道から、南は沖縄まで、大きな販売店様の自社ブランド素麺や自社で扱う原料を練り込んだものや、こだわりの小麦を使用した素麺の製造など幅広いご依頼をいただくようになりました。
もちろん、開発段階のものやサンプル製造などを含めるともっとたくさんのご依頼をいただいていることになります。
石井製麺所では、「健康によりそうめん」として、天然由来の素材や食材を中心に練り込み系の手延べ麺開発を受けています。
着色料や保存料などは一切使用しない、食材の栄養価はもちろん、美味しさを活かした手延べ麺をご提供しています。
試作の時には、ハタにかけた麺が「ブチブチッ」と切れることや、こびきの段階で上手く伸びないものなど、原因究明や改善点の追求で夜も眠れない日が続いたりもしました。
それでも、満足のいく品質のものができ、お客様からお喜びの言葉をいただくとそれまでの苦労も報われるような気がします。
現在では、様々な産地の食材を活かした手延べ麺で地域の盛り上がりに寄与できるものやご依頼いただくお会社様のブランドを代表するような手延べ麺を開発したいと考えています。
家族経営での製造ですので、大きなロットは難しいですが、逆に言えば小ロットで製造・販売したいお会社様にとっては、お使いいただきやすい規模だと考えています。
こだわり食材を練り込んだ手延べ麺をご検討のお会社様があれば、お気軽にお問い合わせください。
もちろん、白い素麺の製造も自信を持っておりますので、自社でお持ちのこだわりの小麦粉や原料などございましたら、遠慮なくご相談ください。
少量のサンプルづくりから、お手伝いさせていただきます。

《石井製麺所公式ホームページ》 https://141seimen.com/business/
《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.37
栄養成分の機能性について/アミノ酸①
夏場、暑くなると食欲も落ちて体力も落ち、イマイチ体調が優れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときは、冷たい素麵!!
といいたいところですが、これから始まる暑い夏を乗り切るためにはそれだけでは、いけませんよね。
食欲が湧かなくて、ついついあっさりとしたものやサラサラっと食べられるものですませてしまったり。。。
素麵だけでは、元気になれる食事は難しいかも知れませんが、夏の疲れに役立つ食材と合わせて食事ができれば、暑い夏も上手に乗り切れるのではないでしょうか。
そこで今回は、体の元気の源、アミノ酸について、ブログを書いてみました。
食品関連の仕事をしていると「アミノ酸」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが「旨味成分」。
グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸などが思い浮かび、出汁や和食などを連想します。
しかしながら、今回は「人間の体(元気)をつくる」アミノ酸の有用性や機能性について調べてみました。
よく聞くBCAAや必須アミノ酸などがありますね。
私三代目も大学のアーチェリー部で活動していたときには、疲労回復や体力改善にアミノ酸(を含む食事)の摂取を心掛けたものです。
「えっ?美味しいものを食べたら疲労回復に繋がるの??」って思いませんか?
アミノ酸には数多くの種類があって、必須アミノ酸や非必須アミノ酸、遊離アミノ酸と呼ばれるものがあり、働きが微妙に違うようです。
その微妙な違いを知って活用できることが大変重要なようです。
アミノ酸を含む食材との組合せで美味しく素麵を食べてもいただきたいですが、現在、様々な食材や素材をまるごと粉末化して麺に練り込み、「健康によりそう麺」をコンセプトに新製品開発もおこなっています。
このアミノ酸の知識は、美味しいだけでなく体が喜ぶ素麵をつくる際にも、どうやら重要なもののようです。
そこで今回は、人間(生物)の体を支えるアミノ酸の有用性や機能性などについて調べて、整理してみました。
調べていても、ちょっと何を言っているか分からない部分もあり、理解を十分にできていないかも知れませんが、今回も勉強のつもりで一緒にお付き合いいただければ幸いです。

【目次】
① 宇宙から飛来?人体に欠かせないタンパク質を構成するアミノ酸とは
② 20種類のアミノ酸、それぞれの有用性について
③ アミノ酸は5種類の元素からできている
④ 食品をはじめ、大きく広がるアミノ酸の機能性について
⑤ アミノ酸をバランスよく摂れる食事とは?
⑥ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリジナルギフト&ノベルティ 編
① 宇宙から飛来?人体に欠かせないタンパク質を構成するアミノ酸とは
アミノ酸はタンパク質の構成成分です。
タンパク質は、エネルギーをつくりだして筋肉や皮膚・髪など体を構成するために重要な栄養素です。
自然界には500種類以上のアミノ酸が存在しますが、その中で人間に必要なタンパク質を構成しているのは20種類のみで、そのうち1つでも欠けるとタンパク質を合成できないそうです。
人間の体は体重の約60%が水分で、その次に多いのが約20%を占めるタンパク質です。
アミノ酸は、私たちの体をつくるために欠かせない要素と言えます。
アミノ酸が最初に発見されたのは、1806年のことです。
フランスの化学者がアスパラガスの芽からアスパラギンを発見しました。
以降、尿結石からシステイン、ゼラチンからグリシン、筋肉や羊毛からロイシンが見つかったそうです。
1935年までに、タンパク質を構成するすべてのアミノ酸が発見されました。
1838年、オランダの化学者がタンパク質の概念を提唱し、タンパク質がアミノ酸から構成されていると示したことにより、アミノ酸の重要性が認識されるようになったそうです。
アミノ酸は、宇宙から飛来した隕石や5億年前の三葉虫の化石からも検出されています。
1969年、オーストラリアに落下した隕石から、微量のグリシン、アラニン、グルタミン酸、ベータアラニンが確認されました。
2022年には日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウの砂から、23種類のアミノ酸(うち、生物のタンパク質をつくるアミノ酸11種)が検出されました。地球以外の宇宙にも生命体が存在している可能性が高まったと考えられています。
現在でも化石や隕石、小惑星のアミノ酸から生命起源の謎を解く研究が続けられているそうです。

<参考サイト>
・アミノ酸
https://himitsu.wakasa.jp/contents/amino-acid/
・アミノ酸とは?種類と働きを解説
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/1989/
・アミノ酸とは?
https://www.ajinomoto.co.jp/amino/about/aminoacids/
・アミノ酸の発見と合成、その歴史について
https://fandw.jp/blogs/column/what_is_amino_acid
② 20種類のアミノ酸、それぞれの有用性について
人体を構成しているタンパク質は10万種類にも及びますが、それらは20種類のアミノ酸の様々な組み合わせでつくられています。
アミノ酸は、食べ物から摂取しなければならない必須アミノ酸9種類と、体内で合成することができる非必須アミノ酸11種類に分けられます。
【必須アミノ酸】
<バリン、ロイシン、イソロイシン>
骨格が一部分岐した分子構造を持ち、「分岐鎖アミノ酸(BCAA=Branched Chain Amino Acid)」と呼ばれます。
筋肉中のタンパク質に含まれる必須アミノ酸のうち約40%を占め、運動時のエネルギー源として利用されます。
BCAAを摂取すると、運動後の筋肉の分解が抑えられ、筋肉のタンパク質をつくる量を増やすことが知られており、また運動による筋肉痛や筋肉のダメージを軽減することも分かっているそうです。
鶏肉・牛肉・マグロの赤身・カツオ・卵・牛乳などに多く含まれます。
<スレオニン>
酵素の活性部位などの形成に用いられます。
ゼラチン、桜エビ、豚肉、鶏肉、大豆製品、海苔、タラ、ゴマサバなどに多く含まれる成分です。
<メチオニン>
生体内で必要な様々な物質をつくるのに用いられる成分です。
シラス、大豆製品、豚肉、鶏肉、サケ、ゼラチンなどに多く含まれます。
<リシン(リジン)>
小麦粉や精白米などの穀物に不足しがちなアミノ酸。
アルギニンと一緒に摂ることで、精神的ストレスや不安感を軽減することが期待されます。
桜エビ、ゼラチン、豚肉、鶏肉、タラ、チーズ、大豆製品などに多く含まれます。
<ヒスチジン>
ヒスタミンなどをつくるのに用いられ、日常生活で感じる疲労感を軽減します。
多く含まれる食品は、煮干し、マグロ、カツオ、鶏肉、豚肉、大豆製品、チーズなど。
<フェニルアラニン>
多種の有用な化合物をつくるのに用いられています。
煮干し、チーズ、イワシ、大豆製品、ゼラチン、豚肉、落花生、鶏肉などに多く含まれる成分です。
<トリプトファン>
多種の有用な化合物をつくるのに用いられます。
多く含まれる食品は、大豆製品、煮干し、桜エビ、豚肉、鶏肉、マグロ、ゴマ、チーズなど。
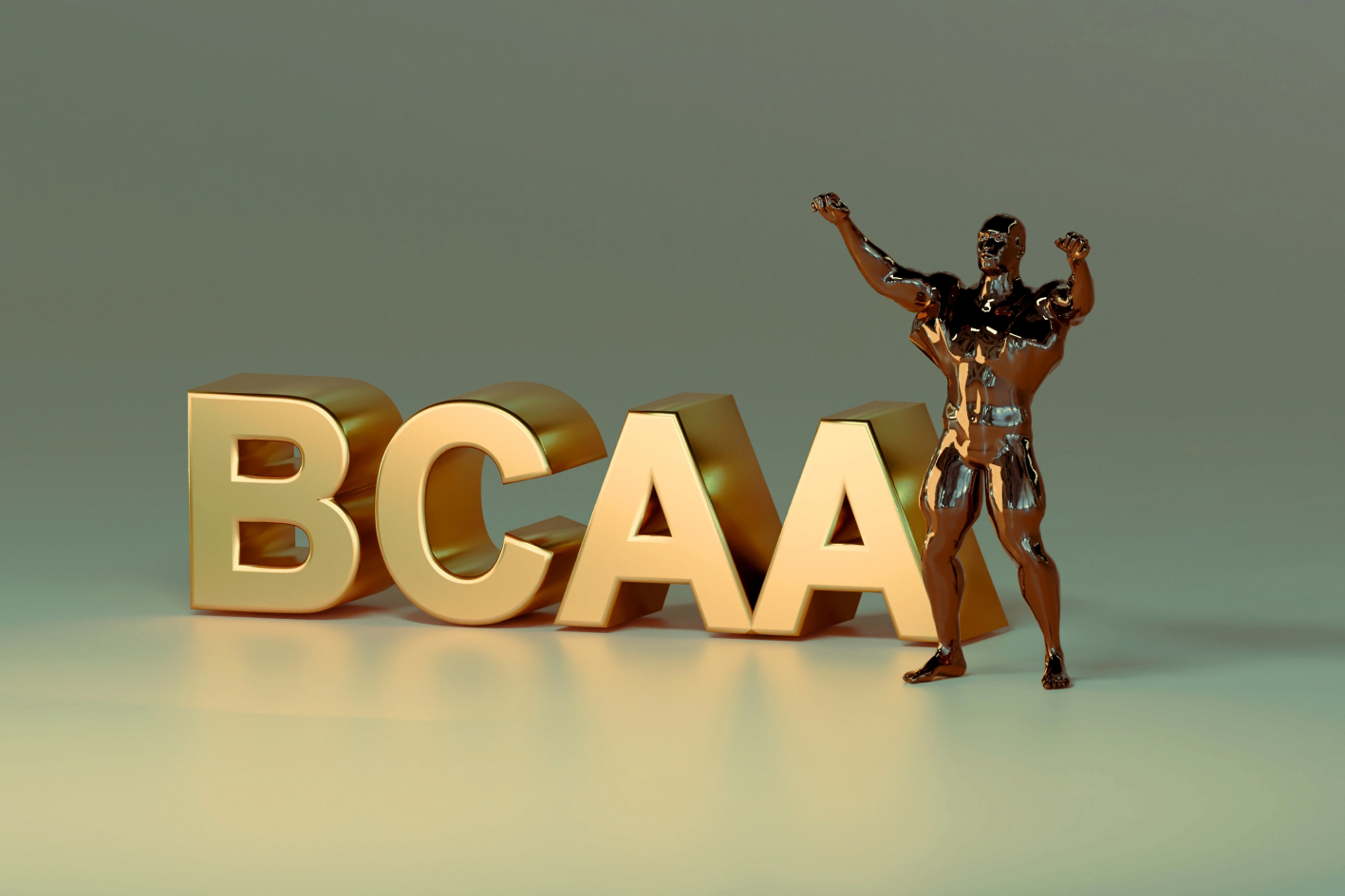
【非必須アミノ酸】
<グリシン>
コラーゲンの3分の1を構成しているアミノ酸。
神経ネットワークの情報のやりとりにも関わり、運動・感覚などの体の調節に役立ち、速やかに自然な深い眠りに入るのを助けます。
ゼラチン、エビ、大豆製品、ウナギ、鶏肉、落花生などに多く含まれます。
<アラニン>
肝臓の働きを助け、体に必要な糖を合成する材料としても使われ、アルコール代謝を改善する作用が報告されています。
多く含まれる食品は、ゼラチン、しらす、大豆製品、鶏肉、豚肉、海苔など。
<セリン>
肌の天然保湿因子(NMF)に含まれるアミノ酸のうち最も多いもの。
細胞の膜の材料となり、神経細胞に多く含まれるリン脂質やグリセリン酸をつくるのに用いられる他、睡眠の質を高めるのに役立ちます。
多く含まれる食品は、ゼラチン、チーズ、大豆製品、海苔、イクラ、豚肉、落花生など。
<アスパラギン酸>
エネルギー生産の場である「TCA回路」の最も近くに位置するアミノ酸のひとつで、エネルギー源として利用されます。
桜エビ、ゼラチン、大豆製品、タラ、豚肉、鶏肉、落花生などに多く含まれています。
<アスパラギン>
アスパラガスから見つかったアミノ酸。
アスパラギン酸とともに「TCA回路」の近くに位置します。
<グルタミン酸>
体内で抗酸化作用を発揮するグルタチオンの材料のひとつ。
多くのアミノ酸が、グルタミン酸をもとに合成されます。
旨味成分で、特に昆布やトマト・ブロッコリーなどの野菜類、チーズなどの発酵食品に多く、他にもゼラチン、大豆製品、アーモンド、豚肉などに多く含まれています。
<グルタミン>
腸管のエネルギー源として利用され、胃や腸管を守る働きをします。
また、肝臓を守りアルコールの代謝を高める働きを持つと報告されています。
<アルギニン>
血管を広げるために必要な一酸化窒素をつくりだし、血管を広げて血液を通りやすくするのを助けます。
余分なアンモニアを除去するのにも役立ちます。
また、免疫機能を高めることが報告されています。
多く含まれる食品は、ゼラチン、大豆製品、落花生、ゴマ、煮干し、鶏肉など。
<システイン>
毛髪や体毛に多く含まれており、黒いメラニン色素の産生を抑え、黄色いメラニンを多くつくるよう働きかけます。
大豆製品、海苔、イクラ、ゴマ、鶏肉、豚肉などに多く含まれています。
<チロシン>
フェニルアラニンやトリプトファンなどとともに芳香族アミノ酸とも呼ばれ、多種の有用なアミンをつくるのに用いられています。
多く含まれる食品は、桜エビ、チーズ、しらす、豚肉、鶏肉、大豆製品など。
<プロリン>
皮膚に潤いをもたらす天然保湿成分(NMF)として最も重要なアミノ酸のひとつで、高い保湿作用があります。
皮膚などの組織を構成するコラーゲンの原料となり、また体に必要な糖を合成する材料としても使われます。
ゼラチン、チーズ、エビ、大豆製品、小麦粉、鶏肉、豚肉などに多く含まれます。
体内では、細胞や血液中などにバラバラの状態で存在するアミノ酸もあり、「遊離アミノ酸」と呼ばれています。
テアニン・オルニチン・シトルリン・タウリンなど多くの種類があり、体を維持するために重要な役割を担っています。
タンパク質構成アミノ酸は一般的には無味ですが、タンパク質が分解されて生じる遊離アミノ酸は味を持ちます。
遊離の形のグルタミン酸やアスパラギン酸は、旨味成分として知られています。
グリシン・アラニン・トレオニン・プロリン・セリンは甘味、フェニルアラニン・チロシン・アルギニン・イソロイシン・ロイシン・バリン・メチオニン・リシンは苦味を持ちます。

<参考サイト>
・私たちのカラダをつくるアミノ酸の種類
https://www.ajinomoto.co.jp/amino/about/classified/
・アミノ酸とは?アミノ酸について簡単解説!
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=130&category=health
・味に関わるおいしい話④ 遊離アミノ酸と味について
https://www.shokukanken.com/colum/colum0193/
・うま味の基本情報
https://www.umamiinfo.jp/what/whatisumami/#:~:text=%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E3%81%8C%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%8A,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81
③ アミノ酸は5種類の元素からできている
アミノ酸は、5種類の元素 (炭素(C)、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)、硫黄(S))から構成されている有機化合物です。
塩基性基のアミノ基(-NH2)と酸性基のカルボキシ基(-COOH)を有します。
アミノ酸同士はペプチド結合(-CONH-)によって結合することにより、二つのアミノ酸が結合した「ジペプチド」や、アミノ酸が多数結合したタンパク質など各種の化合物が構成されます。
アミノ基とカルボキシ基が同じ炭素に結合しているアミノ酸を、α-アミノ酸と呼びます。
タンパク質を構成するアミノ酸は、プロリンを除きすべてα-アミノ酸です。
グリシンを除くα-アミノ酸には、互いに鏡に映すと同一になる右手と左手の関係のような構造のもの(光学異性体)が存在し、一方をL体、もう一方をD体と呼んで区別します。
タンパク質を構成するアミノ酸は基本的にすべてL体です。
D体は、天然では細菌の細胞壁の構成成分や老化組織、神経細胞などに存在が確認されているとのことです。
構造内に2つ以上のアミノ基を持つアミノ酸(リシン・アルギニン・ヒスチジン)は塩基性を、2つのカルボキシ基を持つアミノ酸(アスパラギン酸・グルタミン酸)は酸性を、その他のアミノ酸はほぼ中性を示します。
中性アミノ酸は、アミノ基およびカルボキシ基以外に持っている特徴的な基により分類されます。
アルキル鎖を持つグリシン・アラニン・バリン・ロイシン・イソロイシン、ヒドロキシ基を持つセリン・トレオニン、硫黄を含むシステイン・メチオニン、アミド基を持つアスパラギン・グルタミン、イミノ基を持つプロリン、芳香族基を持つフェニルアラニン・チロシン・トリプトファン、と分けられます。
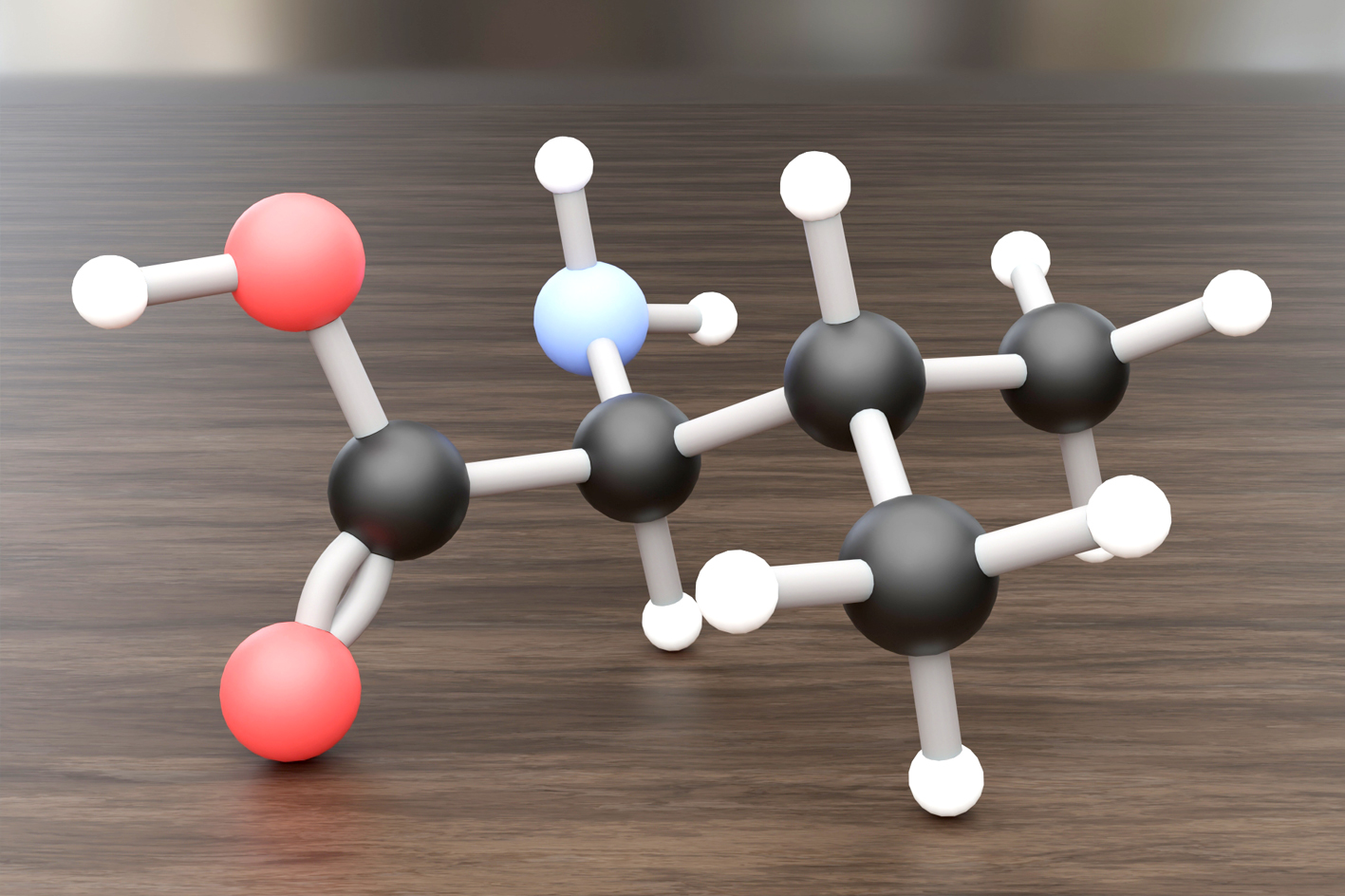
※写真はPhotoACより「バリン(アミノ酸)の分子模型」
<参考サイト>
・アミノ酸とは?
https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/topics/amino/about.html
・Wikipediaアミノ酸
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8
・アミノ酸とは
https://www.rikelab.jp/glossary/4761.html#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA(-,%E3%80%81%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%CE%B1-%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%E3%81%A7%E3%81%
・アミノ酸の名称につく「L」「D」「DL」とは?
https://www.ajinomoto.co.jp/amino/about/aminoacids/kuwashiku1.html
④ 食品をはじめ、大きく広がるアミノ酸の機能性について
タンパク質をつくる重要な成分であるアミノ酸は、個別に色々な機能を持ちます。
機能性成分としてのアミノ酸は、医薬品原料、医療食、健康食品、食品、飲料、化粧品、培地、飼料、肥料といった幅広い分野で活用されています。
主な機能について調べてみました。
【筋肉の維持・増強】
BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)は、筋肉の分解を抑え、筋肉の維持や増強を担う働きをします。運動しながら筋肉量を増やしたい人や、肺の疾患を持つ人が消耗した呼吸筋の損傷を防ぐためなどに役立つ成分です。
【エネルギー代謝に役立つ】
リシン・プロリン・アラニン・メチオニン・アルギニンは、有酸素運動などで脂肪からのエネルギー供給にかかわる物質の原料となると考えられています。またアルギニンには、成長ホルモンを促す働きがあるとされます。
【免疫機能を助ける】
アルギニンやグルタミンは、免疫に関わる物質の働きを助けるとされています。

【リラックスと集中力】
トリプトファンは、脳をリラックスさせるセロトニンの原料になり、チロシンは、脳の興奮や集中に影響するとされるドーパミンの原料になると考えられています。
【美肌】
肌の角質層に含まれるNMF(天然保湿因子)の約半分をアミノ酸とその類縁体が占めており、また真皮に含まれるコラーゲンもアミノ酸からできています。シトルリン、セリン、アルギニン、オルニチンが、美肌に役立つと考えられています。

<参考サイト>
・アミノ酸の多様な用途
http://www.kyowahakko-bio.co.jp/rd/aminonavi/usage/
⑤ アミノ酸をバランスよく摂れる食事とは?
体内で合成できない必須アミノ酸は、食事などからタンパク質として日常的に摂取する必要があります。
食品に含まれるタンパク質は、アミノ酸が50個以上つながった大きな分子なので、そのままの形ではなく、胃や腸で分解されてアミノ酸となってから体内に吸収されます。
そして血液により全身の細胞へ運ばれ、そこでアミノ酸同士が遺伝子(DNA)に従って順番に連結され、必要なタンパク質に再合成されます。
タンパク質を多く含む食品の中でも、必須アミノ酸をバランスよく摂ることができる食品を効率よく摂取することが大切です。
タンパク質の栄養価を評価する方法として有効なのが「アミノ酸スコア」です。
各食品に含まれる必須アミノ酸の構成のバランスを数値化するもので、必須アミノ酸をバランス良く含む良質な食品のアミノ酸スコアは100と評価されます。
代表的な食品は、牛乳、卵、豚肉、鶏肉、牛肉、アジ、サケ、マグロなどです。
アミノ酸スコアは、9種類の必須アミノ酸のうち最も含有量が少ないアミノ酸が基準となり、1つでも含有量の少ないアミノ酸がある食品はスコアが低くなります。
小麦や精白米は、リシンの含有量が少ないためスコアが低くなっています。
足りないアミノ酸を補い、また糖質、脂質、ビタミン、ミネラルといった必要な栄養素もバランスよく摂取するためには、多様な食品を一緒に摂取することが大切です。

<参考サイト>
・「アミノ酸」とは?アミノ酸の種類や含まれる食べ物について解説
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/409/
・人間の体はタンパク質でできている。タンパク質・アミノ酸・ペプチドの関係を解説
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=20&category=health
⑥ 《美味しい小豆島の食財紹介》オリジナルギフト&ノベルティ 編
「大切なお客様の印象に残る贈り物が欲しい」
夏のギフトシーズンを前に、こういったご要望をいただくことがあります。
石井製麺所では、自社の手延べ素麵・手延べ麺だけでなく、小豆島の様々な味覚や商品と組み合わせてオリジナルのギフトをご用意しています。
また、業務用の記念品や粗品などのノベルティなども承っております。
お客様にとってのお客様もまた、弊社では大切なお客様です。
業務用ギフトや大切な方への贈物など、 さまざまなオリジナルギフトのご要望に量・質でお応えします。
◎記念品やお祝いの品なども対応
◎豊富なギフトラインアップから選択可能
◎ご予算に応じたオリジナルギフトセットも対応
◎熨斗、包装紙なども対応可能
◎オリジナルパッケージや支給紙・箱へも対応可能
◎少量・多量にかかわらず対応可能
◎当社契約の運送会社から発送するので低コストでの送付も可能(離島料金不要)※
まずは、ご予算やご要望などをお聞かせください。
できるだけお客様のお考えに近いギフト&ノベルティをご用意させていただきたいと思います。
下記は、今では弊社の人気ギフトセットですが、元々はお客様のご要望から生まれたギフトセットです。
小豆島の醤油、オリーブオイルをはじめ、弊社の乾平うどん、手延べ素麵をひとつにまとめた夏だけの贅沢なセットです。
大切な方に喜ばれる美味しいセットをご用意されませんか。
※送料については取扱数量や重量、送付先により異なりますので、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。また、お支払いは支払条件払いなどにもお応えできますので、条件など事前にご確認ください。
《小豆島便り〈夏〉》 https://141seimen.thebase.in/items/74185567
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.36
麺究者への道/パンについて研究してみる
今回のブログでは、「発酵」「熟成」を語るなら触れておきたい「パン」について調べてみました。
実は、大手パン屋さんで働いた経験があります(笑)。
その時はアルバイトでしたが、今から思うと、家業を継ぐにあたってとても良い経験であり、知識を得る場であったと思います。
単に、パン好きだったのもありますが(笑)。
今、新製品開発にあたって「発酵」「熟成」について、色々と調べていますが、パンについては素麵の製造に近いところもあり、自分の中では参考になる点も非常に多いと感じています。
また逆に、パンに求められて素麵に求められていないものや、パンにはあって素麵に無いものなど、新商品だけでなく、サービスや製造工程でも学びが多く、こうしてブログを書く際にも改めて勉強になると感じています。
パンの歴史を掘り下げてみると、人間の歴史や文化の進化にパンも大きく関わっていたことに気付かされます。
主食とそうでないものの違いも大いにあるでしょうか。
では、なぜ素麵は主食にならなかったのか。
パンも元々は供物であったり、貴族や富裕層のものであったりしました。
素麵も日本に入ってきたときには、貴族のものであり、供物としても珍重されてきました。
それがいつしか、日常食とされるパンと非日常食(と思っていますが)の素麵では差がつき、食卓に上る回数も大きく異なってきます。
もちろん、手軽に食べることができるパンと、ある程度準備が必要な素麵では、自ずと差が出てしまいますが、果たしてそれだけでしょうか。。。
私は、素麵を日常食として取り入れていただくためには、どのような事が必要か、素麵業界のタブーを越えて考えています。
そういう意味では、近くて遠い「パン」は、私の目標であり、参考であり、ライバルでもあります。
今回のブログでは、知っているようで知らなかったパンのあれこれや、今さら聞けないパンの事情について調べてみました。
パンを専門とされる方には物足りないかも知れませんが、もし、追加情報などあればぜひご教授ください。
今回も最後までお付き合いの程、どうぞよろしくお願いいたします。

【目次】
① パンの起源はメソポタミア。そして世界へ
② 鉄砲とともに日本に伝えられたパン
③ パン生地の主な製法とは
④ パンの美味しさは発酵により決まる
⑤ 天然酵母とイーストは何が違う?
⑥ 噛み応えの違いで分けられるハード系、ソフト系
⑦ 小麦とアレルゲンフリーを考える
⑧ グルテンを含まない「米粉パン」とは?
⑨ パンに似ている日本の郷土料理
⑩ 《美味しい素麺》手延べ乾平うどん 編
① パンの起源はメソポタミア。そして世界へ
今から8000年~6000年ほど前の古代メソポタミア(現在のイラク、シリア、トルコのあたり)では、小麦などの穀物を粉にして水を加え薄く伸ばして焼く、平たい無発酵パンを食べており、これがパンの原型と言われています。
この平焼きパンの食文化は中近東やインドの文化圏に広まり、今でもピタパンやトルティーヤ、チャパティなどが食されています。
その後、古代エジプトへ小麦栽培とパンづくりが伝わりました。今から約5000年前、パンを焼こうと小麦粉に水を加えて生地をつくり置いておいたところ、空気中の酵母がついて、自然に発酵。
それを焼いてみるといつもよりふっくらして美味しいパンができた、という偶然から発酵パンが生まれたと考えられています。
古代エジプトではビール発酵種を小麦粉に混ぜて「ガレット」と呼ばれる平焼きパンを焼くようになっり、これが世界最古のパンだと言われています。
最初は砂漠の中で強い太陽熱を利用して焼いていましたが、次第に色々な窯を工夫していったようです。
パンは、古代エジプトの人にとって日常の主食であると同時に神に捧げる供物であり、役人の給料でもあったそうです。
当時大麦の粥が主食だった古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、「エジプト人はパン食い人だ」と驚いたとのこと。ラムセス3世の墳墓にはパン職人たちの壁画が描かれ、大量のパンをつくっていた当時の様子が示されているそうです。
エジプト人はパンの製法を国外に伝えることを禁じていましたが、エジプトに捕虜として捕らわれていたヘブライ人により国外に伝えられたと言われています。
ヘブライ人は窯に工夫を加え、半連続的に大量にパンを製造する方法を開発しました。
これが直焼きパンの製法の始まりとのことです。
古代ギリシャでは今から2500年ほど前にエジプトからパンづくりが伝わりました。
特産のオリーブオイルを使った揚げパンや菓子などがつくられたり、酵母が含まれたブドウ液をパンづくりに用いるようになったりしました。
原料も多様化し、大麦、エン麦、粟、レンズ豆、さらにハチミツやクリーム、卵、ドライフルーツなどを使って主食だけでなく嗜好性の高いパンもつくられたそうです。
また、細かい粉をひくことができる「ひき臼」や、オーブンの原型に近い「パン焼き窯」が発明されるなど、製パン技術も大きく進歩したそうです。

※写真はPhotoACより「ポンペイ遺跡のパン屋」
古代ローマ時代、ローマ軍がギリシャへ侵攻すると、奴隷として捕らえられたギリシャのパン職人により、製粉や製パンの技術がローマへ広まりました。
小麦の皮を取り除いて白く口当たりのよいパンをつくるため、馬のしっぽの毛を使った「ふるい」が発明されたそうです。
ローマ市内には国営のパン焼き窯が設置されて大量生産がはじまり、パンの配給も行われたとのことです。
ローマでは貴族や教会が製パン所を支配し、庶民がパンをつくることを禁じました。
全盛期のローマの街には254軒の製パン所があったそうです。
パン職人は結束して組合を組織し、政治的にも地位が高く、様々な特権をもっていました。
ローマ帝国が各地を征服していくのに伴い、パン食文化もヨーロッパ各国に伝えられていきました。
ヨーロッパではそれまで主に大麦を生産していましたが、より美味しい小麦の生産に変化していったそうです。
また小麦の育ちにくいドイツやロシアなど北欧では、ライ麦粉のパンや、ライ麦粉に小麦粉を混ぜたパンをつくるようになったそうです。
ローマ帝国滅亡後、パンづくりの技術はほとんど進歩が見られませんでした。
当時パンづくりが許されていたのは、一部のパン屋と教会や修道院、貴族に限られていました。
14~16世紀、イタリアを中心にルネサンスが起こると、ヨーロッパでは国ごとに特徴のあるパン文化が花開き、国家規模でナショナルブレッドという考え方が生まれてきました。
フランスパン、イギリスパンといった言葉は、「我が国のパン」という意識が強いことから生まれたものです。
またイギリスから新大陸に渡ったパンは、機械化の恩恵を受けて生産の合理化や量産化が進み、アングロアメリカ系と呼ばれるリッチな配合のパンとなっていきました。
ちなみに「パン」と「ブレッド」は同じものです。
「パン」は日本語をはじめ、台湾語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語などで用いられる呼称で、語源はポルトガル語で「パン」を意味する“pão”だそうです。
「ブレッド」は、英語、デンマーク語、ノルウェー語などで用いられ、長方形の箱型で焼いた「食パン」を指すことが多いとのこと。
語源はゲルマン語で「醸造」を意味する “Brauen”と考えられています。
ちなみに英語圏で「パン」というと、フライパンの短縮形である場合が多く、「パンケーキ」はフライパンで焼くケーキに由来する言葉だそうです。

<参考サイト>
・パンの歴史館
https://www.yamazakipan.co.jp/stylebook/pan-history/index.html
・パンの歴史
https://www.guruman.co.jp/knowledge/knowledge-3523
・パンの歴史は、人類の食へのこだわりの歴史
https://www.pascoshop.com/Page/LP/column/09.html
・おしえて!小麦ごはん
https://delsole-komugigohan.jp/komugigohan/bread/genealogy.html
・パンの歴史
https://www.panstory.jp/history/history.html
・パンは文化だから伝統行事で使われている
https://www.pascoshop.com/Page/LP/column/10.html#:~:text=%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9,%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%9F%E3%81%BE
・「パン」と「ブレッド」「トースト」の違いは?
https://lowch.com/archives/15623
② 鉄砲とともに日本に伝えられたパン
本格的な西洋風のパンが日本へ伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって、鉄砲とともに伝えられたとされます。
1549年、フランシスコ・ザビエルらが日本へやってきてキリスト教の布教活動をはじめると、「キリストの肉」とされるパンも全国へ広まりました。
織田信長は異国の衣食住について非常に関心を寄せ、パンも喜んで食べたと伝えられています。
南蛮貿易で栄えた肥前(長崎県)の平戸や長崎では、パンづくりが特に盛んになったそうです。
しかし、食べていたのは主に日本にやってきていた貿易商人や宣教師たちで、米を主食とする日本人にはパン食はなかなか根付きませんでした。
鎖国政策が打ち出されると、唯一オランダ人の入港を許可された長崎の出島だけでパンづくりが細々と続けられました。
1840年に清とイギリスの間でアヘン戦争が始まり、徳川幕府は外国からの攻撃に備える国防対策に着手しました。
江戸湾の警備を命じられた伊豆韮山の代官・江川太郎左衛門は、戦争が起こった時に兵士に持たせる「兵糧」として、携帯に便利で保存性もよく、火をおこさなくてもそのまま食べられるパンに注目。
1842年、本格的な製パン所をつくり、出島からパン職人を招いてパンを焼かせました。
今の乾パンのようなものだったと言われていますが、日本人が日本人のためにつくった初めてのパンであり、江川太郎左衛門は「日本のパンの祖」と呼ばれています。
1858年の開国後、欧米諸国から来日する外国人たちのため、居留地のある横浜に外国人の経営による4軒のパン屋ができました。
これに続き、長崎や函館の居留地でもパンづくりが行われるようになりました。
当時パンは高級品だったため、大衆にまでは浸透していきませんでした。
1874年、「銀座木村家」創業者の木村安兵衛が、日本人の好みに合わせ、日本酒づくりに使う米こうじ(酒種)でつくったパン生地を開発しました。
1875年にはこの生地であんを包んで焼いた「あんパン」を発売し、爆発的な人気を呼びました。その後、庶民の間であんパンやジャムパン、クリームパンなどの菓子パンが定着していきました。
1890年に大凶作が起こり米が不足すると、代用食として食パンに砂糖醤油をつけて焼いた「つけ焼きパン」が大流行したそうです。
明治から大正にかけて、製パン機械や原材料が著しく進歩し、パン産業は飛躍的に発展しました。
イーストが登場したのもこの頃です。
ビール酵母、生イーストを経て、アメリカからドライイーストが輸入されるようになり、1913年にはアメリカでイーストのつくり方を学んだ田辺玄平が国産イーストを開発。
それを使ったパンづくりが行われるようになりました。
第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官マッカーサーは「日本人を米と魚の食生活から解放する」と言明。
救援物資として日本に大量の小麦粉をもたらしました。
日本では「メリケン粉」と呼ばれ、委託加工所でパンが大量生産されるようになったそうです。
「中種法(なかだねほう)」というアメリカ式の製法でつくられた食パンは、やわらかくて日本人好みで、日本人も主食としてパンを食べるようになっていきました。
1946年には小学校でコッペパンと牛乳の学校給食が始まり、1954年に成立した「学校給食法」では、全国の小中学校の給食で主食がパンと定められました。
1964年の東京オリンピックをきっかけとして日本人の食生活の洋風化が進み、フランスパンやデニッシュペストリーなども登場しました。
1980年代に入ると冷凍パン生地技術が発達し、1990年代以降はコンビニエンスストアが急増。
いつでも手軽に、多種多様なパンを買い求められるようになりました。
その後、全国各地のご当地パンが注目されたり、食パンやコッペパンの専門店が誕生したりとパンブームが到来しました。
2011年には、総務省が行なっている家計調査でパンの購入額が初めてお米を上回りました。
製パン技術の進歩により、国産小麦を使った高品質なパンや全粒粉を使用したヘルシー志向の美味しいパンが次々と商品化されています。
農林水産省の調査によると、2021年の日本人の主食の構成比は、米食41.1%:パン食18.7%:麺類14.1%だそうです。

<参考サイト>
・「日本のパン文化の歴史〜パン史は日本史だ!〜」
https://angel-zaidan.org/contents/japanese_bread_culture_dai_1_kai/
③ パン生地の主な製法とは
パンの基本的な材料は、小麦粉と水と塩、ここまでは素麺と同じですが、そこにパン酵母が加わります。
パン酵母は「イースト」とも呼ばれる、約10ミクロンの卵型の微生物です。
パン酵母には、生地の状態を良くする、味と香りのもととなるアルコールやエステルなどの物質を生成する、など様々な働きがあります。
パンに主に使われる小麦粉は、タンパク質の多い強力粉です。
小麦粉を水とこね合わせると、タンパク質の一種である「グルテン」という網目構造の物質が形成されます。
こねることでグルテンができるのは、他の穀物にはない小麦粉ならではの性質です。
グルテンは弾力があり、引っ張ると伸びる性質を持っています。
塩はグルテンを強くして生地を引き締め、雑菌の繁殖を防ぐなどの役割を果たします。
グルテンが膜をつくり、パン酵母が発生させる二酸化炭素(炭酸ガス)を包みこむことで、パン生地が伸びてふくらみます。
ふくらんだ生地を焼くと、ふくらんだまま固まってパンができます。
パン生地は、使う酵母の種類や発酵させる時間、材料の配合量などにより仕上がりが大きく左右されます。
パン生地をつくる方法は細かく分けると約20通りあり、その多くは「ストレート法」「中種法」の2つの方法を応用したものだそうです。
【ストレート法】
必要な材料をまとめて1度にミキシングする製法。
作業工程が少ないため、短時間で簡単にパン生地をつくることができます。
発酵時間が他の製法より短いため、粉の風味を感じやすく、風味豊かでもちもちとした弾力のあるパン生地に仕上がりますが、ボリュームが出ない、大量生産できない、他の製法に比べて日持ちしない、などの短所があるそうです。
フランスパン、クロワッサン、デニッシュなどのパン生地づくりに向いています。
【中種法】
パン生地づくりに使用する小麦粉の一部または全部を先に発酵させて中種をつくり、残りの材料に混ぜ合わせて本仕込みする製法です。
「パン生地に使用する小麦粉の50%以上を中種に使用する」「つくった中種は最低2時間以上発酵させる」という2つの条件を満たす必要があります。
進展性が高く機械にかけても傷みにくい生地になります。
手間と時間がかかりますが、きめが細かくソフトでボリュームのあるパン生地に仕上がるため、ふんわりとした仕上げにしたい食パンなどに適しています。

<参考サイト>
・パンのミニ百科
https://www.yamazakipan.co.jp/entertainment/pan_ency/index.html
・パンの工場見学
https://www.panstory.jp/pankojo/pankojo.html
・パン生地をつくる上で知っておきたい!製パン法の種類
https://koki.company/blog/detail.html?1648456172
・パン作りの基礎
https://yoshitei.net/foundation/index.php?eid=00020
④ パンの美味しさは発酵により決まる
美味しいパンをつくるには、生地をうまく発酵させることが重要です。
パンづくりにおける発酵とは、生地の中にあるショ糖やでんぷんなどの糖分をパン酵母が分解して、炭酸ガスやアルコールを発生させることです。
粉に含まれるでんぷんが酵素によってより小さい麦芽糖に分解されます。
麦芽糖がパン酵母に含まれる酵素によってブドウ糖となり、さらに炭酸ガスとアルコールなどに分解されます。
発生した炭酸ガスは、パン生地の骨格であるグルテンの網目構造のなかに閉じ込められます。
パン生地がふくらみ、同時に発生するアルコールや香気成分、アミノ酸は、パン独特の香りや味わいのもととなります。
パン生地を発酵することにより弾力のあるパンになり、パンに風味や香りが生まれます。
発酵中はパン生地の熟成も進むため、小麦の風味や旨味、弾力を引き出すために大切な工程となっています。
パンの発酵は2段階に分かれています。
【一次発酵】
一次発酵の目的は、パン生地をふくらませることと、熟成により小麦の風味や旨味を引き出すことです。
ゆっくり時間をかけて生地を熟成させるほうが、美味しいパンになります。
一般的な一次発酵の方法は、まるめた生地をボウルに入れ、乾燥を防ぐためにラップをかけ、室温25~35℃、湿度70~75%の環境に置き、生地が2~2.5倍にふくらむまで待ちます。
生地の表面を指でそっと押してすぐに離し、指の跡が残ったら発酵が完了しています。
指を抜いた穴がすぐに元に戻ってしまう場合は発酵不足、穴の周りにシワができて生地表面に多くの気泡がある場合は過発酵とのことです。
一次発酵が不足していると二次発酵もうまくいかず、あまりふくらまないそうです。
ふわふわした感じのない、目の詰まったかたいパンになります。
逆に発酵させすぎると、パサついた食感でアルコール臭と酸味の強いパンになってしまうとのことです。
【二次発酵】
二次発酵は、成形したパン生地を最終的に発酵させることが目的です。
一次発酵の後、パンの成形をおこなうとパンの中の炭酸ガスが抜けていってしまいます。
パンを焼く前に再度発酵させることで、生地の中にまた炭酸ガスが生まれ、パンがふっくらと仕上がります。
一般的な二次発酵の方法は、成形後の生地をオーブンシートに並べ、室温30~40℃、湿度75~80%の環境に置き、生地が2倍程度にふくらむまで待ちます。
生地の表面を指で軽く押し、指の跡が少し残る程度であれば発酵が完了しています。
指の跡が完全に戻ってしまった場合は発酵不足、指の跡がしっかり残った場合は過発酵の状態です。
二次発酵が不足していると、うまくふくらまず粘土のような食感になるそうです。
逆に発酵させすぎると、表面がぼこぼこして焼き色があまりつかず、パサついた食感になってしまうとのことです。

<参考サイト>
・パンの発酵の仕組みと役割は?発酵方法の手順や膨らまない際の6つの原因
https://sala1.jp/column/bread-hakkou/
・パンの美味しさと食感の決め手になる発酵とは
https://koki.company/blog/detail.html?1666934987
・なぜ必要?パン作りに欠かせない「発酵」の役割と方法を解説
https://macaro-ni.jp/106288
⑤ 天然酵母とイーストは何が違う?
酵母は自然界の様々な場所に生息する微生物で、自然界には数百種類もの酵母菌が存在するそうです。
その中で、パンづくりに利用されるのは「サッカロマイセス・セレビシエ」という酵母です。
最近「天然酵母」という言葉をよく見かけるようになりました。
天然酵母パンはヘルシーというイメージがありますが、実は「天然酵母」も「イースト(パン酵母)」も同じ「サッカロマイセス・セレビシエ」に分類されるそうです。
天然酵母を使ったパンとイーストを使ったパンは、具体的に何が違うのか調べてみました。
「イースト」は、パンづくりに適した1種類の酵母を人工的に培養した酵母のことで、天然の酵母の中でも発酵力が高いものを選んでおり、また添加物によって酵母の発酵力や安定性を高めています。
パンの発酵に特化した酵母なので安定した強い発酵力があり、短時間でパンを焼き上げることができます。
イーストを使ったパンはよくふくらみ、ふんわりとやわらかく食べやすい食感に仕上がります。
酸っぱいようなアルコールのような、独特の香りがあります。
焼き立てが最も美味しく、時間がたつと乾燥が進んで味が落ちてしまいます。
「天然酵母」には実は明確な定義がなく、イーストと区別するための表現だそうです。
一般的に、穀物や果実などについている複数の酵母が混ざったものです。
発酵に関係ない酵母も含まれ、発酵する力を強める添加物が入っていないので、発酵力が弱く不安定な場合が多いそうです。
天然酵母に使われる主な素材は、小麦粉・ライ麦・米などの穀物、リンゴ・バナナ・イチゴなどの果物、レーズン・プルーン・いちじくなどのドライフルーツ、桜・ローリエ・ホップなどの植物、そのほかヨーグルトや酒などもあるそうです。
種類ごとに香りや風味が異なり、奥深く複雑な味わいを楽しむことができます。
自然界にいる酵母を一から培養する自家製酵母の場合、まず素材を5~7日間発酵させます。
その後3~4日間、毎日小麦粉を足して酵母を育て、パンをふくらませられる発酵力をつける「種起こし」という工程を経ます。
こうしてできた「種」を使ってパンをつくるので、培養から焼き上がりまで1週間以上かかるとのことです。
最近では、酵母を培養する手間が省けるドライタイプの天然酵母も市販されています。
天然酵母パンは、噛みごたえのあるもっちりとした食感になり、酵母の香りや小麦そのものの甘みなど奥深い味わいと豊かな旨みがあるのが特徴で、時間がたっても美味しく食べられます。
パンの生地をふくらませる材料には「ベーキングパウダー」もありますが、これは炭酸水素ナトリウム(重曹)を主成分とする合成膨張剤で、イースト(酵母)とは全く違うものです。
水分と熱により化学反応を起こして炭酸ガスを発生させ、生地をふくらませます。
生地を寝かせる必要がなく、すぐに形成や焼成に取りかかれます。
サクサクとした軽い食感に仕上がるので、蒸しパンや焼き菓子づくりによく使われます。

<参考サイト>
・天然酵母とイーストの違いとは?パン酵母の種類や使い分けのコツ
https://sala1.jp/column/kobo-yeast-difference/
・天然酵母パンとは?特徴や普通のパンとの違いについても解説!
https://www.kurashiru.com/articles/f27e5eb3-3e0b-4700-8cb1-ef43fa8fa990
・ゼロから学ぶパン酵母
https://www.cotta.jp/special/bread/yeast.php
・天然酵母ってなに?
https://pand.jp/article/bread/3476/
・天然酵母とは?天然酵母パンの秘密
https://www.tontonshop.com/page/67
・失敗しない!自家製酵母の起こし方~酵母作り|お悩み解決
https://tomiz.com/column/troubleshooting-guide/homemade-yeast/
・失敗しない!自家製酵母の起こし方~種起こし&パン作り|お悩み解決
https://tomiz.com/column/troubleshooting-guide/homemade-yeast2/
・インスタントドライイーストとベーキングパウダーの違い
https://www.cotta.jp/special/article/?p=51192
⑥ 噛み応えの違いで分けられるハード系、ソフト系
パンは、その食感の違いにより「ハード系」「ソフト系」と分類されることがあります。
その中間のものを「セミハード系」と言うことも。それぞれの材料や製法にはどのような違いがあるのか、調べてみました。
【ハード系】
材料は基本的に小麦粉・酵母・塩・水のみ。
生地が伸びにくく、ふくらむ力があまり強くないため、スチームを当てて生地表面を湿らせながら焼きます。
焼き上がると、皮はかたくパリッとしており、中身はもっちり歯応えのある食感になります。
バケットなど、料理に合わせて食べる食事パンが多いそうです。
【セミハード系】
ハード系とソフト系の間のかたさの食感のパンで、生地をゆでてつくるベーグルや、イタリアのフォカッチャ、食パンなどがあります。
【ソフト系】
材料は小麦粉・酵母・塩・水に、砂糖や卵、油脂などが加わります。
生地がふくらみやすいので、焼く時にスチームを当てる必要はありません。
全体にふわふわしたやわらかい食感になります。
糖分が多いため焼き色がしっかり付きやすい特徴があります。
バターロールや、ブリオッシュなどの甘いパンがあります。

<参考サイト>
・ハード系パンとソフト系パンの作り方や材料の違いと種類
https://bread-everyday.com/hardbread-softbread-difference/
・ハードパンとソフトパン
https://pan-zukan.com/shurui/hardsoft/
⑦ 小麦とアレルゲンフリーを考える
食品の製造に携わる者として、避けて通れないのが食物アレルギーの問題です。
パンや素麺の主原料である小麦のアレルギーをお持ちの方も少なからずおられます。
「アレルゲンフリー」「アレルゲン不使用」といった言葉がありますが、それぞれ意味合いが異なり、また、日本と海外でもアレルゲンに関する表記の違いがあるということで、調べてみました。
【アレルゲン不使用】
アレルゲンを含む原料を使用せずに製造したものを指します。
アレルゲンを含まない、ということではありません。
例えば同じ製造室内でアレルゲンを使用する食品を製造していた場合、混入の恐れが完全には否定できないからだそうです。
【アレルゲンフリー】
日本国内では、アレルゲン含有量が「数μg/g(数百μg/100g)未満」のものを指します。
検査技術の進歩に伴いアレルゲン含有量の検出下限値は下がっていますが、全く含まないことの証明は不可能なので、ゼロとは言い切らないそうです。
【アレルゲン除去食品】
消費者庁より許可を受けた場合にのみ表示ができる食品で、特定の食品アレルギーの原因物質である特定のアレルゲンを不使用または除去(検出限界以下に低減した場合を含む)したものです。
医師、管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用することが適当とされています。
最近よく目にする「グルテンフリー」について、小麦アレルゲンが含まれていないという意味ではありません。
欧米諸国ではセリアック病という自己免疫疾患が一般的な病気のひとつであり、グルテンフリー食品はその治療食として利用されています。
グルテン濃度が20ppm未満であれば「グルテンフリー」の表示が可能だそうです。
輸入食品を利用する際には留意しておきたいものです。
日本ではセリアック病が極めてまれな病気とのこともあり、「グルテンフリー」記載の基準が現時点では定められていません。
グルテン含有量1ppm以下の米粉を「ノングルテン」と表示するガイドラインが策定されているそうです。
セリアック病は食物アレルギーとは異なるメカニズムで起こる病気なので、グルテンフリー食品が小麦アレルギーの人向けとは言い切れないようです。
日本では、ごく微量のアレルゲンによっても食物アレルギーが引き起こされる可能性を考慮して、小麦などの特定原材料を含む食品にあっては、原材料としての使用の意図にかかわらず、原則、当該特定原材料を含む旨を表示する必要があります。
数ppm以上の小麦総タンパク量を含む状況であれば、容器包装に小麦のアレルギー表示をしなければなりません。
また混入の可能性が排除できない場合については、食物アレルギーを持つ人に対する注意喚起表記が推奨されています。
<参考サイト>
・食物アレルギー表示で食品事業者に求められていること
https://www.sujahta.co.jp/analysis/c_06.html#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%82%92,%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%92%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
・アレルゲンフリーの表示について
https://www.label-bank.co.jp/blog/allergy/201512allergy
・アレルゲン除去食品ってなに?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/assets/food_labeling_cms206_20231023_01.pdf
・輸入食品の「グルテンフリー」表示について
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/gluten_free201607
・グルテンフリーについて
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/201905gluten-free
・グルテンフリーとグルテンフリー食品が必要な人
https://www.nippn.co.jp/BrandB/eiyou/column/25.html
⑧ グルテンを含まない「米粉パン」とは?
健康や美容の面から最近注目を集めている「米粉パン」。
その製法や食感など、小麦粉を使ったパンとの違いについて調べてみました。
米を細かく砕いた米粉は、粒子が細かくさらっとしており、水に溶けやすくだまになりにくい特徴があります。
グルテンを含まないため、小麦粉ほどふくらまず、水分を多く含みしっとりもちもちした食感になります。
小麦粉パンに比べ咀嚼する回数が多いので満腹感が得やすく腹持ちが良いのが特徴です。
米粉パンはグルテンアレルギーの人でも安心して食べることができますが、中には小麦のグルテンを添加してつくられているものもあるため、気になる場合はしっかり確認する必要があります。

<参考サイト>
・グルテンフリーで注目される米粉パン!小麦粉との違いを解説
https://koki.company/blog/detail.html?1691370032
・米粉パンの特徴とは?メリットやデメリットもご紹介
https://www.kobeseika.ac.jp/contents/boulanger/rice_flour_bread/
⑨ パンに似ている日本の郷土料理
小麦粉を使った郷土料理は日本各地にありますが、その中でも、生地を練って重曹やベーキングパウダーを加え発酵させて蒸したり焼いたりしてつくる、パンに似た食べ物について、いくつか調べてみました。
【がんづき】(宮城県・岩手県)
小麦粉、ベーキングパウダー、黒砂糖、水だけでつくるシンプルな蒸しパン。
その名は、雁(がん)の肉に似ていることに由来するとされる。
おやつや軽食、また農作業の合間に小腹を満たすために食べられてきた。

※写真はPhotoACより「仙台の「がんづき」」
【小麦まんじゅう】(埼玉県・栃木県)
かつて埼玉県では米の裏作として小麦栽培が盛んで、小麦粉を使ったうどんやお菓子が伝承されてきた。
小麦粉に砂糖、牛乳、重曹、ベーキングパウダー、卵を混ぜ合わせて生地をつくり、小豆あんを包んで蒸した小麦まんじゅうは、七夕やお盆、十五夜などの行事に仏様にお供えする菓子だった。
栃木県は日本有数の麦作地帯で、お盆の前に挽きたての小麦粉が出回るので、お盆の行事時には小麦まんじゅうが食されてきた。
小麦粉と砂糖、重曹でつくった生地であんを包み蒸し上げる。
【焼きまんじゅう】(群馬県)
群馬県では小麦の生産がさかんで、小麦を使った郷土料理も多い。
小麦粉やもち米にどぶろくを加えて発酵させ、蒸してまんじゅうにし、さらに竹串に刺して味噌だれをつけ焼き上げる。
お花見や夏祭りなどの際に食されている。
【炭酸まんじゅう】(群馬県)
小麦粉と重曹、ベーキングパウダー、砂糖を使って生地をつくり、あんを包んで蒸し上げる。
中に高菜やおからなどのおかずを入れて惣菜風にするケースも見られる。
季節行事のおもてなし料理や、農作業の間食、農作業がひと段落した時のご褒美として食べられてきた。
【ばらっぱまんじゅう】(千葉県)
小麦粉にふくらし粉と砂糖を混ぜて生地をつくり、濡れ布巾をかけて数分寝かせ、あんを包んで蒸し上げる。
夏祭りやお盆などのハレの日に食べられている。
【かんこ焼き】(神奈川県)
江戸時代から相模原市津久井地域に伝わる郷土料理。
稲作に適さない山間地で、古くから麦や豆が栽培され、小麦を中心とする粉食文化が根付いている。
小麦粉でつくった生地を少し発酵させ、小豆、かぼちゃ、フキなどの山菜、しめじなどのキノコ、クリ、切り干し大根、漬物など季節の食材を具として包み、軽く焼いたあとに蒸しあげる。昼食やおやつに親しまれている。
【石垣団子】(神奈川県)【石垣もち】(大分県)
火山灰に覆われやせた土地が多かった神奈川県相模原台地では、麦やさつまいもが多く栽培されてきた。
「石垣団子」は、皮をむいたさつまいもをサイコロ状に切り、小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖、塩を混ぜた生地に入れて丸め、蒸し上げる。
農作業の軽食として食べられてきた。
サイコロ状のさつまいもが石垣のように見えることからその名がついたとのこと。
大分県では小麦などの穀物栽培がさかんであったことから、小麦粉を使った郷土料理や菓子が浸透している。
「石垣もち」は、小麦粉とさつまいもだけを使ったシンプルなものや、地域によってはベーキングパウダーを加えてふんわりした食感を出すものもある。
【ほたようかん】(徳島県)
小麦粉と黒糖、重曹、ミョウバンでつくる生地の、蒸しパンのようなお菓子。
中に空洞ができていることを徳島の方言で「ほた」と呼び、ふわふわとしたスポンジのような見た目からその名がついたとのこと。
農作業の間食としてや、豊作を祝うものだったそう。
【みとりまんじゅう】(福岡県)
福岡県は小麦の生産が盛んで、小麦粉は身近な食材として用いられてきた。
小麦粉と砂糖、重曹を混ぜ合わせた生地であんを包み蒸し上げる。蒸した時に生地がふくらんで、きれいな丸い形になる。
今でもお盆につくられ、仏様にお供えされたり近所の親戚に配ったりする風習が残っている。
【ふくれ菓子】(鹿児島県)
鹿児島では江戸時代から黒糖が甘味料として強く根付き、黒糖を使った様々な郷土料理が生まれている。
小麦粉と重曹、溶き卵、粉黒糖、はちみつ、酢、水を混ぜ合わせ、蒸し上げる。
温かいとふんわりした食感で、冷めるともっちりとした食感になる。
かつては豊作を願う祭りの席や、農作業時のお茶うけとして食べられていたとのこと。
近年は郷土菓子として注目され、専門店などもできている。

※写真はPhotoACより「鹿児島県の郷土菓子 ふくれ菓子」
【げたんは】(鹿児島県)
かつて米の集荷地であった横川町(現・霧島市)に集まる人をもてなすための、お茶うけとしてつくられた。見た目が泥に汚れた下駄の歯に似ていたことからその名がついたという説があり、また「三角菓子」とも呼ばれていたとのこと。小麦粉と重曹、黒糖を混ぜ合わせた生地をオーブンで焼き、二等辺三角形になるように切って、黒糖の蜜にくぐらせて食べる。表面は黒糖の蜜のシャリッとした食感、中はしっかりとしたかたい生地で、時間とともに黒糖の蜜が染みこんでいく。

※写真はPhotoACより「げたんは 鹿児島名物 郷土菓子」
<参考サイト>
・農林水産省 うちの郷土料理
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html
⑩ 《美味しい素麺》手延べ乾平うどん 編
「手延べ乾平うどん」とは、小豆島の「手延べ素麺」の製法を生かしてつくられた「手延べうどん」です。
生地を“のばして”麺にするので包丁切りの手打ちうどんと違い、なめらかで角のない舌触りと、ツルツルとしたのど越しが特徴です。
さらに「手延べ乾平うどん」は麺を平たくすることで、スープや出汁に絡みやすくなり、美味しく召し上がっていただけます。
また、夏にお召し上がりいただくのにピッタリな、茹で時間が短めの「手延べうどん」です。
石井製麺所のイチオシの夏うどんと言えば、お家カレーを使ったカレーうどんです。
夏に食べるカレーうどん、美味しいですよね。
ぜひご自宅のカレーでお試しください。
もちろん、温冷どちらでも美味しく召し上がっていただけますので、お出汁を利かせためんつゆで、冷やしうどんとして召し上がっていただいても◎。
煮崩れしにくいので、温かいお出汁やスープと一緒に「豚キムチ鍋うどん」も暑い日にはおすすめです。
ドレッシングをサ〜ッとかけて、豚しゃぶサラダうどんもいかがでしょうか。
賞味期限は約1年となっていますので、備蓄食としてもぜひご活用ください。

《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/
《手延べ乾平うどん》 https://141seimen.thebase.in/categories/5913110
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.35
栄養成分の機能性について/多量ミネラル
早いもので、長野での催事から約1カ月。
普段、自社工場内で作業をしています(地域の寄り合いや近くのお店や会社への配達はあります)が、催事で直接お客様と相対して販売の機会を得ることは大きな学びと、マーケティング戦略に繋がる気づきがあると感じます。
例えば今回の催事でも勝手に、「信州の方は美味しい『蕎麦』を食べておられるので、『素麵』にはご興味が薄いのではないか」と不安を感じておりましたが、「外で食べるなら『蕎麦』、家で食べるなら『素麵』」という方も多く、とてもホッとしたのを思い出します。
何事も向かい合って、きちんとお話をお聴きしてみないと分からないものですね。
これからも思い込みを持たずに、しっかりお客様とお話しさせていただきたいと思いました。

さて、GWも明けていよいよ本格的な夏が近づいてまいりました。
現在は定期的に雨の恵みがある小豆島ですが、オリーブの木も花を付け、まさに今が見頃です。
この時期が来ると、石井製麺所でも益々忙しさが増してきます。
いつもはGW明けに夏の素麺のご案内をお客様へお出ししていますが、今年は催事もあり、少し出すタイミングが遅くなりました。
古くからのお客様からは、「今年の案内はまだですか?」とお声もいただきながら、家族総出で封筒にご案内を詰めて準備させていただきました。
ただ、まだ石井製麺所を知って間もないお客様に対しては、少し早いのではないかなと感じる部分もあります。
やはり暑さを実感する気候になってからが、お客様にも喜ばれるでしょうか。。。
そのあたり、ご意見ございましたらぜひお聞かせください。
暑さで汗がしたたり落ちるくらいの季節に皆さまには、弊社の素麺を美味しく召し上がっていただけることを願っております。
ところで、暑くなって汗をかく季節には熱中症対策としても、塩分やミネラルの補給など注意が必要といわれます。
でも、塩分は「血圧が気になるから」と摂取を控える方もいらっしゃると思います。
素麵をつくる際にも塩は欠かせないのですが、その塩分を気にされる方もいらっしゃいました。
しかしながら素麵の場合は、茹でる際に塩分はほとんどがゆで汁に溶け出してしまうため、素麵自体に含まれる塩分量はほとんど無くなってしまいます(とはいえ、一緒に付けるめんつゆの塩分はあるので漬け過ぎには注意が必要ですが)。
夏場は特に(?)身近で、よく聞く「ミネラル」という言葉ですが、食事と切っても切り離せない大切なもののようです。
この季節、気になるミネラルについて調べてみましたので、今回も最後までお付き合いただけましたら幸いです。

【目次】
① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?
② 「多量ミネラル」それぞれの働きについて
③ 人体に不可欠な「塩」の働き
④ 熱中症を防ぐためにも欠かせない「水分」と「ミネラル」補給
⑤ 手延べ素麵作りに欠かせない「塩」の役割とは
⑥ 素麺を食べても塩分の取り過ぎにならない理由
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》毎日の健康を考えた長命草セット 編
① 身体に必要な栄養素・ミネラルとは?
ミネラルは、身体にとって重要な役割を担っている五大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)の1つで、身体にごく微量に存在しています。
「無機質」とも呼ばれます。
人体の約95%は主要4元素(酸素、炭素、水素、窒素)で構成されており、残りの約5%はミネラルで構成されます。
ミネラルは自然界に100種類以上存在しており、その中でも体内でさまざまな働きをする栄養素で通常の食事からでは不足しがちなものを「必須ミネラル」と言います。
現在、必須ミネラルは16種類とされ、このうち13種類について厚生労働省が摂取基準を定めています。
ミネラルは体内で合成できないため食物として摂る必要があります。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、
◎1日の推奨量や目安量が約100mg以上のミネラルを「多量ミネラル」
種類:ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン
◎1日の推奨量や目安量が100mg未満のミネラルを「微量ミネラル」
種類:鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン
と分類しています。
ミネラルが不足すると欠乏症やさまざまな不調が発生しますが、摂りすぎた場合にも過剰症や中毒を起こすものがあります。

<参考サイト>
・身体の調整に欠かせない栄養素~ミネラル~
https://www.mpc-lab.com/blog/20200619#:~:text=%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%86%E3%81%88%E3%81%A7%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%AC%A0%E3%81%AA%E8%BA%AB%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%80%82&te
・e-ヘルスネット ミネラル
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-035.html
・ミネラルの種類とそれぞれの働きを解説!ミネラルを含む食べ物も紹介
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=249&category=health#:~:text=%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%92%E3%83%88%E3%81%AE,%E3%81%AB%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%84%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E3%81%A7%E
・ミネラルとはどのような栄養素?種類別の働きについて解説
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/6010/
・ミネラル類
https://himitsu.wakasa.jp/contents/minerals/
② 「多量ミネラル」それぞれの働きについて
5つの「多量ミネラル」それぞれの働きや過不足による影響について、調べてみました。
【ナトリウム】
食塩の成分でもあり、体内では主に細胞外液に存在し、体液の浸透圧を調節して、胆汁・膵液・腸液などの材料となる重要な成分のひとつです。
ですが、古くから日本人の食事は食塩を含む醤油や味噌などの調味料で味付けしてきており、日本人はWHOが示す食塩摂取量1日5gよりも多く摂取する傾向があるそうです。
食塩などのナトリウムを摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が高くなり、それが中枢神経に働いてのどが渇き、人は水分を摂ります。
水分を摂ると血管に流れる血液量が増え、血圧が高くなるため、高血圧につながります。
またナトリウムの摂りすぎは胃がんなどのリスク上昇の要因となるため、摂取量に注意が必要です。
ナトリウムは、塩、しょうゆ、みそなどの食塩(塩化ナトリウム)を含む調味料の他、ハム、ウインナー、練り製品、即席めんなどの加工食品や野菜の漬け物などにも多く含まれています。
また、うま味調味料などの食品添加物の多くには、グルタミン酸ナトリウムなどのナトリウム塩の形でナトリウムが含まれているそうです。

【カリウム】
野菜、芋、果物などの植物性食品に多く含まれます。
細胞内液の浸透圧のバランスを保つ、神経や筋肉の興奮伝導を調節する、などの働きがあります。
ナトリウムを体外に排出する働きがあり、血圧を正常に保つ働きが期待される一方で、腎機能が低下している場合など、カリウムの摂取量に注意が必要な場合もあるそうです。
カリウムは、ほとんどの細胞の中に存在することから広く食品に含まれますが、特にバナナ、メロン、アボカドなどの果実類、ほうれん草などの野菜類、さつまいもなどのいも類、大豆や小豆などの豆類、魚類、肉類に多く含まれています。

【カルシウム】
乳製品や小魚などに多く含まれ、骨や歯を構成する成分。
また一部のカルシウムは、血液や神経、筋肉内で「カルシウムイオン」として存在し、心筋の収縮作用を増やして筋肉の興奮を抑制する、血液を凝固させする、などの働きを持ちます。
不足すると、骨粗しょう症やイライラの原因の1つとなります。
日本人の食生活では不足しがちなので、積極的に摂りたい栄養素です。
カルシウムは、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚、豆腐や納豆などの大豆製品、野菜類や海藻などに多く含まれます。
なかでも、牛乳や乳製品は、他の食品に比べてカルシウムの吸収率が高いうえに、1回の摂取量も多いので、効率よくカルシウムが摂れるそうです。

【マグネシウム】
ナッツ類や魚介類、精製していない穀物などに多く含まれ、骨や歯の形成に関わり、体内のさまざまな代謝をサポートしています。
体温・血圧を調節するほか、神経情報の伝達や筋肉の収縮などにも関わっているそうです。
不足すると、動脈硬化や狭心症、心筋梗塞や筋肉のけいれん、神経過敏症などの症状を引き起こします。
また、骨粗しょう症や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まります。
マグネシウムは海水に多く存在しているため魚介類や海藻類に多く含まれます。
その他にも穀類、野菜類、豆類などにも含まれ、香辛料などにも含まれています。
ナッツの中でマグネシウムが一番多いのはかぼちゃの種で100g中530mg含まれているそうです。

【リン】
骨や歯を構成する成分で、細胞の浸透圧やpHバランスを保つ作用などもあります。
さまざまな食品に含まれ、ハムやソーセージなどの加工品にも添加されており、一般的な食事をしていれば不足することはほとんどないそうです。
摂りすぎるとリンの濃度を調節するホルモンを分泌する器官に異常が起こることがあります。
リンは、ハムやソーセージをはじめ、練り物、インスタント麺などの加工食品にも含まれるそうです。
また、肉や魚、卵、乳製品、豆類など、たんぱく質の多い食品に多く含まれているそうです。

<参考サイト>
・減塩食について
https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/low-salt/#:~:text=%E9%A3%9F%E5%A1%A9%E3%81%AF%E8%A1%80%E5%9C%A7%E3%81%A8%E5%AF%86%E6%8E%A5,%E8%A1%80%E5%9C%A7%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
③ 人体に不可欠な「塩」の働き
人間が生きていくうえで大切な働きをしている「塩」は、体内でナトリウムイオンと塩化物イオンに分かれて存在しており、いろいろなシステムの働きを守り、維持する役割を果たしています。
体内の塩分量は、大人で体重の0.3~0.4%、子供では約0.2%とされています。
例えば体重60kgの人の体内の塩分量は約200gということになります。
【細胞を正常に保つ】
人間の体を構成する細胞は、細胞外液という液に囲まれています。
塩はイオンの状態で細胞外液に多く含まれ、細胞外液の量を維持しています。
このことにより、全身の細胞に酸素や栄養分が運ばれたり、二酸化炭素や老廃物が肺や腎臓に運ばれ排出されたりします。
また、細胞外液の濃度を調整し、バランスを一定に保つことで、細胞の働きを支えています。
【消化や吸収を助ける】
体内の塩化物イオンは胃酸の主成分となり、胃で食べ物を殺菌したり、消化を助けたりしています。
ナトリウムイオンは小腸で、アミノ酸やブドウ糖などの吸収を助けています。
【情報を脳や体に伝える】
神経細胞は、ものを触ったときなどの刺激を脳に伝える、脳から体を動かすように筋肉に命令を伝える、などの働きをしています。
神経細胞が刺激や命令を伝えるときに必要となるのがナトリウムイオンです。

<参考サイト>
・塩と健康の関係
https://www.nihonkaisui.co.jp/small_customer/learning_salt/health
・体内の塩
https://www.shiojigyo.com/siohyakka/about/human/inside.html
・塩とからだの大事な関係
https://www.shiotokurashi.com/life
④ 熱中症を防ぐためにも欠かせない「水分」と「ミネラル」補給
私たちの体は、暑い時には汗をかいて熱を放出し、体温を調整しています。
夏は汗で水分が失われがちになります。
水分不足になると、発汗機能がうまく働かず体温が急激に上昇し、血液は濃縮され流れが悪くなり、脳への血流が低下して熱中症を引き起こします。
体重の約1%の水分を失うと脱水状態になり、4~5%失うと体温上昇に加え吐き気やめまいなどの症状が現れるそうです。
脱水症状は、脳梗塞や心筋梗塞の発症を引き起こすこともあります。
血液がドロドロになり、熱を放出するために血管が拡張することで血圧が低下し、血液の流れが遅くなり、脳や心臓の血管に血栓が詰まりやすくなるそうです。
汗をかくと、水分だけでなくナトリウムやカリウムなど水溶性のミネラルが排出されてしまいます。
水分補給が大切ですが、水分を一度に大量に摂ると、体内でのミネラルバランスが崩れてしまうこともあります。
暑い時期は食欲が落ちて食事から必要な栄養素をしっかり摂れていない場合もあり、特にミネラル不足に注意が必要です。
ナトリウムが不足すると血圧低下や循環血液量の低下の原因になり、カリウムが不足すると夏バテを引き起こすとされています。
日本人はナトリウムを多く摂りすぎる傾向にあるので、汗で失われた塩分を補給する時は、ナトリウムの摂り過ぎによる血圧上昇を抑える働きのあるカリウムを一緒に摂ることを心がけると良いそうです。

<参考サイト>
・高温多湿の夏は、思わぬ“脱水症状”に注意!
https://www.shaho-net.co.jp/healthup3/summer.html
・発汗により失われる水溶性ミネラル・ビタミンと欠乏症
https://www.kes-eco.co.jp/safety-report/269
・夏バテ防ぐミネラル補給 しっかり3食、バランス重視
https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXKZO45767350W9A600C1W10600/
・夏のミネラル補給
https://kenko.sl-creations.co.jp/column/column61.html
⑤ 手延べ素麵作りに欠かせない「塩」の役割とは
素麵は小麦粉を塩水で練り合わせてつくります。
昔は経験知から来るものだと思われますが、現代では塩を入れる理由としては、科学的根拠が証明されているようです。
特に①番は、素麺づくりの極意の部分で、小麦の種類、気温、湿度、水の量にあわせて、毎日毎回微妙に調整しながら製麺しています。
これが、もっと“見える化”させることができれば、“間違いの無い”美味しい素麺が安定してつくれると思うのですが。。。その日が来るように、今はしっかりと先代の作り方を学んでおります。
美味しい素麺をつくるために不可欠な「塩」であることを、改めて認識することができました。
① グルテンを引き締める
麺のコシの元となるグルテンは、小麦粉のたんぱく質が水と合わさることで形成されます。
生地をこねて引きのばすことにより、グルテンが何層にも重なった地層のように組織されます。
塩には、このグルテンを強く引き締める働きがあります。
夏は気温が高く、生地がだれやすくなるので塩を多くし、逆に冬は生地が硬くなるので塩を減らす、といったように、季節や天候などにより塩分濃度の微調整が必要です。
まさに、良い塩梅が美味しい素麺に不可欠なのです。
② 酵素の活性を抑制する
塩が小麦粉に含まれるたんぱく質分解酵素の働きを抑えることで、生地がじっくり熟成され、より弾力が増します。
③ 保存期間を長くする
雑菌が繁殖しにくくなり、保存性が向上します。
④ 乾燥を防ぐ
塩には吸水性があり、水分を蓄えようとします。
熟成を繰り返しながら麺を細く延ばしていく手延べ製法において、塩は急激な乾燥によるひび割れを防ぎ、表面をなめらかに仕上げるのに役立ちます。
⑤ ゆで時間を短縮する
ゆでる時に、麺に含まれている塩がお湯の中に溶けだし、お湯が麺の中に入り込んで、でんぷんが糊化します。
塩を多く含んでいれば、それだけ早くゆで上がることになります。
⑥ 味を良くする
ゆでることで塩分の多くは溶け出しますが、わずかに残った塩味が、麺の風味や旨みを引き立てます。

<参考サイト>
・うどんに塩を入れる理由
https://www.flour.co.jp/news/article/111/
・手延べそうめん、うどんの副原料
https://www.shimabara-soumen.com/article/14245881.html
・うどんと塩
https://www.nichimen.or.jp/know/zatsugaku/19/
⑥ 素麺を食べても塩分の取り過ぎにならない理由
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、食塩摂取の目標量(食塩相当量として)は、成人1人1日当たり男性7.5g未満、女性では6.5g未満と設定されています。
素麵の製麺時に加えた「塩」は、茹でる際にその役目を果たして、最終的にゆで汁に溶け出します。
素麵の「栄養成分表示」では、食塩相当量4.1gと記していますが、ゆで上げ後の食塩相当量は0.4gとなります。
さらに水洗いすることでも塩分が抜けます。
素麺は塩分の多い食品ではないといえると思いますので、どうぞ安心してお召し上がりください。

<参考サイト>
・厚生労働省 e-ヘルスネット「ナトリウム」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-024.html#:~:text=%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E6%91%82%E5%8F%96,%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
・文部科学省 食品成分データベース
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
・そうめんの塩分量は多い?少ない?塩分を控えめにしたおすすめレシピ
https://dime.jp/genre/1405923/
・「そうめん」の塩分量はどれくらい?管理栄養士が教える減塩のコツ3つ
https://macaro-ni.jp/109133?page=2
⑦ 《美味しい小豆島の食財紹介》毎日の健康を考えた長命草セット 編
「1株食べれば、1日長生きする。」
そう言い伝えられ、古くから人々の健康を支える野菜として親しまれてきた長命草(ちょうめいそう)。
その名前のとおり、食べる人の健康長寿を支える可能性を秘めた“パワーベジタブル”です。
「しょうどしま長命草」は、小豆島の特産品である醤油の絞り粕を肥料に、
農薬を使わずに栽培された、小豆島育ちの健康野菜です。
そのしょうどしま長命草を丸ごと粉末化したパウダーは、長命草の栄養価をそのまま摂り入れられ、さまざまなお料理にも活用できる微粒粉末です。
三代目はパン作りが趣味なので、よく食パンに混ぜて使っています。
ホットミルクに混ぜると抹茶風味に、冷たいアイスクリームや、ヨーグルトに1杯入れる健康習慣、いかがでしょうか。
しょうどしま長命草素麵は、無添加・無着色にこだわっています。
また、普通の素麵とは製法が若干異なるため、独自製法によりゆっくり丁寧に手延べ製法で仕上げています。
めんつゆで召し上がっていただいても美味しいですが、香草のような風味を生かして、コンソメスープに入れてみたり、ナンプラーで味付けをしたフォー風アレンジもオススメなんです。
暑くてあっさりしたものを食べたくなりますが、そういうときこそ、健康面を考えた健康麺で暑い夏も元気にお過ごしください。
《毎日の健康を考えた長命草セット》 https://141seimen.thebase.in/items/55455003
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.34
麺究者への道/味噌について研究してみる
今、このブログを仕上げているのは、催事真っ最中の長野の空の下です。
ブログ自体は、少しずつ書きためているのですが、ブログの導入部分は最終仕上げなので、いつも後回しになっています。
催事のための準備にも追われ、なかなか仕上げが出来ず、逆に、催事中のホテルの中で、作業をおこなっています。
まあ、他にすることもないので、のんびりと書いています。
さて、今回のブログでは発酵食品の代表格である、味噌について調べた物を綴りました。
醤油や素麺よりも遙か昔から日本人に愛用されてきた食品のためか、本当に多様性に富み地域に根付いた“らしさ”のある味噌が多く見受けられました。
中でも気になったのは、愛知県の「八丁味噌」。
ご存じでしたか?
「八丁味噌」については、GIという商標的な認可で、近代的な製法をおこなう組合に所属する会社と古くからの製法を続ける会社との間で、「どちらが、八丁味噌ブランドなのか?」という点でトラブルとなり、古くからの製法を守り続ける会社が負けるというショッキングなニュースが、まさに最近ありました。
この事件があったから味噌を調べたわけではありませんが、ある意味、小豆島手延べ素麺でも、起こりえる問題だなと考えさせられるニュースでした。
今回のブログでは、いつものように味噌の歴史やその広がり、種類や地域性について調べてみました。
調べる内に味噌はとても優れた健康食で、こんなにも愛される食品なんだと、改めて気付かされました。
その味噌の良さを皆さまにお伝えすることが出来れば幸いです。
今回も最後までお付き合いの程、どうぞよろしくお願いいたします。
 ◎4月24日(水)ながの東急様地下1階の催事場から、催事の準備を終えて。
◎4月24日(水)ながの東急様地下1階の催事場から、催事の準備を終えて。
【目次】
① 高級品から、武将に重宝され、庶民の味へ
② 味噌の味と熟成の関係とは?
③ JAS規格ができたばかりの味噌。麹・味・色による分類とは?
④ シンプルな原料で、発酵・熟成を経てつくられる味噌
⑤ 地域特性の多様さが多彩な味噌をつくる
⑥ 味噌問題勃発?!
⑦ 発酵過程で栄養価アップ!味噌の健康作用
⑧ ご当地味噌を使った郷土料理も多種多様
⑨ なめ味噌や、海外の味噌に似た調味料とは?
⑩ 《美味しい素麺》手延べ黒ごま麺 編
① 高級品から、武将に重宝され、庶民の味へ
味噌は、大豆や麹、塩などを発酵・熟成させてつくる日本の古来からの発酵調味料です。
そのルーツについては、中国もしくは朝鮮半島経由で伝わったという説と、弥生時代から日本独自の塩蔵を経て発展したという説があるそうです。
中でも有力なのが、中国で生まれた、肉や魚を塩で漬けて発酵させた「醤(ひしお)」や、大豆や雑穀と塩を合わせて発酵させた「豉(くき)」が、日本に伝わり独自の発展を遂げたという説です。
奈良時代、701年に完成した「大宝律令」に「未醤」という文字が書かれており、「みしょう」 から 「みしょ」 、「みそ」へと変化していったと考えられています。
平安時代に初めて「味噌」という文字が文献に現れ、「延喜式(えんぎしき)」という法典では貴族の給与や贈答品として使われていたという記述があります。
当時は寺院や貴族階級のみが食することのできる貴重な高級食材で、おかずとしての「なめ物」だったようです。
鎌倉時代には、中国からの僧の影響ですり鉢が広まり、粒味噌をすりつぶしたものを使った味噌汁が誕生したとされています。
これにより、禅宗の質素倹約の食事である「一汁一菜」の形態が、鎌倉武士の食事の基本として確立されたそうです。
室町時代には大豆の生産量が増え、農民が自家製の味噌をつくるようになり、保存食として庶民にも浸透しました。
味噌汁以外の料理も、室町時代に生み出されたそうです。
戦国時代には武将たちが戦陣食として味噌を用いました。
貴重なタンパク源として、干したり焼いたりして携帯しやすくしていたそうです。
江戸時代、江戸の人口が増え、三河や仙台から味噌が江戸に送られるようになりました。味噌汁が庶民の味となり、味噌が生活に根付いていきました。
昭和時代、味噌の容器が樽からカップへ変化し、だし入り味噌が登場するなど、社会変化に合わせて進化していきました。

<参考サイト>
・味噌のきほん
https://www.hakko-blend.com/study/hakkofood/02.html#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%81%AB%E3%82%82%E3%80%8C%E8%B1%86%E6%9D%BF,%E3%81%9F%E8%AA%BF%E5%91%B3%E6%96%99%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
・マルコメ 味噌のこと
https://www.marukome.co.jp/miso/
・味噌 特定非営利活動法人 うま味インフォメーションセンター
https://www.umamiinfo.jp/richfood/foodstuff/miso.html
・みそ(味噌)を知る イチビキ
https://www.ichibiki.co.jp/enjoy/knowledge_miso/
・みその豆知識 かねこみそ
https://kanekomiso.co.jp/knowledge/knowledge-of-miso/#section1
・味噌 ひかり味噌
https://www.hikarimiso.co.jp/enjoy-miso/encyclopedia/type.html
② 味噌の味と熟成の関係とは?
味噌の旨味は、大豆タンパクが分解されてできるアミノ酸(主にグルタミン酸)に影響され、熟成の進んだものほど旨味が強くなります。
さらに塩味や酸味、甘味が調和し、良い香りと適度な粘度が加わって形成されるそうです。
また熟成が進むと舌に感じる刺激が和らいで伸びとコクのある味わいになるとのことです。
味噌は仕込み初期には塩辛く感じられ、熟成するにつれて、塩分濃度は同じですが塩辛味が減少します。
この現象を「塩なれ」といい、乳酸やペプチド、アミノ酸など、酸味や旨味成分の影響を受けた結果起こるものだそうです。
味噌の甘味は、麹が多いほど強くなります。
これは、米や麦のデンプンが麹のアミラーゼにより糖に分解されるからとのことです。
熟成期間が長くなると、糖分は酵母や乳酸菌により消費されるため減少するそうです。

③ JAS規格ができたばかりの味噌。麹・味・色による分類とは?
味噌にはとても多くの種類があり、その多様性に対して規格を設けるためのグループ分けが困難といった理由により、「日本農林規格(JAS)」でも明確な基準がありませんでした。
2022年3月、味噌の海外市場における競争力の強化や日本からの輸出拡大などを目的としてJAS規格が制定されました。
日本独自の伝統的な生産方法として、①こうじ菌は「Aspergillus oryzae(アスペルギルス・オリゼー)」に限定②こうじは「ばらこうじ」または「豆こうじ」に限定、という、主に2つの基準を定めています。
味噌は「麹の種類」「味」「色」により大きく分類することができます。
【麹の種類による分類】
味噌は大豆と塩、そして麹でつくられます。主に3種類の麴が使われています。
<米味噌>
「米麹」を原料に使用した味噌で、国内生産量の約80%を占める。「赤味噌」や「白味噌」も、米味噌の一種。塩味と酸味があるのが特徴。

<麦味噌>
大麦やハダカムギを使った「麦麹」でつくる味噌。田舎味噌とも呼ばれ、熟成期間が短い。麦特有の香ばしさがあり、さっぱりとした甘味が特徴。生産量は全国の約5%で、主に九州・四国・中国地方でつくられている。

<豆味噌>
蒸した大豆に麹菌を付けた「豆麹」を使用する味噌。
赤黒い色で、渋みや酸味の強い個性的な味わい。生産量は全国の約5%で、主に愛知県、岐阜県、三重県でつくられている。

<調合味噌(合わせ味噌)>
米味噌、麦味噌、豆味噌を混ぜたものや、醸造段階で米麹と麦麹を合わせてつくるものなど、2種類以上の味噌を組み合わせた味噌。生産量は全国の約10%。
【味による分類】
塩味の強さにより分けられます。また塩分が一定なら、「麹歩合」(原料の大豆に対する米や麦の比率)が高いほうが、甘味が強くなります。
<甘味噌>
塩分濃度5~7%程度。関西地方で食べられる「白味噌」や、東京の伝統的な「江戸甘味噌」など。
<甘口味噌>
塩分濃度7~11%程度。流通している多くの味噌がこれに分類される。文字通り甘いものから、甘じょっぱいと感じるものまで幅広い。
<辛口味噌>
塩分濃度11~13%程度。もっとも塩味が強く、すっきりした味わいが特徴。かつては主流だったが、現在では主に北の地域でつくられている。
【色による分類】
味噌は主に熟成期間によって色が変わります。
短いと白っぽく、長くなるにつれて淡色、赤色になり、長期熟成になると黒っぽく変化していきます。
発酵・熟成中に、原料の大豆などに含まれるアミノ酸が糖と反応して褐色に変化する「メイラード反応」が起こることにより色が変化します。
完成してからも熟成が進むため、時間が経つにつれて味噌の色は濃くなっていきます。
<白味噌>
熟成期間約1カ月。甘味の強い白味噌が一般的で、塩分が高めのものもある。
<淡色味噌>
熟成期間約4~8カ月。全国的に流通しており、スーパーなどでよく見かける味噌。
<赤味噌>
熟成期間1年以上。色が濃く、中には黒色に近いものもある。

<参考サイト>
・味噌をもっと楽しもう~味噌の分類~
https://misovation.com/blogs/journal/types-miso#link3
・いろいろなJAS認証 みそ
http://jascert.or.jp/veriousjas/miso/
④ シンプルな原料で、発酵・熟成を経てつくられる味噌
味噌がどのようにつくられているか調べてみました。
最も多く食べられている米味噌を例にご紹介します。
【大豆を洗い、水に浸す】
乾燥させた大豆をよく洗い、一晩以上水に浸漬させる。水をたっぷり含んだ大豆の水を切り、温める。
【蒸したり煮たりして、冷ます】
水で戻した大豆を、高温・高圧で、短時間で蒸し上げてやわらかくし、しっかり冷ます。
【米を蒸して種麹を付ける】
洗って水に浸漬した米を蒸し上げ、広げて少し冷ます。種麹をまんべんなく振りかけ、温度・湿度管理をしながら麹菌を繁殖させる。
【原料を混ぜ合わせ、仕込む】
大豆を細かくつぶし、米麹と塩、水を加えてよく混ぜ、容器に仕込む。
【発酵・熟成させる】
仕込んだ味噌を発酵・熟成させることにより、風味豊かな味噌が出来上がる。
<発酵>
麴菌が持つアミラーゼが米のデンプンを分解してぶどう糖(グルコース)に、プロテアーゼは大豆のタンパク質を分解してペプチドやアミノ酸にする。
<熟成>
発酵過程でできたブドウ糖から、酵母によるアルコール発酵や乳酸菌による乳酸発酵により酸味や香り成分がつくられる。

※写真はPhotoACより「味噌蔵」
⑤ 地域特性の多様さが多彩な味噌をつくる
味噌の発酵・熟成は微生物の働きによるもので、微生物の働き方は気候風土、環境、水質などさまざまな条件によって変わり、蔵によっても違いがあります。
また、それぞれの地域の原料事情や食習慣、嗜好に合わせて、多彩な味噌がつくられています。
各地で食べられている個性豊かな味噌について、調べてみました。
※各味噌紹介でのお料理写真は、必ずしも地域の味噌を使用した物かどうかは分かりませんが、その地域の味噌を使ったお料理をご紹介しています。なお、次の項目でも地域に根付く味噌を使った郷土料理をご紹介しています。予めご了承ください。
【北海道味噌】(北海道)
さっぱりとした味わいで、食材の風味を活かしてくれる。昔から新潟や佐渡との結びつきが強かったことから、越後味噌や佐渡味噌と似ている。

※写真はPhotoACより「北海道の味噌ラーメン」
【津軽味噌】(青森県)
麹歩合が低く塩分が高めの長期熟成の赤色辛口味噌で、「津軽3年みそ」と言われる。かつて凶作が頻発することから、ききんに備えて長期保存できるみそづくりが盛んになったと言われている。

※写真はPhotoACより「青森貝味噌焼き」
【仙台味噌】(宮城県)
戦国時代、伊達政宗は味噌を兵糧として製造したとされる。軍用だけでなく産業発展のために良質なみそづくりを続けたと言われる。当時から伝わる伝統的な長期熟成型の味噌。

※写真はPhotoACより「仙台味噌の焼きおにぎり」
【会津味噌】(福島県)
会津盆地の寒暖差の大きな厳しい気候の中でつくられる、300年の歴史を持つ長期熟成型の赤色辛口味噌。

※写真はPhotoACより「しんごろう」
【信州味噌】(長野県)
生産量日本一で、全国で生産・消費される味噌の約40%を占める。武田信玄の時代、大豆栽培が盛んに行われ、味噌づくりに適した気候と水質もあって全域に広まったとのこと。

※写真はPhotoACより「信州味噌漬け」
【江戸甘味噌】(東京都)
米麹を多く使用し、10日ほどの短期でつくられる赤色甘口味噌。どじょう鍋などにも用いられる。濃厚な甘みと光沢が特徴。
【東海豆味噌】(愛知県、岐阜県、三重県)
中京地方を中心につくられている豆味噌で、「名古屋味噌」「三河味噌」「三州味噌」「八丁味噌」などと呼ばれる。わずかな酸味と苦味、濃厚な旨味を持つ。

※写真はPhotoACより「五平餅」
【西京味噌】(京都府)
米麹の割合が非常に高く、強い甘味があるのが特徴。懐石料理や普茶料理で必要不可欠。関西では、お正月に白味噌のお雑煮が食べられている。

※写真はPhotoACより「鰆の西京焼き」
【越後味噌】(新潟県)
上越地方では、味噌汁に米麹の粒がふわっと浮かぶことから「浮麹(うきこうじ)味噌」と呼ばれる、淡い赤色でさわやかな味わいの味噌。中越・上越地方では麹歩合が低めの、赤色で華やかな香りを持つ味噌、と地域性がある。
【佐渡味噌】(新潟県)
麹が多く使われ、長期間熟成させるため塩なれしたコク深い旨味を感じられる味噌。
【加賀味噌】(石川県)
石川県の味噌は米味噌で、加賀地方では米麹を多く使い長時間熟成させたものが多く、山吹色でやや辛口。能登地方では水分が多くてやわらかく塩辛いとのこと。
【讃岐味噌】(香川県)
麦味噌文化圏の四国の中でも、瀬戸内に面する海沿岸地域では、濃厚な甘みがある豊かな風味の、米味噌の白色甘味噌もつくられている。白味噌仕立てであん餅を入れる雑煮が食される。

※写真はPhotoACより「元旦あんもち雑煮」
【御膳味噌】(徳島県)
麹の割合が高く、豊かな旨味のある赤色甘口味噌。塩分は辛口味噌と同等ながら、中辛に位置する味わい。阿波藩主・蜂須賀公の御膳に供されたのが名前の由来とされる。
【瀬戸内麦味噌】(愛媛県)
米味噌圏と麦味噌圏が交差する地域で好まれる麦味噌。特に愛媛でつくられるものは麹の割合が高いため、麦独特の芳香と軽やかな甘味がある。
【府中味噌】(広島県)
皮を取り除いた大豆を原料とした、白やクリーム色の甘味噌。きめ細やかで豊かな風味とコクが特徴の、白色甘味噌の代表格。
【九州麦味噌】(九州地方)
九州では麦味噌が主流。温暖な気候のため、熟成期間は比較的短め。熊本県は「肥後味噌」、鹿児島県は「薩摩味噌」など昔の藩の名称で呼ばれる味噌が多くある。
<参考サイト>
・越後みその特徴
https://niigata-echigomiso.amebaownd.com/pages/3944496/page_201602191132
⑥ 味噌問題勃発?!
地域の特産品のブランド価値を高めるため、国が定めている制度に「地域団体商標制度」と「GI(地理的表示)制度」というものがあります。
うまく活用すれば消費者に品質や信頼性をアピールし競争力を高めることができる制度で、その性格や対象範囲にそれぞれ違いがあるそうです。
しかしながら、味噌に関して地域性を大切にしすぎたためか、愛知県の名産である「八丁味噌」では、登録に関して、実はGIをめぐってトラブルが発生し、訴訟問題にまで発展してしまいました。
2017年12月に、愛知県全体を生産地とし、近代的製法で生産する業者組合の「八丁味噌」について、農林水産省がGIの登録を認可しました。
これに異議を申し立てたのが、愛知県岡崎の老舗味噌会社の2業者です。
両社は、他業者が八丁味噌を製造する際「木樽で2年以上熟成させる」という伝統的な製法を継承していないことなどを理由に、国にGI登録の取り消しを求めていました。
組合に加盟していない2社だけがGIマークを商品に付けられず、著しい不利益を被る、という主張です。
結論から言うと、2024年3月、最高裁は原告側の上告を棄却し、老舗側の敗訴が確定しました。
これにより老舗側は2026年2月以降は、製品に「八丁味噌」の名称を自由に使えなくなりますが、GI登録品との混同を防ぐ表示をするなど適切に対応すれば名称を使用できる、とのことです。
地域性(多数)を大切にするのか、昔ながらの製法(少数)を大切にするのか…今後も課題となるのでしょうね。
小豆島の手延べ素麺もまさに、そういった問題が考えられるのではないかと思います。
参考までにそれぞれの制度について、調べてみました。
【地域団体商標制度】
2005年に法制化された、特許庁が審査・登録する制度で、あらゆる商品やサービスが対象となります。
特定の地域に関連する商品やサービスに対して、例えば「地域名+商品・サービスの名称」のような地域ブランドの名称を商標として登録することで、特定の団体が地域団体商標マークおよびその名称を独占して使用することができる制度です。
農協や商工会議所など地域に根ざした団体しか利用できない制度とのことです。
(例)「有田みかん」「和歌山ラーメン」「泉州水なす」
【GI(地理的表示)制度】
農林水産省が管轄するもので、農林水産物と、酒類を除く飲食料品を対象とし、2015年に制度化されました。
特定の地域で生産される農林水産物や食品について、その地域と結びついた名称を表示することにより、品質や特性を保証する制度。
約25年の生産実績を有することが求められます。
GIは地域の共有財産となります。
国際的な取り決めに基づいた制度なので、海外市場での競争力を高めることにもつながるそうです。
(例)「紀州金山寺味噌」「わかやま布引だいこん」「神戸ビーフ」

<参考サイト>
・農林水産物のブランディング ~地域団体商標とGI制度
https://www.kinokapat.jp/blog-trademark-004/
・「地域団体商標マーク」と「GIマーク」との相違点
https://www.syohyo-jp.com/mame/chiikidantai_gi.html
・【解説】地域団体商標制度と地理的表示保護制度とは?何が違う?
https://www.primeworks-ip.com/tmds/33/
・「八丁味噌」のGI登録をめぐる地元での対立構造
https://www.syohyo-jp.com/mame/8miso_gi.html
・「八丁味噌」ブランド訴訟、ついに決着 岡崎市の老舗側の敗訴が確定 「混同を防ぐ表示をすれば…」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/313755#:~:text=%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81%E3%81%8C%E5%9C%B0%E7%90%86,%E6%A3%84%E5%8D%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
・八丁味噌、老舗の敗訴確定 表示登録訴訟、名称に制限
https://news.yahoo.co.jp/articles/2fca91696892873689b8c9f8756752a55e3a3c0a
⑦ 発酵過程で栄養価アップ!味噌の健康作用
味噌の主原料となる大豆は、良質なタンパク質を豊富に含み「畑のミルク」とも呼ばれています。
味噌は発酵する過程で、アミノ酸やビタミン類が大量に生成されます。
生命維持に欠かせない必須アミノ酸9種類が、味噌にはすべて含まれているとのことです。
味噌に含まれるタンパク質は、分解されて消化吸収しやすい形となっており、他の食べ物の消化吸収を助ける働きも期待できます。
大豆に含まれる大豆イソフラボンは、骨の健康維持に役立ちます。
他にも、味噌に含まれるビタミンEやサポニン、褐色成分のメラノイジンなどには抗酸化作用があり、肝臓内の過酸化物質の増加を抑制することが確認されているそうです。
また、リノール酸やペプチド、レシチンなどの成分が含まれ、悪玉コレステロールを抑制する働きが期待でき、生活習慣病やがんのリスクを下げることが分かっています。
また、味噌に含まれる食物繊維が腸内をきれいにしたり、微生物が腸内の腐敗物や有害物を体外に送り出したりしてくれます。
まさに健康食の代表格とも言えるのが、日本で古くから愛されてきた味噌なのです。

<参考サイト>
・味噌が健康にいいのはなぜ?味噌汁を毎日の食卓に!
https://www.genmaikoso.co.jp/cultivate/web/detail.asp?id=161
・【管理栄養士執筆】味噌の栄養価まとめ 健康に良い味噌の選び方を解説
https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/miso-nutrition
⑧ ご当地味噌を使った郷土料理も多種多様
全国には様々な種類の味噌があり、味噌を使った郷土料理もバラエティに富んでいます。
代表的なものや、特徴的なものを調べてみました。
【石狩鍋】(北海道)
古くからサケ漁がさかんな石狩川で、漁師たちが暖を取るためにつくったのが発祥とされる。脂ののったサケのあらと野菜や豆腐を昆布出汁の鍋に入れ、たっぷりの味噌で味を調える。

※写真はPhotoACより「石狩鍋 土鍋」
【しょうが味噌おでん】(青森県)
極寒の冬に体を温めるため、おでんにショウガ入り味噌をかけたのが始まりとされる。津軽味噌に酒、みりん、だし汁を混ぜて煮立て、生のおろしショウガを加える。

※写真はPhotoACより「味噌おでん」
【ばっけ味噌】(宮城県)
「ばっけ」とはフキノトウを指す宮城の方言。あく抜きしたフキノトウを茹でて刻み、クルミや味噌と合わせたもの。ごはんや肉、魚、豆腐に乗せたり、おにぎりの具にしたりして食べる。

※写真はPhotoACより「ご飯のお供 ふきのとう味噌」
【じゃじゃ麺】(岩手県)
茹でたうどんを皿に乗せ、甘辛い肉味噌や刻んだ長ネギ、キュウリを盛り付ける。
中国の家庭料理「炸醤麺(ジャージャー麺)」がルーツで、第二次世界大戦時に旧満州で食べた味を、帰国後に屋台で再現したのが始まりとのこと。

※写真はPhotoACより「盛岡じゃじゃ麺」
【こんにゃく味噌おでん】(群馬県)
群馬県の特産品であるこんにゃくを切って串に刺し、たっぷりの味噌と酒で煮込み、味噌だれを塗って食べる。一部の地域では、こんにゃくの水気を切るため布巾に思い切りたたきつけることから「ひっぱたきおでん」とも呼ばれている。
【落花生味噌】(千葉県)
千葉県は落花生収穫量が全国の8割を占める。農家の人たちが市場に出回らない規格外の落花生の活用方法として考案した料理。各家庭で好みの味噌や味付けでつくられ、酒のつまみやご飯のおかず、お茶請けとして食べられている。

※写真はPhotoACより「ピーナッツ味噌」
【味噌田楽】(愛知県)
豆腐を切って串に刺して焼き、八丁味噌などの赤味噌に木の芽を乗せたり、すって混ぜ込んだりした味噌だれを付けて食べる。こんにゃくやサトイモを使ったものもあり、家庭でもつくられている。
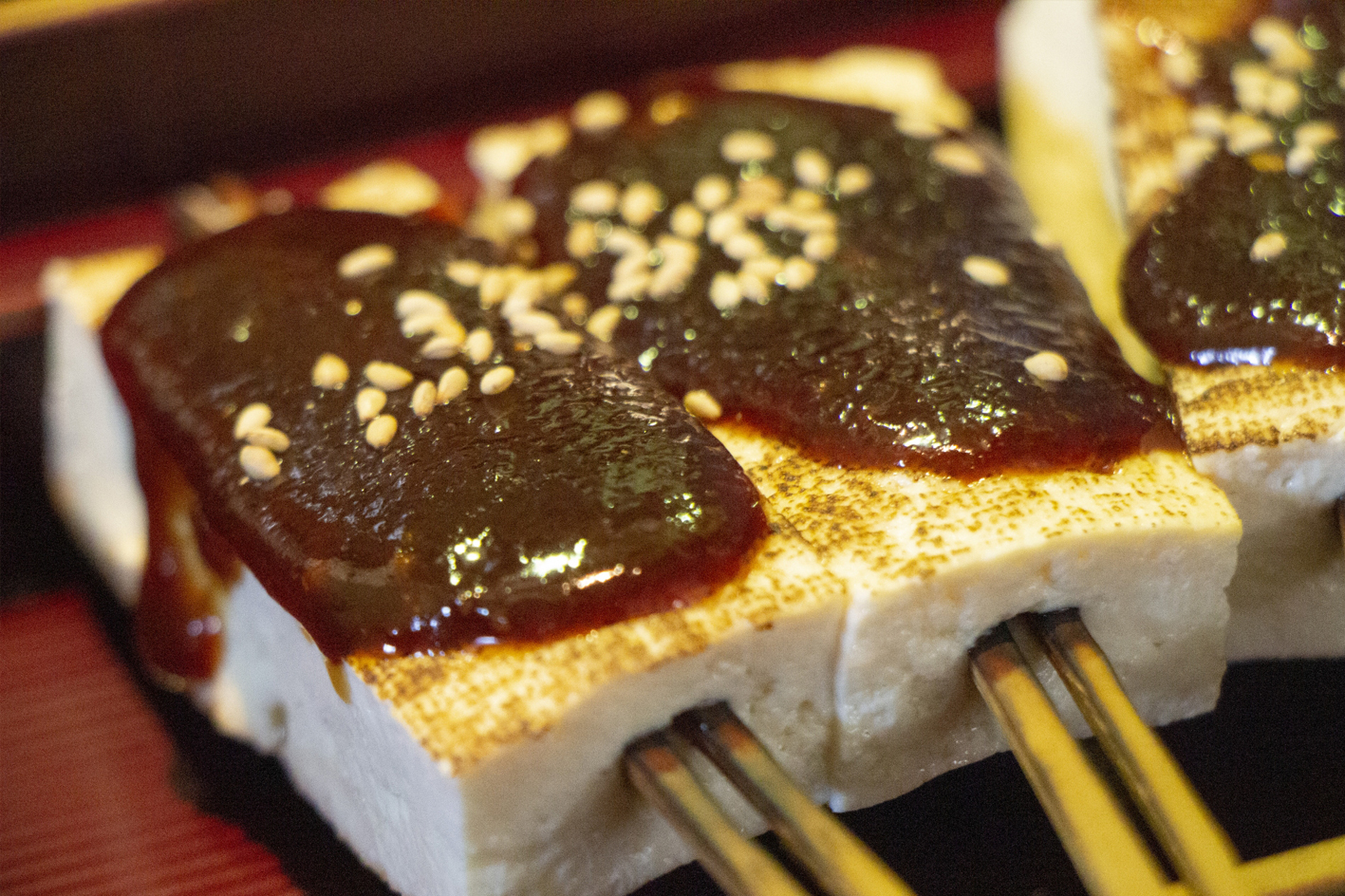
※写真はPhotoACより「味噌田楽」
【煮味噌】(愛知県)
ダイコン、ニンジン、ゴボウ、サトイモなど、四季折々の食材を味噌で煮込んだ料理で、「味噌煮」とも呼ばれる。味噌とみりんで味付けをする場合や、味噌と出汁で味噌汁風にする場合など、家庭によってバリエーションがある。
【味噌煮込みうどん】(愛知県)
八丁味噌仕立ての汁にコシの強いうどんを入れて煮こんでつくる、愛知県を代表する麺料理のひとつ。土鍋を使い、油揚げや鶏肉、かまぼこ、ネギを入れ、最後にひと煮立ちさせる前に卵を割り入れるのが一般的な食べ方とのこと。

※写真はPhotoACより「味噌煮込みうどん」
【味噌カツ】(愛知県)
昭和40年代、カツに豆味噌でつくったたれをかけて提供したのが始まりという説が多数ある。豆味噌をベースに砂糖やみりんを加えて出汁で伸ばしたたれは、濃厚でコクのある甘辛い味わい。

※写真はPhotoACより「味噌カツ」
【ふな味噌】(愛知県、岐阜県)
木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)ではフナなどの川魚が豊富に獲れ、重要なタンパク源として食してきた。フナを大豆と一緒に弱火で時間をかけて火を入れ、豆味噌(赤味噌)と砂糖を加えてさらに煮詰める。赤味噌により川魚特有の臭みが消え、旨味が増すとのこと。

※写真はPhotoACより「鮒味噌」
【朴葉味噌】(岐阜県)
落葉広葉樹の朴の葉の上に味噌を乗せ、炭火などで焼きながら食べる。林業が盛んだった飛騨地域で、山仕事を生業とする人たちが朴葉を皿の代わりにして味噌を焼いたのが始まりと言われている。

※写真はPhotoACより「朴葉味噌」
【漬物味噌煮】(岐阜県)
塩気の強い豆味噌の「郡上味噌」と煮干し出汁の鍋に、白菜の切り漬けを入れて煮込む料理。家庭料理として親しまれ、季節の野菜や肉などを入れて食べる。
【豆腐の味噌漬け】(熊本県)
豆腐の水気をよく絞り、塩分濃度が高めの味噌に漬けたり、砂糖をまぶして味噌に漬けたりしてつくる料理。硬めの豆腐が用いられ、豆腐を常温で長期保存できるようにしたもの。半年ほど漬けた豆腐には、ウニやチーズのような濃厚な風味があるとのこと。薄くスライスして、ご飯に乗せたりお酒の肴にしたりする。

※写真はPhotoACより「味噌漬け豆腐」
【冷汁】(宮崎県)
魚のすり身に、炙った味噌とすりゴマなどを合わせて味を整え、豆腐やキュウリ、青ジソ、ミョウガなどを加える。魚の骨や昆布などでとった出汁で伸ばして冷ましたものを、熱々の米飯や麦飯にかけて食べる料理。「すったて」、「つったて」と呼ぶ地域もある。

※写真はPhotoACより「冷や汁」
【地鶏の味噌ころばかし】(宮崎県)
「ころばかし」とは県西地方の方言で、鍋の中で煮転がすこと。昔から伝わる家庭料理のひとつ。一口大に切った地鶏とショウガを鍋で炒め、中火でやわらかくなるまで煮て、みそと砂糖を加え煮詰める。こんにゃくやダイコン、ゴボウ、ニンジンの乱切りを加えることも。
【豚味噌】(鹿児島県)
豚バラのブロック肉を湯がいて一口大にカットし、粒味噌と砂糖、カツオ節、落花生の粉と混ぜ合わせる料理。ごはんや豆腐、うどんに乗せたり、おにぎりの具にしたりして食べる。

出典:農林水産省Webサイトより「豚味噌」(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/butamiso_kagoshima.html)
<参考サイト>
・うちの郷土料理:農林水産省
https://www.maff.go.jp/result.html?cx=015840603635610229114%3Ad5nyfxhiq78&ie=UTF-8&q=%E5%91%B3%E5%99%8C&sa=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&siteurl=www.maff.go.jp%2Fj%2Fkeikaku%2Fsyokubunka%2Fk_ryouri%2Fsearch_menu%2Fmenu%2Fnimiso_aichi.html&ref=&ss=674j140506j11#gsc.ta
・全国みそ料理めぐり
https://miso.or.jp/museum/miso_culinary_tour/
・愛知ご当地グルメ図鑑 みそかつ
https://www.tabemaro.jp/gourmet/misokatsu/
・豆腐の味噌漬け
https://traditional-foods.maff.go.jp/menu/toufunomisoduke
⑨ なめ味噌や、海外の味噌に似た調味料とは?
日本には、味噌汁や料理に調味料として使う味噌だけではなく、そのままおかずとして食べる「なめ味噌」というものもあります。
また海外にも、味噌に似た調味料がありますので、いくつか調べてみました。
【金山寺味噌】(和歌山県、千葉県、静岡県など)
なめ味噌の代表的なもの。3種類の穀物(米・大豆・ハダカムギ)に麹菌を付けて麹にし、ウリ・ナス・ショウガ・シソなどの野菜を合わせて発酵・熟成させてつくられる。和歌山では伝統的に茶粥と一緒に食べるとのこと。

※写真はPhotoACより「金山寺味噌」
【そてつ味噌】(鹿児島県奄美、沖縄県粟国島)
原料は、ソテツの実から取ったデンプンと玄米を麹にしたソテツ麹と、大豆やサツマイモ、塩。ソテツの種子を主原料とするものと、玄米を主原料とするものがあり、後者はなめ味噌として食べられているとのこと。
【豆板醤(トウバンジャン)】(中国)
ソラマメに唐辛子と塩を加え発酵させてつくる、中国の代表的な唐辛子味噌。麻婆豆腐や担々麺などの中華料理に欠かせない調味料。生のソラマメにカビづけをしてソラマメ麹をつくり、塩漬けにして発酵後、唐辛子を加えて熟成させるのが、伝統的な製法とのこと。

※写真はPhotoACより「麻婆豆腐」
【甜麺醤(テンメンジャン)】(中国)
回鍋肉や北京ダックなどに使われる中華甘味噌で、小麦粉、塩、麹を発酵させたもの。小麦本来の甘さが引き出されていて、料理にまろやかなコクと甘みを与える。日本では大豆を使ってつくる場合もあるとのこと。

※写真はPhotoACより「北京ダック」
【コチュジャン】(韓国)
ビビンパやプルコギなどの韓国料理に欠かせない唐辛子味噌。甘さと辛さが調和しており、コクのある味わい。「メジュ」と呼ばれる、もち米などの穀物に煮大豆をすりつぶして納豆のように枯草菌で発酵させたものに、醤油・唐辛子を加え、さらに発酵・熟成させてつくる。

【マーマイト】(イギリス)
ビールの製造過程で発生する酵母に塩を足し、砂糖を少し入れて煮詰めてつくる発酵食品。イギリスではトーストに塗るのが一般的な食べ方で、スープや煮込み料理に入れることもあるとのこと。こげ茶色でドロッとしていて独特のにおいと味わいがある。
【ベジマイト】(オーストラリア)
「マーマイト」に似た食品で、さまざまな野菜をイースト菌で発酵させたもの。黒いペースト状で、八丁味噌、アンチョビ、チーズ、醤油を足したような独特の塩辛い味と、ビール酵母のような発酵臭が特徴的。
ニュージーランドには「ビタマイト」という似た食品があるとのこと。
<参考サイト>
・世界の料理は微生物であふれている!|世界の発酵食品10選
https://micsmagazine.com/basic/2438/post
・酵母の力で体の内側からきれいに!イギリス発の発酵食品「マーマイト」の魅力
https://www.marukome.co.jp/marukome_omiso/hakkoubishoku/20190710/11401/
・マズいのにハマる人続出!? 謎の調味料「ベジマイト」ってなんだ
https://macaro-ni.jp/33137
⑩ 《美味しい素麺》手延べ黒ごま麺 編
味噌に合う手延べ麺と言えば、石井製麺所の中では、この「手延べ黒ごま麺」もそのひとつだと思います。
三代目個人の嗜好ですが、豆板醤(中国の代表的な唐辛子味噌)とにんにくを利かせた濃厚な味付けの担々麺スープで食べる「手延べ黒ごま担々麺」は美味しくてハマります。
「黒の食材」を練り込んだ“健康麺”ですので、冬におすすめしていますが、夏には汗が噴き出すほどの辛い味付けで、味わってみるのもいかがでしょうか。
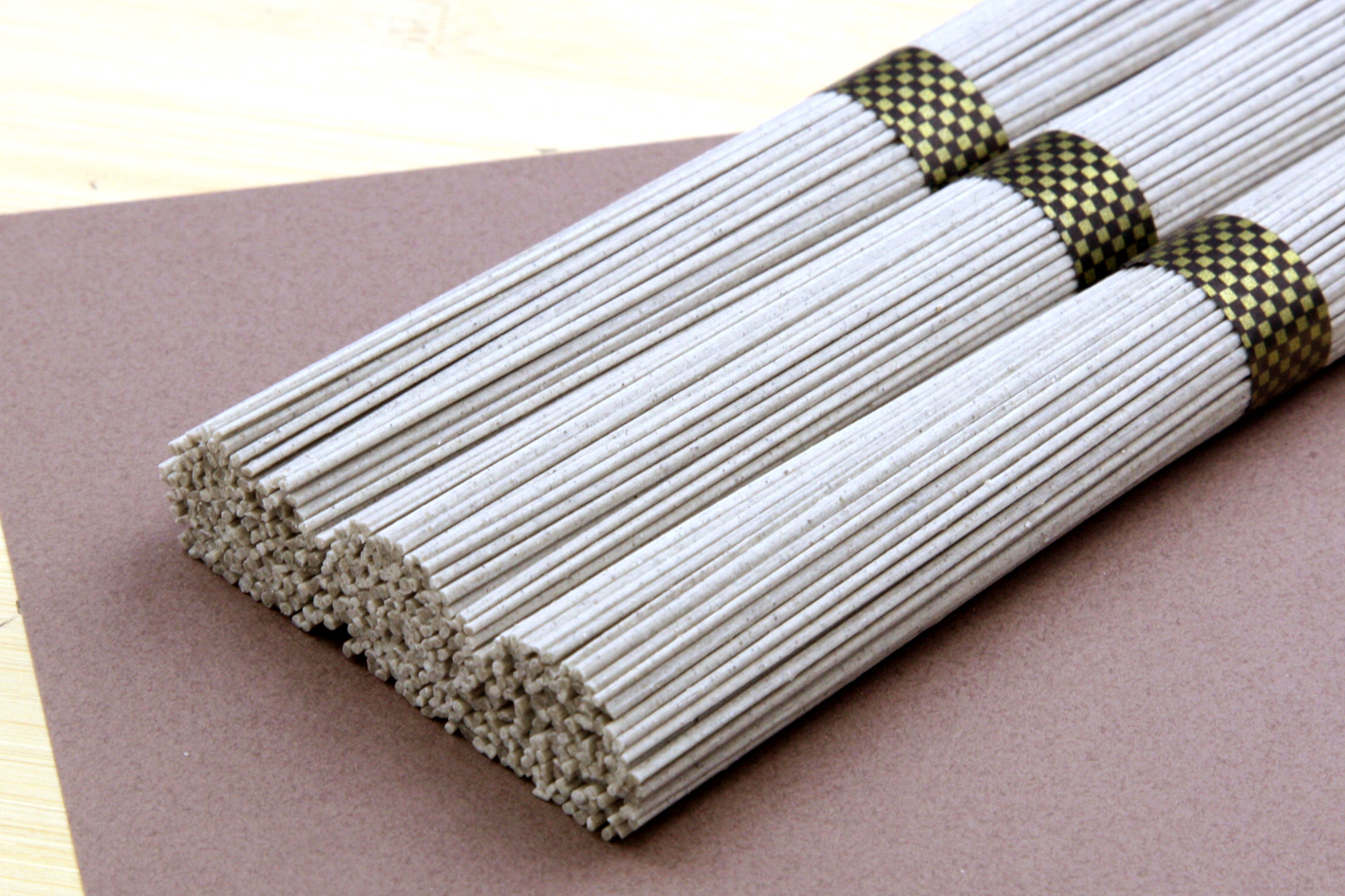
《石井製麺所オンラインショップ》 https://141seimen.thebase.in/
《手延べ黒ごま麺》 https://141seimen.thebase.in/items/69195918
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、色々な産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、様々な素麺の情報を発信できれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。
【お!いしい けんぶんろく】 Vol.33
栄養成分の機能性について/ビタミンC・クエン酸
早いもので、5月1日より「手延べレモン素麺」を販売再開いたします。
この時期だけの味覚としていつもご好評をいただき、これまでにたくさんの方にお召し上がりいただいております。
下の写真は、そのレモン素麺を乾燥しているところです。
レモン素麺が始まると製麺所は、とてもフルーティな香りでいっぱいになります。
普段は小麦粉とごま油の芳ばしい香りでいっぱいですが、この日はレモンの香りが一際心地よい時間です。
ただレモン素麺は、ノバシから乾燥にかけて非常に気をつかう、なかなか製麺の難しい素麺のひとつなんです。
レモンに含まれる成分のせいだと考えられますが、とてものばしにくく、通常の素麺に比べて長い熟成時間が必要です。無理にのばしてしまうと、干している(乾燥させている)ときにも「プチプチ」と切れてしまうことがあります。
そうなってしまうと手の施しようがありません。。。
そうならないためにも、湿度や温度、水や塩加減に細心の注意を払いながらいつも製造をしています。
素麺づくり…特にレモン素麺は、干すまでに品質が決まるといっても過言ではありません。
(もちろん干してから、裁断、包装して出荷するまでにも大切な工程はありますが…)
そのため、従来の白い素麺のように、“いつもの”つくり方では上手く行きません。
小麦粉のブレンド割合を調整したり、のばす工程で特注の道具を使用するなど、さまざまに工夫を凝らして独自の製法を用いています。
もし機会がございましたら、「そんな手間暇の掛かる素麺なんだな〜」と思い出していただきながら、召し上がってみてください。
今回は、そんなレモンに多く含まれているという「ビタミンC」や「クエン酸」について調べてみました。
パッと思い浮かぶのは、酸っぱい食べ物で、なんとなく「ビタミンC」も「クエン酸」も同じように思っていましたが、実は全然別の物でした。
私三代目も大学生の時にアーチェリー部で副主将を務めた経験がありますが、暑い時期に集中力を高めたり健康に気を使う時にはいつも、「ビタミンC」や「クエン酸」を意識して活用していた記憶が蘇ります。
夏に失われがちな成分と聞きますから、やはり暑い時期には意識して摂取したいものですね。
ちょっとした気遣いで暑い夏も健やかに過ごせるヒントもあると思いますので、今回も最後までお付き合いただけましたら幸いです。

【目次】
① ご存じですか?!ビタミンCとクエン酸の違いとは?
② オレンジ果汁から発見されたビタミンC
③ 体内でつくれないビタミンC、摂取のコツは?
④ グルテン形成を助けるビタミンC
⑤ 紀元前から健康効果が注目されてきたクエン酸
⑥ クエン酸の効率的な摂り方や食べ方の工夫
⑦ 素麵の茹で水に梅干しを入れるとクエン酸の力で歯応えUP!
⑧ 《美味しい素麺》手延べレモン素麺編
① ご存じですか?!ビタミンCとクエン酸の違いとは?
同じものと勘違いされることがある「ビタミンC」と「クエン酸」は、まったく別の物質です。
どちらもレモンなどの果物に多く含まれる水溶性の有機酸であり、酸っぱいイメージがあることから混同されてしまうようです。
ビタミンCは体内でつくれず、食品からの摂取が必須の栄養素です。
酸味はありますがクエン酸ほどではありません。
レモン果汁にはビタミンCの100倍以上のクエン酸が含まれるとのことで、レモンの酸味の主成分はクエン酸だそうです。
クエン酸は体内で合成でき、食品からの摂取が必須ではありませんが、炭水化物のひとつとしてエネルギー源になります。
ビタミンC とクエン酸それぞれについて詳しく調べてみましたので、次の段落からご紹介します。

<参考サイト>
・クエン酸とビタミンCの違いは?【全く違う別の物質です】
https://kagakucook.com/citric-acid-is-not-vitamin-c/
・クエン酸とビタミンCは違うもの?相乗効果で疲労回復!それぞれの効果と豊富に含む食べ物
https://kosodate-yakuzaishi.com/citric-acid-vitamin-c/
② オレンジ果汁から発見されたビタミンC
ビタミンとは、体の機能を正常に保つために必要な有機化合物です。
人間の体内では合成することができないので、食物から摂取する必要があります。
その性質から水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分けられ、ビタミンCは水溶性ビタミンのひとつです。
16世紀から18世紀にかけての大航海時代に、新鮮な野菜や果物の摂取量が極端に少なかった船員たちの間で「壊血病」と呼ばれる病気が流行しました。
血管がもろくなり、口や鼻から多く出血する症状が、血液が壊れていくようであったことからその名がついたそうです。
壊血病の症状は他にも、貧血・筋力量の低下・呼吸困難・いらつきなどがあるとのことです。
18世紀中頃、イギリス海軍のジェイムズ・リンドが、壊血病の治療に柑橘系の果物が有効であると示しました。
1919年、生化学者のジャック・ドラモンドが、オレンジ果汁の中に壊血病を防ぐ物質を発見し、1920年に初めて「ビタミンC」と命名されたそうです。
ビタミンCはアスコルビン酸とも言われ、コラーゲンの生成に欠かせない化合物です。
コラーゲンは皮膚・血管・軟骨などに存在し、細胞と細胞をつなぐ繊維状のタンパク質です。
ビタミンCが不足するとコラーゲンが合成されないため、血管がもろくなり出血を起こす壊血病の原因になります。
ビタミンCには他にも、鉄の吸収を促進する働きや、毛細血管・歯・軟骨などを正常に保つ働き、皮膚のメラニン色素の生成を抑え、日焼けを防ぐ作用、ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を強める働きがあります。
また、抗酸化作用が注目されており、がんや動脈硬化の予防、老化防止に役立つことが期待されています。

<参考サイト>
・厚生労働省e-ヘルスネット ビタミン
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-027.html
・ビタミンCの働きと1日の摂取量
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/vitamin-c.html
・ビタミンCの必要性~歴史から見るビタミンC~
https://www.mpc-lab.com/blog/20200604
・ビタミンCの働きと1日に摂取する目安量は?ビタミンCを多く含む食品も紹介
https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?id=180&category=health
・ビタミンCを多く含む食品
https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/vitamin-c.html
③ 体内でつくれないビタミンC、摂取のコツは?
ビタミンCは体内で、活性酸素を消去したり、コラーゲンなどをつくるのに必要な酵素の働きを助けたりすることで多く消費されます。
また、ストレスや喫煙などによっても消費量が多くなることが分かっています。
ビタミンCの推奨摂取量は、成人で1日100mgとされています。
余剰分は体外に排出されますが、過剰摂取による不調が現れたという報告もあります。
1度にまとめて摂取するよりも、1日3回の食事の栄養バランスを整えてこまめに摂取することが理想だそうです。
ビタミンCは、柑橘系の果物や野菜など、身近にある様々な食材に含まれています。
【1回の食事量に含まれているビタミンCの含有量】
・パプリカ(赤)生:1/2個(65g)あたり111mg
・キャベツ生:50gあたり21mg
・ブロッコリーゆで:1/2株(80g)あたり44mg
・キウイフルーツ(黄)生:1個(80g)あたり112mg
・イチゴ生:5個(75g)あたり47mg
・ミカン生:1個(100g)あたり35mg
ビタミンCは水に溶けやすく熱に弱いため、加熱調理で何割かは損失してしまうといわれているそうです。
調理時に水や熱に接する時間を短くすることや、煮出した汁ごと食べる、電子レンジを活用する、など工夫したいものです。
なおジャガイモやサツマイモはビタミンCがデンプンにより保護されているので、調理後もほとんど分解されず残っているそうです。

④ グルテン形成を助けるビタミンC
私たちの素麺づくりにおいて、その出来を左右する小麦粉の「グルテン」がビタミンCの影響を受けるらしいということで、調べてみました。
グルテンは小麦粉独自のタンパク質で、こねたり練ったりすることでできる繊維状の組織です。
グルテンにはグルテニンとグリアジンという2種類のタンパク質があり、この2つが絡み合って形成されます。
生地を引き伸ばす工程を繰り返す手延べ製法では、グルテンの向きが揃うことにより、ツルツルしたなめらかな食感が生まれて美味しくなります。
ビタミンCには、グルテンの中のゴムのような役割を担うグルテニン同士の結合を助ける働きがあるため、結果として生地の弾力性が高まりコシが強くなるとのことです。
昔から、パン生地に柑橘系の果汁を加えると品質の良いパンができることが知られていたそうです。
1938年にはビタミンCが製パン性の向上に寄与していることが証明され、その反応機構はある程度解明されています。
ビタミンCが空気中の酸素との接触などにより酸化され、酸化型ビタミンCとなります。
これが間接的に反応してグルテンの結合を進めるなどの働きにより、生地の弾性が高まるということです。

<参考サイト>
・パン作りを科学的に解説!絶対に失敗しないパン作りの基礎~グルテンに影響する食材~
https://okashikagaku.hatenablog.com/entry/2020/01/28/%E3%83%91%E3%83%B3%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%82%92%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AB%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%91#%E3%82%A2%E3%
・グルテンに影響を与える材料
https://note.com/otsukayosuke/n/n4c3a27ea2ee8
・グルテン
https://www.patissient.com/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3/
・製パンにおけるビタミンCの働きとは
https://www.panpedia.jp/lesson/pdf/2013.10_4-7.pdf
⑤ 紀元前から健康効果が注目されてきたクエン酸
クエン酸は、酢や柑橘類に含まれる酸味成分のひとつ。
人間が生きていく上で重要なエネルギーをつくり出すために必要不可欠な成分です。
また乳酸の生成を抑制し、疲労回復にも役立つとして、クエン酸を多く含む食品が古くから親しまれています。
クエン酸は1784年にスウェーデンの科学者シェーレがレモン果汁より発見しましたが、それよりはるか以前からその健康効果が人々に注目されていたと言われています。
紀元前460~377年の古代ギリシャでは、医者のヒポクラテスがお酢の力に注目して様々な病気の治療に利用したとの記録が残っています。
日本でも、4世紀前半頃から初めて食用の酢がつくられるようになったとされており、7世紀初めには酢をつくる官職が置かれていたほど貴重なものとして扱われていたそうです。
1953年、イギリスの生化学者H.A.クレブスにより「クエン酸回路」が発見されました。
クエン酸回路とは、細胞内のミトコンドリアで行われる、体を動かすのに不可欠なエネルギーをつくり出すシステムです。
摂取した食べ物の栄養素が体内に吸収され、酵素やビタミンによって分解される過程でエネルギーがつくられる仕組みのことで、クエン酸はクエン酸回路での化学反応において中心的な役割を担っています。
人間の体は約60兆個の細胞からできていて、ひとつひとつの細胞でクエン酸回路を正常に行うために、クエン酸は非常に重要な役割を持つ成分とのことです。
クエン酸の摂取によりクエン酸回路を活性化すると代謝アップにつながり、ダイエットにも役立つそうです。
他にもクエン酸には、疲労物質である乳酸を分解することにより、疲労回復や筋肉痛を軽減する働きがあるとされています。
また、その酸味により唾液や胃液の分泌を促して、食欲増進や夏バテ防止などにも役立ちます。
マグネシウムやカルシウムなどのミネラルの吸収促進、美肌、肝臓の機能改善などにも良いとされています。

<参考サイト>
・わかさの秘密 クエン酸
https://himitsu.wakasa.jp/contents/citric-acid/
・クエン酸の効果とは?お菓子・お料理・お掃除活用法
https://www.kyoritsu-foods.co.jp/feature/kuensan/
・疲労をためない手軽な工夫?疲労回復に役立つクエン酸を上手に取りましょう
https://brand.taisho.co.jp/contents/sports/529/
・クエン酸の効果・効能とは?健康効果が期待できる食品を紹介
https://www.suntory-kenko.com/column2/article/3388/
⑥ クエン酸の効率的な摂り方や食べ方の工夫
クエン酸は体内で合成されますが、体内には大量にためておくことができず、余った分は体外に排出されてしまうので、分散してこまめに摂取するのが良いそうです。
運動した後に摂るよりも運動前に摂ることで、エネルギーの生成がスムーズに行われ、運動中に疲労物質が分解が促進されて疲れが残りにくくなるとのことです。
クエン酸は、レモン、みかん、グレープフルーツなどの柑橘類や梅干し、酢など、酸味のある食べ物に多く含まれます。
大きめのレモン1個に約4g、梅干し1個に1gのクエン酸が含まれているそうです。
クエン酸を多く含む食材と相性の良い組み合わせについて、いくつか調べてみました。
【レモンとはちみつ】
はちみつの主成分であるブドウ糖と多糖は消化吸収が早く、体内ですぐエネルギーに変わるため、クエン酸を豊富に含むレモンと組み合わせることでさらにエネルギー代謝が促進します。
また、レモンのクエン酸がはちみつのビタミンB群の吸収を良くする、酸味が緩和され抗酸化に役立つ皮の部分も食べやすくなる、などの相乗効果が期待できます。
夏にはよくお世話になりました。

【梅干しと鶏むね肉】
鶏むね肉に含まれるイミダペプチドという抗酸化成分が、活性酸素による酸化ストレスから細胞がダメージを受けるのを防ぐとされます。
クエン酸が豊富な梅干しと一緒に摂ることで、エネルギー代謝の促進が期待できます。
クエン酸の働きで鶏むね肉がやわらかくなる効果もあります。

【梅干しと鶏レバー】
梅干しに含まれるクエン酸が、鶏レバーに含まれる鉄分の吸収を高めてくれます。
【グレープフルーツとホウレンソウ】
クエン酸の働きで、ホウレンソウに豊富に含まれるマグネシウムがより効率よく吸収できます。
<参考サイト>
・クエン酸が多く含まれる食べ物は?食べ合わせについても調査!
https://www.marine-bio.co.jp/citric-acid/article13/
⑦ 素麵の茹で水に梅干しを入れるとクエン酸の力で歯応えUP!
クエン酸は果物や野菜などに含まれる成分ですが、さらさらした白色の結晶性の粉末状で市販されているものもあります。
クエン酸の働きを調理などに活かすコツについて、いくつか調べてみました。
【根菜類の下ごしらえに】
ゴボウ、レンコンなどの根菜類は、水1リットルにクエン酸小さじ1(3g)を溶かした水につけておくと、黒ずみを防いできれいに仕上がるそうです。
【キャベツの下茹でに】
キャベツを茹でる時にクエン酸を少量お湯に加えておくと、独特の臭みが気にならなくなるそうです。
【大根おろしに】
大根おろしが辛い時に、クエン酸を少量加えると辛みが抑えられて食べやすくなります。
【焼酎やウイスキーに】
焼酎やウイスキーにごく少量のクエン酸を加えると、酸味がさらに美味しくなるそうです。
【素麺を茹でる時に】
鍋にたっぷりのお湯と梅干を2~3個入れ、沸騰した後2~3分煮ます。
そのお湯で素麺を茹でると、歯応えがぐんとアップします。
梅干しを入れることで茹で水が弱酸性に傾くと、麺のグルテンがしなやかになり、結果としてデンプンが溶けにくくなり、歯応えを保ちながらのどごし良く茹で上がるとのことです。
小豆島の製麺所の方に聞くと、このへん、色々な各ご家庭での食べ方や説があるようです。
茹でている時に梅干しを入れる方がいたり、お酢を入れたりする方もいらっしゃいます。
あと、ちなみにですが、茹でている時に「びっくり水」を入れる方がいらっしゃいますが、石井製麺所ではおすすめしません。
お湯の温度が下がってしまい、茹で時間がかかることでシャキッと茹で上がらなくなってしまいます。
しっかりとぐらぐらと沸騰したお湯に入れて茹でることをおすすめします。

<参考サイト>
・そうめんの科学
https://ntv.co.jp/megaten/oa/20180624.html
・コシのある素麺は梅干しでつくる!
https://note.com/travelingfoodlab/n/n0b2920e0f7e3
⑧ 《美味しい素麺》手延べレモン素麺 編
5月1日から販売を再開する「手延べレモン素麺」。
袋を開けて麺を茹でると、レモンの爽やかな香りが広がります。
酸っぱい素麺ではないのですが、レモンらしいほのかな香りと、すっきりとした味わいが特徴で、
コシの強い麺が夏の暑い日に気持ちよくのどを通る素麺に仕上がっております。
レモン(に含まれる成分)と素麺(特に小麦粉)は上述のように、実は、とても良好な関係のものなんです。
ですから、レモン素麺はちょっと“ミーハー”なイメージがあるかも知れませんが、製法、食べ方、食べる方の健康を考えた“良い出来”の素麺だと自負しています。
多少手間は掛かるのですが、毎年楽しみにしてくださるお客様もいらっしゃっいますので、私たちも精一杯製麺に取り組んでいます。
このブログを書いている時点で、販売はまだ解禁になっていませんが、販売再開の際には一度お召し上がりいただけましたら幸いです。
『お!いしい けんぶんろく』について
本ブログでは、新製品開発のためにデータベース的にいろいろな素材や成分について調べたものを綴ったものです。色々な食品やそれにまつわる産地を調べたり、食べ方を探求したり、将来的には実際に産地に行って交流を深めたり…そんなことができれば良いなと考えています。まずは勉強からと言うことで、小豆島もそのひとつですが、日本の素麺や麺類について調べながら、幅広く食品の知識を広げることができれば良いなと考えています。もし、間違いなどあれば、ご指摘ください。たくさんの方の“素麺のデータベース”になればと考えています。
色々な情報を紐解きながら…なので、間違いや勘違い、伝承だと色々な解釈があったりすると思いますので、優しい気持ちで見守っていただき、一緒に学べる場にできれば幸いです。